ZENKEI AI ポッドキャスト、シーズン34は2022年10月26日に開催した ZOOMライブの模様です。
この日のテーマは「最近の話題から〜2022年秋〜」でした。
エピソード2は、前座その1「個人出版とその周辺」の後半です。
このブラウザでは再生できません。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
ビデオ見れる人はこちらからご覧ください。
(以下は、OpenAI の Whisper を使って文字起こししたものを修正したものです。)
** 注:以下は未編集の草稿です **
こんにちは。ZENKEI AI FORUMです。
みなさんこんばんはです。2022年、早いね、10月26日。10月の、もう最終水曜日になりましたが、 ZENKEI AI フォーラムです。
なんかねー まあまあいいですねあの ai フォーラム技術書店で技術書を書いているという文脈でね同人誌活動はサークル化するんです からはいでこれね文学振り回って書きましたが なんかねスイッターを見てたらね技術書店終わってねで前期 ai フォーラムは2年前にオンラインなってコロナ になったからこういう活動にあの踏み込めたってか踏み込んだわけですけども 8こういう技術同人誌活動というものに踏み入れて足を踏み入れてまだ2年しか経ってないんですけども でももう結構した気になってるんだけどそこしてたらねタイムラインに この文学フリマーに本を出しますとかいう人がねの投稿とかタイムライン流れてくるね文学振りまっていうのはまあまあ想像する に技術書店というのは技術書の同人誌イベントなんでで文学振りまっていうのはきっと文芸系の同人誌活動っていうのは まあ当然ありますからねそうそうそれなんだろうなっていうふうに思ったんですけども なんだろうあのちょっと興味が湧いて言ってみたいですねサイトにそしたらでそもそも文学振りまって何っていうのを思うじゃないですか サイトに行って成り立ちみたいなのを探したら大塚英二不良再建としての文学 っていう2002年の 群蔵っていう雑誌に書かれた出された文章っていうのがドーンと載ってたんですね これがどうも出発点らしいかったんですねこれ結構長い分子もなんだけどあのつらつらね見っけでねなんだろうと思って読んだんだ けども感動したん これ結構感動したねあの20年前っていう 現実にもなんか重いものを感じたしこの内容にもあのなんかすげーと思ったんでそれを ai フォーラムのこの場でね ちょっとシェア共有したいなと思ってワンセクション入れましたちょっとお付き合いください ねまあ 興味ある人は見に行ってくださいっていうことなんですけども簡単に何に感動してんのっていうのを簡単に言っとくと20年前 もうすでに出版業界は社用産業だと言われていて なんか業界を刷新しないといけないと生き残っていけないとかっていうようなあのムードだったらしいですね 日本なんか何も変わんないだろうと思いますけどねあの20年経ってもみたいなねあのだ今だってねあの本屋さん大変とかっていうの何も変わってないじゃないですか っていうのはまあでも考えたらねー オーバードクター問題とかっていうの何も解決されないでかつての若手研究者はあのもうね教授みたいな権威の方にいて 事態は何ら変わってないっていうのを見ればねまあ 世の中っていうか日本っていうものはどこもそうなのかなっていうような 話はやめておいてですねえっとこのね文学振り回しここで大塚さん はなんか多分ねあの 文学プロパーな人たちなのか人なのかから多分論争ってかイチャモンつけられてたみたいですねあの詳しくは追ってません高校の文書しか僕読んでね でそれに対する8反論じゃなくて返答なんですねそれ素晴らしいなと思ったんですけどもバカ野郎って言われてバカ野郎って返す っていうのはよくあるパターンですけどもa 建設的な提案を返したんですねこれねえっとで出版っていうものの置かれている状況っていうのを分析して でこの人この人は僕多分アニメよりの人なのかなって認識をして間違ってたらごめんなさいですけどもあの なんかね宮崎駿の読んでてなんか名前を見てなんか単行本1個からあの山文庫バッなんか買った記憶がありますけどちゃんと読んでない ようなa で 業界分芸っていうか文学っていうものまあ生涯難しいですよねあの ピュアなエンタメとは違うっていう部分の難しさっていうのは金にならないという意味でねあのわかるんですけども 全然状況どういうふうに 建設的にマーケットっていうかねあの市場経済を回していくようにするかっていうんで キーワードはねあのデスクトップパブリッシングって言うかね電子化しましょうっていうのが一つと 8そうやって出版のコストを下げて利益を出すみたいなね まあ当たり前のことで今流に言えばこれデジタルdx ですね実際となすフォーメーション 20年前だからそんなことがないんだけどそういうこと言っているんだなぁという感じでしたねでまぁ 素晴らしいと思ったのはいうだけではなくてそれをじゃあ実現こうしたら実現できるんだっていう形でね 書きっぱなしにしないようにと赤で書きましたわで 文学コミケってここ書いてありますがなんか商標の関係でね8正式には文学振りまというイベントをやる同人活動を導入して 文学っていうものをa 対象に広めるっていう民主かな そういう活動自分の旗振りで自分の責任でやるとで僕が1回だけだけども まず立ち上げるというふうに言って この後スピード感がすごいのどんだねこれ雑誌イベント掲載して賛同する人はお深は書を送ってくれと参加表明として でそれは締め切りは1ヶ月だと1ヶ月のうちに参加表明をしてくれる人が50人いたらこのイベントを開催すると 50に集まらなかったら諦めるやらないでその結果何が起きたかというと 何に集まったのが僕じゃないですけども20年前に文学振りまっていうのが始まって 今日とかもね今日とかもタイムラインとか見てたら今度の文学振りまのどこそこに今度出そうと思いますとかっていうのが流れてるわけですよ20年きちんと継続 sdg ずねっ それがこのタイム間でね記事出して1ヶ月締め切りをやるかやらないかつって融資がゴンって集まってそれがきっかけで始まって20年続く このダイナミックスすごいなぁと思う思いましたんでその感動ねみんなに伝えたいなと思ってあのわざわざここに時間を割いてるんですが これね思い出したのね思い出したのはデルクシバーズのテッドのねハウチングしたとムーブメントのビデオねもうこれやーと思った これ見てない人は見てくださいあのあの見てる人前提でここここに書いてありますがこれ後で読みたい人におねがいし これ見てねあーって大塚さんっていうのをこのシェアレスダンシングガイだとクリーズ以外だと でねあの50人集まった人たちはこのねフォロワーだとファーストフォロワーファーストフォロワーが大事なんだよと あのムーブメント維持するためにはで大塚さんはねあのそうムーブメントが大事でリーダー よりもムーブメントが大事でしょっていうポイントもまさにその通りだしすごいなぁと思いましたでね なんかこの精神性っていうかね文学僕はあの僕全部あの リアルタイムってかな時間軸に世間の動向と関係なしにあの後じえ的に全部レトロスペクティブに物事をわかるなんかあの間の悪い人間だなぁと思いますが僕とか はね同人活動は最近2年前さっき言って2年前の技術書店からが書店ですからねそこから今20年前の分 クリマン出来事すげーすげーって言ってるっていうなんかあのまあ面白いことをやってるんですけど じゃあみんなとね話し合わないかなそれで でこのラインでさっきね喋った amazon のkindle デジタルダイヤクトパブリッシングのペーパーパックサービスっていうのは 時間があっちゃこっちゃいってますけれどもそれの今日的なね去年とか今年とかの 適合でしょなんかね 点がつながってる気がしてるなぁって思ってますんでこの時点でねもうまとめる強引にまとめるんですけど何が見えかけてるのか というね結局20年のタイムスパンによる出版業界のデジタルトランスフォーメーションの話なんだと 今ねそういう落とし方が自分の中でできるのかなぁと思って考えてるって話なんですけども プレイヤーねどういうプレイヤーがいるかマーケットですからね経済圏 その経済圏であのエージェントとして動いているプレイヤーはどういうカテゴリーの人たちがいるかというと ね言わずもがなですけども作家 生産者作家で出版社 流通の人たちで本屋さん お店ですねで本屋さんに行って生産物を買うお客さん読者 こういうプレイヤー普通のマーケット同じですねあの農業だったらね農家の人が農産物を作って スーパーマーケットチェーンなのかなんかわからない大企業がサラリーマンがっていうねあの配送してではスーパーマーケットお店 街のお店に果物が並んで野菜が並んでそこにa ねお客さんとして買い物に行くと そういう構造ですねどこにでもあるで出版業界の問題点と大塚さんがあのすべて指摘してますがまあ僕なりに 簡単に4行でまとめるとっていう話です作家の取り分が少ないと 陰性10%か詳しい数字はの大塚さんの見るなり他の同人誌活動なんかねあの同人 活動とはっていうなんか冊子僕買いましたけどもあれにも詳しく書いてありましたけどね でで作家の取り分が少ないっていうのと同時にこの両端ですね 本屋の取り分でもう少ないですねあの本屋さん一冊万引きされたらもうあの大変になっちゃうっていう話が有名です けども本体価格の10パーとかもっと引っ張ったりするの 詳しくはあのググればわかるんですよ知られてないんですけど取り分が少ないとじゃあどこがとってのっても必然的にねこの真ん中がとってるわけですけどね あと法律的にねあのね出版業界はあの再販制度あのね低下っていうものがどういう形である維持されているっていうね これもここが保護されているわけですねであの 参入するのが難しいような流通システムになってるとかそういう問題点があると上に サイクルが硬直化してみたいな話ですねこれに対して20年前に文学振り間っていうのがやったことは何かっていうと 僕の僕のあの朝じぇね2日3日くらいでビビってみて大すげすげーと思った理科解釈は ね作家とお客さんを直接つなぐようないわゆる同人スピリットであるいはコミュニティ経済ファンダム経済って呼ばれてるやつね あのkpop とかいう奴の話に僕の中ではつながってるそういう活動したとつまりは正しい意味の中抜きをしたと ねピンハネするっていう中抜きご用ではなくてあのいらない 中間マージンを取り除くっていう中抜きをしたっていう活動が20年前ねあのっていうのが文学振り間という出来事だったのかなぁ ねそれは同人活動であり今風な新しい経済活動っていうふうに見ることもできるのかなっていう話僕視点で言うとね ねここ数年 amazon がやったことっていうのはじゃあこの枠組みで考えると何なんだろうって思うとamazon はここの大ボスみたいですかね書店の大ボスみたいですからね書店の大ボスさんがつまり文学振り間は作家と読者をつなげたんだけども書店の大ボスが個人作家個人作家を 名にですね出版社を会社内で8 amazon っていうお店を 使えるようにしてくれたっていうふうに読むことができるね ああそれは一種の民主化そういう意味では民主化だねっていう風な解釈がない立つ それにとどまらず紙の本を出せるっていうことねでってことは であのペーパーオンデマンドあんまこれはというの紙のも出せるということは同人誌活動においてはねあの重要なプレイヤーっていうのはあの 印刷屋さんっていう同人誌印刷屋さんっていうのは重要なプレイヤーとしているなぁっていうのは僕は2年経験してはねあの感じてるんですけども amazon がそこをもう食っちゃうみたいだね街のちっちゃい本屋さんを amazon が食っちゃって街のちっちゃい本屋さん大変と言ってるところに 街のちっちゃい印刷屋さんも amazon っていうでかいところが食っちゃうっていう構造もあるのかなぁと思ってなんかいたしかいしっていうか うーんと思ってであとあの作家視点で言うと amazon のペーパーパックサービスってのはプリントオンデマンドっていうのが本質的なんですけども 在庫を持たない紙の本の出版システムでありその結果としてサービスとしては本を出版っていうイベントに対して初期投資が 作家が制作者が負担する初期投資0 なので作家の生産入コストがゼロになっちゃったこれはこれインパクトでかいと僕は思いますね もちろんここでさっきも言ってるねオンデマンド印刷のクオリティに我慢ならんっていう人は自腹で初期投資をかけていい 本を作ればいいしその場合はあれだね自分で isb アイス bn とって入れなきゃいけないよねそこらへんはまた面倒くさくなるでしょうけどね っていう風なあの風景になっているのかなぁとねあの複雑な心境っていうのはさっきも言いましたけれども こういう活動ね特に今 amazon の話をしてますがamazon って なんていうの民主化みたいなねどっちが味方でどっちが敵っていう時のあの権力があってかね あの体制があってかねamazon ってだって 支配側だよねっていうねそこがこういう活動してるっていうんでそこが なんかあれねあの僕は何度も引用している若林系の8楕円なんとかっていう本の中にも書いて あったね amazon っていうのはやろうと思えばこういう 8個人 とか中小の人たちをが 自立できるような空間をコーディネートできるポジションにいたんだか彼らは 意図的なのか意図的ではないのかわかんないけども選択そっちの選択をしないでamazon が仕切るっていう amazon が支配者になるっていう選択をとってるんだよっていう 指摘がどっかにありましたねあの今度きちんとフォローしてあの 引用しとこうかなと思いますが山西そうの辺がちょっとこうもろては上げてやったーって言えない感じを残す 状況なんだなぁとでもベターにはなってるんやなーっていう気は部会社がね 庭川でちょこっと見た感じにおいてはいい方向に行ってのが20年というね時間がかかりつつ デスクトップパブリッシングは個人の活動にやっと音を下ろしてあのっていうねあのパーソナルコンピューターの理想の形が一つできてデジタルと トランスフォーメーションの一つの理想形になっとるのかなっていう気が20年かけちゃいけないような気がしますけどもできてるかなっていうふうな気がしましたね でそうすると次の一手っていうかね今トントントンって流れている時の未来をどういうふうに作るんだっていう視点で当然 考えてくなるときにわかったと8ね歪んだ構造のうち出版社取り継ぎみたいな上に書いたね 悪大化みたいないい書き方して申し訳ないけどもここはほぼあの9問題をほぼ解決されたと そしたらさっきから言ってるよねamazon の独占からの脱却っての次に目指すとこなのっていう ふうになるよなぁと普通ねあるいは苦しいとこどこって言ったらやっぱりね街の本屋さんであったりっていうことねそうすると 次の一手っていうやっぱりこういう地域経済で自立する仕組みっていうのはどういうふうにここに乗っけるかとかっていう話なの かなと思ったりまあ結局は多様性をどういうふうに 持ち込むのかウィンウィンの形に持ち込むのか でまぁコミュニティ経済っていうのはあの同人化みたいなんでね生産者と消費者の垣根を取り除くっていう文脈はほぼ出来上がってるんでマーケットとして機能するようなものとしてはね これをローカル経済としてきちんと回すな商店は同人活動っていうものの中にお店をどう組み込むのかという話なんですか ね思いつきだけじゃないって言うあの 皆さんもこの辺考えてみたらってが一緒に考えましょうってかね考え考えたら面白いんだろうなぁと思い思ってるってことですね うんはいっていうのが前座の 1でしただけ喋っとんだ1時間近く喋ってね前座の位置だけではい えっとしくしくといきますこれはマウスがね不安定なんですよねテレビ



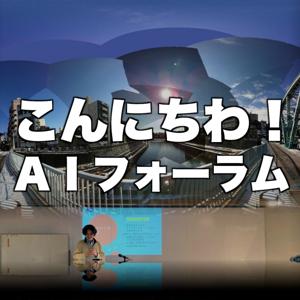

 View all episodes
View all episodes


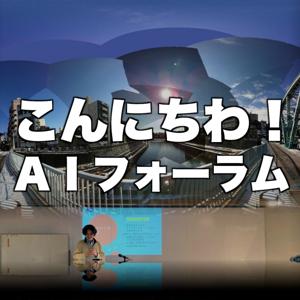 By Kengo Ichiki
By Kengo Ichiki