
Sign up to save your podcasts
Or


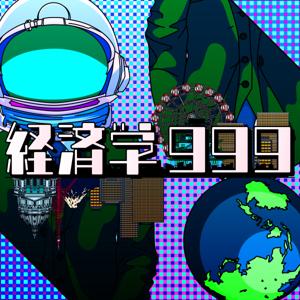

瀧さんに再度ご出演いただき前回聞けなかったマネーフォワードのデータを使った研究論文の経緯、オルタナデータの活用やEBPMのあるべき姿、デジタル行財政改革に対する思い、今後のキャリア展望などについて語っていただきました。
聞き手:今井誠さん(エコノミクスデザイン)、森脇大輔(サイバーエージェント)
10万円給付金の研究へのデータ提供の経緯(1:40~)
▼マネーフォワードでPh.D.取った人が10人出たらかっこいい▼家計調査の弱点を補えるデータ▼社内での優先順位▼海外では会計ソフトと政府が連携▼定額給付金のターゲットを巡る対立▼銀行データを使った先行研究▼銀行データではできないこと▼世帯によって違う給付金の効果が明らかに▼限界消費性向の推定▼政策転換の示唆▼省庁関係者への説明▼ネガティブな反応も▼ダメだったら辞めればいい▼政府のエンドースの必要性▼ヘッジファンド中心のオルタナデータ市場▼家計簿データの代表性の問題▼日銀の研究への協力▼データ利活用における社内ガバナンス体制▼緊急事態における企業データの開放▼データ活用の条件▼方向性のないデータ同士をぶつけてもカオスが生まれるだけ▼目的を定めてコンソーシアムを組むべき▼Howの議論だけでなくWhatの議論を▼データ利活用の「税金」▼リクルーティングには有効▼守りだけでないデータ管理の責任▼データの価値を示すのも企業責任の一端
EBPMの現在地と今後(29:00~)
▼客観的な言葉になってきた「EBPM」▼まずは一回使って次のタイミングではデータが取れるようにする▼あまりにひどい政策への目端がきくように▼家計が黒字でも統合政府が赤字の状況▼家計管理くらいのレベルで財政を管理して納得感を▼システム経費の捉え方を変える▼政府支出のROIに時間削減も含めるべき▼アメリカSECのレポートの衝撃▼霞が関のインセンティブ構造の問題▼各省庁にデータ分析のリソースを▼吉川洋教授のデータサイエンス重視の姿勢▼徴税、統計、貨幣が腐ると国家の体をなさなくなる▼統計を行政業務の近くに▼統計業務を評価をする仕組みに▼仕事には必ず数字はついてまわる▼
今後のキャリアについて(41:30~)
▼仕事に恵まれた▼下駄を履いてる状況▼デジ行財の「財」の部分に想い▼日本にとってタフな選択が待っている▼社会分断をさせずに子どもを産みたい社会に▼理論的には引き裂かれる役をやりたい▼バックトゥーザフューチャーPt.2▼政府はもっとトレードオフを▼池尾先生の「日本経済の隘路」から20年▼家計簿の統合政府版を作る▼予測市場の活用▼Fintechは未来予測のツール
◆参考資料◆
特別定額給付金が家計消費に与える影響に関する研究論文(プレスリリース、論文)
銀行データを用いた研究(論文)
日銀における研究(論文1、論文2)
デジタル行財政改革会議への提出資料(リンク)
プロトタイプ研究所「提言4」(リンク)
池尾和人「銀行はなぜ変われないのか: 日本経済の隘路」(Amazon)
 View all episodes
View all episodes


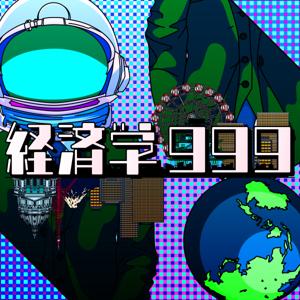 By Daisuke Moriwaki
By Daisuke Moriwaki
瀧さんに再度ご出演いただき前回聞けなかったマネーフォワードのデータを使った研究論文の経緯、オルタナデータの活用やEBPMのあるべき姿、デジタル行財政改革に対する思い、今後のキャリア展望などについて語っていただきました。
聞き手:今井誠さん(エコノミクスデザイン)、森脇大輔(サイバーエージェント)
10万円給付金の研究へのデータ提供の経緯(1:40~)
▼マネーフォワードでPh.D.取った人が10人出たらかっこいい▼家計調査の弱点を補えるデータ▼社内での優先順位▼海外では会計ソフトと政府が連携▼定額給付金のターゲットを巡る対立▼銀行データを使った先行研究▼銀行データではできないこと▼世帯によって違う給付金の効果が明らかに▼限界消費性向の推定▼政策転換の示唆▼省庁関係者への説明▼ネガティブな反応も▼ダメだったら辞めればいい▼政府のエンドースの必要性▼ヘッジファンド中心のオルタナデータ市場▼家計簿データの代表性の問題▼日銀の研究への協力▼データ利活用における社内ガバナンス体制▼緊急事態における企業データの開放▼データ活用の条件▼方向性のないデータ同士をぶつけてもカオスが生まれるだけ▼目的を定めてコンソーシアムを組むべき▼Howの議論だけでなくWhatの議論を▼データ利活用の「税金」▼リクルーティングには有効▼守りだけでないデータ管理の責任▼データの価値を示すのも企業責任の一端
EBPMの現在地と今後(29:00~)
▼客観的な言葉になってきた「EBPM」▼まずは一回使って次のタイミングではデータが取れるようにする▼あまりにひどい政策への目端がきくように▼家計が黒字でも統合政府が赤字の状況▼家計管理くらいのレベルで財政を管理して納得感を▼システム経費の捉え方を変える▼政府支出のROIに時間削減も含めるべき▼アメリカSECのレポートの衝撃▼霞が関のインセンティブ構造の問題▼各省庁にデータ分析のリソースを▼吉川洋教授のデータサイエンス重視の姿勢▼徴税、統計、貨幣が腐ると国家の体をなさなくなる▼統計を行政業務の近くに▼統計業務を評価をする仕組みに▼仕事には必ず数字はついてまわる▼
今後のキャリアについて(41:30~)
▼仕事に恵まれた▼下駄を履いてる状況▼デジ行財の「財」の部分に想い▼日本にとってタフな選択が待っている▼社会分断をさせずに子どもを産みたい社会に▼理論的には引き裂かれる役をやりたい▼バックトゥーザフューチャーPt.2▼政府はもっとトレードオフを▼池尾先生の「日本経済の隘路」から20年▼家計簿の統合政府版を作る▼予測市場の活用▼Fintechは未来予測のツール
◆参考資料◆
特別定額給付金が家計消費に与える影響に関する研究論文(プレスリリース、論文)
銀行データを用いた研究(論文)
日銀における研究(論文1、論文2)
デジタル行財政改革会議への提出資料(リンク)
プロトタイプ研究所「提言4」(リンク)
池尾和人「銀行はなぜ変われないのか: 日本経済の隘路」(Amazon)