1922年頃、賢治が農学校の教え子たちのために作詞して、皆で歌っていたという行進曲です。賢治らしい語彙が輝くその歌は、朝焼けの北上山地の情景に託して、岩手の農業の「夜明け」と、それを担う青年たちに贈るエールでした。
歌詞の二番で「金の鎌」というのは、空にかかる鎌の形をした月(五日月)のことで、ここでは「銹びし鎌」に象徴される古い農業が沈んだ後に、朝日に輝きつつ、若者たちとともに新しい「犂」が現れる、という形になっています。田畑を耕す農具である「すき」は、漢字で書くと、人間が引く「鋤」と、家畜が引く「犂」とがありますが、「鋤」は「鍬」などとともに、江戸時代から使われる伝統的な農具であったのに対して、畜力を利用した「短床犂」は明治末期に完成して普及が始まり、大正時代から昭和30年頃までは、これが全国で広く使用されていたということです。すなわち、この「燦転」たる「犂」は、大正時代の片田舎では、新たな農業の象徴でもあったのでしょう。
歌曲の旋律は、第一高等学校の寮歌「紫淡くたそがるゝ」のものを借用したものです。単純なメロディーですが、歌詞の凛々しい雰囲気とほどよくマッチしていますね。
「夜明け」の歌であることにちなんで、前奏では「起床ラッパ」をイメージしてみました。
<歌詞>
蛇紋山地の 赤きそら
雲すみやかに過ぎ行て
夢死とわらはん田園の
黎明いまは果てんとす
銹びし五日の 金の鎌
かの山稜に 落ち行きて
われらが犂の 燦転と
朝日の酒は 地に充てり
起てわが気圏の戦士らよ
暁すでに やぶれしを
いま角礫のあれつちに
リンデの種子をわが播かん
とりいれの日は遠からず
微風緑樹の 荘厳と
禾穀の浪は きららかに
歓呼は天も 応へなん
ふるふ地平の紺の上
広き肩なすはらからよ
げに辛酸のしろびかり
になひてともに過行かん



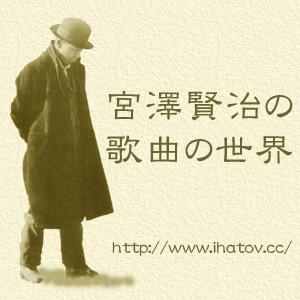

 View all episodes
View all episodes


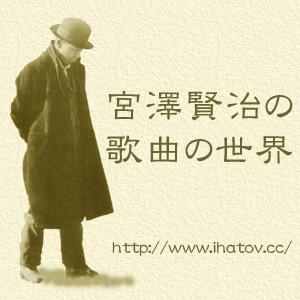 By www.ihatov.cc
By www.ihatov.cc