参照テキスト: 青空文庫図書カード№1813
音声再生時間: 24分30秒このブラウザでは再生できません。
*
(二月×日)
私は私がボロカス女だと云うことに溺れないように用心をしていた。街を歩いている女を見ると、自分のみっともなさを感じないけれども、何日も食えないで、じっと隣室の長閑(のどか)な笑い声を聞いていると、私は消えてなくなりたくなるのだ。死んだって生きていたって不必要な人間なんだと考え出してくると、一切合切がグラグラして来て困ってしまう。つかみどころなき焦心、私の今朝の胃のふが、菜っぱ漬けだけのように、私の頭もスカスカとさみしい風が吹いている。極度の疲労困憊(こんぱい)は、さながら生きているミイラのようだ。古い新聞を十度も二十度も読みかえして、じっと畳に寝ころんでいる姿を、私はそっと遠くに離れて他人(ひと)ごとのように考えている。私の体はいびつ、私のこころもいびつなり。とりどころもない、燃えつくした肉体、私はもうどんなに食えなくなってもカフエーなんかに飛び込む事は止やめましょう。どこにも入れられない私の気持ちに、テラテラまがいものの艶ぶきをかけて笑いかける必要はないのだ。どこにも向きたくないのなら、まっすぐ向うを向いていて飢えればいいのだ。
夜。
利秋君が、富山の薬袋に米を一升持って来てくれる。この男には、何度も背負い投げを食わしたけれど、私はこんなアナキストは嫌いなのだ。「貴女が死ぬほど好きだ。」と言ってくれたところで、大和館でのように、朝も晩も朝も晩も遠くから私を監視している状態なんて、私の好かないところです。
「もう当分御飯を食べる事を休業しようかと思っていますのよ。」
私は固く扉を閉ざしてかぎをかけた。少しばかり腹を満たしたいために、不用な渦を吸いたくなかった。頭の頂天まで飢えて来ると鉄板のように体がパンパン鳴っているようで、すばらしい手紙が書きたくなってくる。だが、私はやっぱり食べたいのです。ああ私が生きてゆくには、カフエーの女給とか女中だなんて! 十本の指から血がほとばしって出そうなこの肌寒さ……さあカクメイでも何でも持って来い。ジャンダークなんて吹っ飛ばしてしまおう。だがとにかく、何もかもからっぽなのだ。階下の人達が風呂へ行ってる隙に味噌汁を盗んで飲む。神よ嗤(わら)い給え。あざけり給えかし。
あああさましや芙美子消えてしまえである。
働いていても、自分には爪の垢ほども食べるたしにはならないなんて、今までの生活(くらし)むきは、細く長くだった。ああ一円の金で私は五日も六日も食べていった事があった。死ぬる事なんていつも大切に取っておいたのだけれど、明日にも自殺しようかと考えると、私はありったけのぼろ屑(くず)を出して部屋にばらまいてやった。生きている間の私の体臭、なつかしやいとしや。疲れてドロドロに汚れた黒いメリンスの衿(えり)に、垢と白粉(おしろい)が光っている。私は子供のように自分の匂いをかぎました。この着物で、むかし、私はあのひとに抱かれたのです。あの思い! この思い! 蒼(あお)ざめて血の上って来る孤独の女よ、むねを抱いた両手の中には、着物や帯や半衿のあらゆる汚れから来る体臭のモンタージュなり。
私はこのすばらしいエクスタシイを前にして、誰に最後の嘲笑(ちょうしょう)さるべき手紙を書こうかと思った。Aにか、Bにか、Cにか……。シャックリの出る私の人生観を一寸匂わしてね。面白い興奮だと思う。「ね、こんなに、私は貴方を愛しているのに……」古新聞の上に散らかった広告の上には、一寸面白いサラダとビフテキのような名前がのっていた。三上於菟吉(おときち)なんて一寸エネルギッシュでビフテキみたいたが、これも面白い。吉田絃二郎(げんじろう)なんて、菜っぱと小鳥みたいなエトランゼ。私は二人へ同じ文章を書いてみようと思った。
海ぞいの黍畑(きびばたけ)に
何の願いぞも
固き葉の颯々(さっさつ)と吹き荒れて
二十五の女は
真実命を切りたき思いなり
真実死にたき思いなり
伸びあがり伸び上りたる
玉蜀黍(とうもろこし)は儚(はか)なや実が一ツ
ああこんな感傷を手紙の中にいれる事は止めましょう。イサベラ皇后様がコロンブスを見つけた興奮で、私のペン先はもうしどろもどろなのだ。ああソロモンの百合の花に、ドブドブと墨汁をなすりつけ給え!
(二月×日)
朝、冷たい霧雨が降っていた。晩あたりは雪になるかも知れない。久しく煙草も吸わない。この美しい寝ざめを、ああ石油の匂いのプンプンする新らしい新聞が読みたいものだと思う。
隣室のにぎやかな茶碗の音、我に遠きものあり。昨夜書いた二通の手紙、私は薄っすりとした笑いを心に感じると、何もかも、馬鹿くさい気がしてしまった。だけどまあ、人生なんてどっちを見ても薄情なものだ。真実めかして……ところで、問題は私の懐中に三銭の銅貨があることである。この三銭のお金にセンチメンタルを送ってもらうなんて事は、向う様に対してボウトクだけれど、十銭玉で七銭おつりを取るヨユウがあったら、私はこの二通の手紙を書かないで済んだかも知れないのだ――。日本綴りのボロボロになった「一茶句集」を出して読むなり。
きょうの日も棒ふり虫よ翌日(あす)も又
故郷は蠅(はえ)まで人をさしにけり
思うまじ見まじとすれど我家かな
一茶は徹底した虚無主義者だ。だけど、いま私は飢えているのです。この本がいくらにでも売れないかしら。――寝たっきりなので、体をもち上げるとポキポキ骨が鳴ってくる。指で輪をこしらえて、私の首を巻いてみると、おいたわしや私の動脈は別に油をさしてやらないのに、ドクドク澄んだ音で血が流れを登っている。尊しや。
二通の手紙。ドッチヲサキニダシマショウカ。何と他愛もない事なのだろう。吉田氏へ手紙を出す事にきめる。さて、音のしなくなった足をふみしめて街に出てみるなり。
湯島天神に行ってみた。お爺さんが車をぶんぶんまわして、桃色の綿菓子をつくっていた。あるかなきかの桃色の泡が真鍮(しんちゅう)の桶(おけ)の中から湧(わ)いて出てくると、これが霧のような綿菓子になる。長い事草花を見ない私の眼には、まるでもう牡丹(ぼたん)のように写ります。「おじいさん! 二銭頂戴。」子供の頭ぐらいの大きい綿菓子を私はそっと抱いた。誰もいない石のベンチでこれを食べよう。綿菓子を頬ばって、思うまじ見まじとすれど我家かな、漠然とこんな孤独を愛する事もいいではありませんか。
「おじいさん、三銭下さいな。」
あえなくも菜っぱと小鳥の感傷が、桃色の甘い綿菓子に変ってしまった。何と愛すべき感傷であろう。私の聯想(れんそう)は舌の上で涙っぽい砂糖に変ってしまった。しっかりと目をつぶって、切手をはらない吉田氏への手紙をポストに投げる。新潮社気付で送ったけれど、一笑されるかもしれない。三上氏への手紙は破る。とても華やかに暮している人に、こんな小さな現実なんて、消えてなくなるかも知れないもの――。身近にある人の事なんか妙にかすんでしまってくる。綿菓子のじいさんは、この寒空に雨が煙っているのに、何時までもガラガラと真鍮の車をまわしていた。ベンチに腰をかけて雨を灰のようにかぶって綿菓子をなめている女、その女の眼には遠い古里と、お母さんと男のことと、私のかんがえなんて、こんなくだらない郷愁しかないのだ!
(三月×日)
昼夜帯と本を二三冊売って二円十銭つくる。本屋さんが家までついて来て云う事には、「お家さえ判っておりませば、又頂きに上ります。」どういたしまして、私の押入れの中はマニア作家の頭のように、がらくたばかりですよ。
昼。
浅草へ行った。浅草はちっぽけな都会心から離れた楽土です。そんなことをどっかの屋根裏作家が云いました。浅草は下品で鼻もちがならぬとね。どのお方も一カ月せっせと豚のように食っているものだから、頭ばかり厖大(ぼうだい)になって、シネマとシャアローとエロチックか、顔を鏡にてらしあわせてとっくりとよくお考えの程を……ところで浅草のシャアローは帽子を振って言いました。「地上のあらゆるものを食いあきたから、こんどは、空を食うつもりです。」浅草はいい処ところだと思うなり。灯のつき始めた浅草の大提灯(おおぢょうちん)の下で、私の思った事は、この二円十銭で朗かな最後をつくしましょう。と云うことだ……何だか春めかしい宵なり、線香と女の匂いが薫じて来ます。雑沓(ざっとう)の流れ。――公園劇場の前に出てみると、水谷八重子の一座の旗の中に、別れたひとの青い旗が出ている。これは面白い。他人よりも上品にかぎの締ったあの男と私の間、すべてはお静かにお静かにと永遠に歳月が流れています。裏口からまわって、楽屋口の爺さんに尋ねてみるとつんけんした面がまえだった。廊下はいっぱい食物の皿小鉢で、お姫様も女学生も雑居のありさまなり。歪(ゆが)んだ硝子窓に立てかけた鏡が二ツ、何年か前の見覚えのある黒い鞄(かばん)が転がっていた。
「ヤア!」
楽屋へ坐っていると、下男風な丁髷(ちょんまげ)をのっけた男がはいって来た。
「随分御無沙汰しています。」
「お元気でしたか。」
浅草の真中の劇場の中で久し振りに、私は別れた男の声を聞いた。
「芝居でも見ていらっしゃい、一役すんだら私のは済むんだからお茶でも飲みましょう!」
「ええ、ありがとう、奥さんもいま一緒に何か演(や)っているんですか?」
「あああれ! 死にましたよ、肺炎で。」
あんなにも憎しみを持って別れた女優の顔が、遠くに浮んで、私はしばらくは信じられなかった。この男はとても真面目な顔をして嘘をついたから……。
「嘘でしょう。」
「貴女に嘘なんかついたって仕様がないもの、前々から体は弱かったのね。」
「本当ですか? 気の毒な……顔をつくって下さいな、私初めて貴方の楽屋を見たの。楽屋の中って随分淋しいもんね。」
男と話していると、背の高い若侍が、両刀をたばさんではいって来る。
「ああ紹介しましょう、この人は宮島資夫(すけお)君の弟さんでやっぱり宮島さんと云うひとです。」
このひとはきっちりと肉のしまった、青年らしい肩つきをしていた。――随分、この男も年をとったとも思えるし、鞄の中から詩稿なぞを出しているのを見ると、この人が役者である事が場違いのような気がして仕方がない。体だって肥っているし、それに年をとって、若い渋味のない声だし、こんな若い人達ばかりの間に混って芝居なんかしているのが、気の毒に思えて仕方がなかった。私はこの男と田端に家を持った時、初めて肩上げをおろしたのを覚えている。「僕の芝居を見て下さい、そして昔のように又悪口たたかれるかな。」私は名刺をもらうと楽屋口から外へ出た。今さらあの男の芝居を見たところでしようがないし、だが、大きな雨がひとしずく私の頬にかかってきたので、あわてて小屋へはいるなり。舞台はバテレン信徒を押し込めてある牢屋(ろうや)の場面で、八重子の華魁(おいらん)や、牢番や、侍が並んでいる。桜がランマンと舞台に咲いている。そして舞台には小鳥が鳴いていた。長い愚にもつかない芝居である。私は舞台を眺めながら色んな事を考えていた。「バテレンよゼウスよ!」あのひとは一寸声が大きすぎる。私は耳をふさいであの男の牢屋の中の話を聞いていた。八重子の美しい華魁が牢の外に出ると、観客は湧き立って拍手を送っていた。美しい姿ではあるけれども、何か影のない姿である。私は退屈して外へ出てしまった。あのひとは「お茶でも一緒に飲みましょう。」と言ったけれど、縁遠いものをいつまでも見ていなくてはならないなんて、渦は一切吸わぬ事だ――。薬屋をみつけては、小さいカルモチンの箱を一ツずつ買う。死ねないのならば、それでもいいし、少し長く眠れるなんて、幸福な逃げ道ではないか、すべては直線に朗かに。
(三月×日)
五色のテープがヒラヒラ舞っていた。
どこかで爆竹の弾ける音がすさまじく耳のそばでしている。飛行機かしら、モータボートかしら……私の錯覚から、白い泡を飛ばしている海の風景が空の上に見えてきました。銀色の燈台が限の底に胡麻粒(ごまつぶ)程に見えたかと思うと、こんどはまるで象の腹のようなものが眼の中じゅうに拡がって、私はずしんずしん地の底に体をゆりさげられているようだった。十子が私の裸の胸に手拭を当ててくれている。私はどうしても死にたくないと思った。眼をあけると、瞼(まぶた)に弾力がなくて、扇子をたたむようにくぼんで行く。私は死にたくない……。「若布(わかめ)とかまぼこのてんぷらと、お金が五円きていますよ。」私は瞼を締める事が出来なかった。耳の中へゴブゴブ熱い涙がはいって行く。枕元で、鋏(はさみ)をつかいながら十子が、母さんのところから送って来た小包をあけてくれた。お母さんが五円送ってくれるなんて、よっぽどの事だと思う。階下の叔母さんがかゆをたいて持って来てくれた。気持ちがよくなったら、この五円を階下へあげて、下谷の家を出ようと思う。
「洗濯屋の二階だけれどいいところよ、引越さない?」
私は生きていたい。死にそくないの私を、いたわってくれるのは男や友人なんかではなかった。この十子一人だけが、私の額をなでていてくれている。私は生きたい。そして、何でもいいから生きて働く事が本当の事だと思う――。



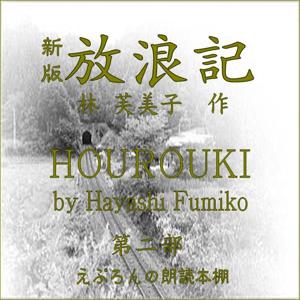

 View all episodes
View all episodes


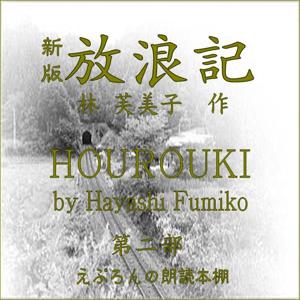 By えぷろん
By えぷろん