参照テキスト:青空文庫図書カード№1813
音声再生時間:24分19秒
このブラウザでは再生できません。
*
(七月×日)
ちっとも気がつかない内に、私は脚気(かっけ)になってしまっていて、それに胃腸も根こそぎ痛めてしまったので、食事もこの二日ばかり思うようになく、魚のように体が延びてしまった。薬も買えないし、少し悲惨な気がしてくる。店では夏枯れなので、景気づけに、赤や黄や紫の風船玉をそろえて、客を呼ぶのだそうである――。じっと売り場に腰を掛けていると、眠りが足らないのか、道の照りかえしがギラギラ目を射て頭が重い。レースだの、ボイルのハンカチだの、仏蘭西(フランス)製カーテンだの、ワイシャツ、カラー、店中はしゃぼんの泡のように白いものずくめである。薄いものずくめである。閑散な、お上品なこんな貿易店で、日給八十銭の私は売り子の人形だ。だが人形にしては汚なすぎるし、腹が減りすぎる。
「あんたのように、そう本ばかり読んでいても困るよ。お客様が見えたら、おあいそ位云って下さい。」
酸っぱいものを食べた後のように、歯がじんと浮いてきた。本を読んでいるんじゃないんです。こんな婦人雑誌なんか、私の髪の毛でもありはしない。硝子(ガラス)のピカピカ光っている鏡の面を一寸ちょっと覗(のぞ)いて御覧下さい。水色の事務服と浴衣が、バックと役者がピッタリしないように、何とまあおどけた厭な姿なのでしょう……。顔は女給風で、それも海近い田舎から出て来たあぶらのギラギラ浮いた顔、姿が女中風で、それも山国から来たコロコロした姿、そんな野生の女が、胸にレースを波たたせた水色の事務服を着ているのです。ドミエの漫画ですよこれは……。何とコッケイな、何とちぐはぐな牝鶏(めんどり)の姿なのでしょう。マダム・レースやミスター・ワイシャツや、マドモアゼル・ハンカチの衆愚に、こんな姿をさらすのが厭なのです。それに、サーヴィスが下手だとおっしゃる貴方の目が、いつ私をくびきるかも判らないし、なるべく、私と云う売り子に関心を持たれないように、私は下ばかりむいているのです。あまりに長いニンタイは、あまりに大きい疲れを植えて、私はめだたない人間にめだたない人間に訓練されていますのよ。あの男は、お前こそめだつ人間になって闘争しなくちゃ嘘だと云うのです。あの女は、貴女はいつまでもルンペンではいけないと云うのです。そして勇ましく戦っているべき、彼も彼女もいまはどこへ行っているのでしょう。彼や彼女達が、借りものの思想を食いものにして、強権者になる日の事を考えると、ああそんなことはいやだと思う。宇宙はどこが果てなんだろうと考えるし、人生の旅愁を感じる。歴史は常に新らしく、そこで燃えるマッチがうらやましくなった。
夜――九時。省線を降りると、道が暗いのでハーモニカを吹きながら家へ帰った。詩よりも小説よりも、こんな単純な音だけれど音楽はいいものです。
(七月×日)
青山の貿易店も、いまは高架線のかなたになった。二週間の労働賃銀十一円也、東京での生活線なんてよく切れたがるもんだ。隣のシンガーミシンの生徒?さんが、歯をきざむようにギイギイとひっきりなしにミシンのペタルを押している。毎日の生活断片をよくうったえる秋田の娘さんである。古里から十五円ずつ送金してもらって、あとはミシンでどうやら稼かせいでいる、縁遠そうな娘さんなり。いい人だ。彼女に紹介状をもらって、××女性新聞社に行く。本郷の追分で降りて、ブリキの塀(へい)をくねくね曲ると、緑のペンキの脱落した、おそろしく頭でっかちな三階建の下宿屋の軒に、螢(ほたる)程の小さい字で社名が出ていた。まるで心太(ところてん)を流すよりも安々と女記者になりすました私は、汚れた緑のペンキも最早何でもないと思った。
昼。
下宿の昼食をもらって舌つづみを打つと、女記者になって二三時間もたたない私は、鉛筆と原稿紙をもらって談話取りだ。四畳半に尨大(ぼうだい)な事務机が一ツ、薄色の眼鏡をかけた中年の社長と、××女性新聞発行人の社員が一人、私を入れて三人の××女性新聞。チャチなものなり。又、生活線が切れるんじゃないかと思ったけれど、とにかく私は街に出てみたのだ。訪問先は秋田雨雀(うじゃく)氏のところだった。この頃の御感想は……私はこの言葉を胸にくりかえしながら、雑司(ぞうし)ヶ谷(や)の墓地を抜けて、鬼子母神(きしぼじん)のそばで番地をさがした。本郷のごみごみした所からこの辺に来ると、何故なぜか落ちついた気がしてくる。一二年前の五月頃、漱石(そうせき)の墓にお参りした事もあった……。秋田氏は風邪を引いていると云って鼻をかみながら出ていらした。まるで少年のようにキラキラした眼、やさしそうな感じの人である。お嬢さんは千代子さんと云って、初めて行った私を十年のお友達のように話して下すった。厚いアルバムか出ると、一枚一枚繰って説明して下さる。この役者は誰、この女優は誰、その中に別れた男のプロマイドも張ってあった。
「女優ってどんなのが好きですか、日本では……」
「私判らないけど、夏川静江なんか好きだわ。」
私はいまだかつて私をこんなに優しく遇してくれた女の人を知らない。二階の秋田さんの部屋には黒い手の置物があった。高村光太郎さんの作で、有島武郎さんが持っていらっしたのだとかきいた。部屋は実に雑然と古本屋の観があった。談話取りが談話がとれなくて、油汗を流していると、秋田さんは二三枚すらすらと私のノートへ手を入れて下すった。お寿司を戴く。来客数人あり。暮れたのでおくって戴く。赤い月が墓地に出ていた。火のついた街では氷を削るような音がしている。
「僕は散歩が好きですよ。」
秋田氏は楽し気にコツコツ靴を鳴らしている。
「あそこがすずらんと云うカフエーですよ。」
舞台の様なカフエーがあった。変ったマダムだって誰かに聞いたことがある。秋田氏はそのまま銀座へ行かれた。
私は何か書きたい興奮で、沈黙だまって江戸川の方へ歩いて行った。
(七月×日)
階下の旦那さんが二日程国へ行って来ますと云って、二階の私達へ後の事を頼みに今朝上ってみえたのに、社から帰ってみると、隣のミシンの娘さんが、帯をときかけている私を襖(ふすま)の間から招いた。
「あのね一寸!」
低声なので、私もそっといざりよると、
「随分ひどいのよ、階下の奥さんてば外の男と酒を呑んでるのよ……」
「いいじゃないの、お客さんかも知れないじゃないですか。」
「だって、十八やそこいらの女が、あんなにデレデレして夫以外の男と酒を呑めるかしら……」
帯を巻いて、ガーゼの浴衣をたたんで、下へ顔洗いに行くと、腰障子の向うに、十八の花嫁さんは、平和そうに男と手をつなぎあって転がっていた。昔の恋人かも知れないと思う。只うらやましいだけで、ミシンの娘さんのような興味もない。夜は御飯を炊くのがめんどうだったので、町の八百屋で一山十銭のバナナを買って来てたべた。女一人は気楽だとおもうなり。糊(のり)の抜けた三畳づりの木綿の蚊帳の中に、伸び伸びと手足を投げ出してクープリンの「ヤーマ」を読む。したたか者の淫売婦が、自分の好きな男の大学生に、非常な清純な気持ちを見せる。尨大な本だ、頭がつかれる。
「一寸起きてますか?」
もう十時頃だろうか、隣のシンガーミシンさんが帰って来たらしい。
「ええまだねむれないでいます。」
「一寸! 大変よ!」
「どうしたんです。」
「呑気(のんき)ねッ、階下じゃ、あの男と一緒に蚊帳の中へはいって眠っててよ。」
シンガーミシン嬢は、まるで自分の恋人でも取られたように、眼をギロギロさせて、私の蚊帳にはいって来た。いつもミシンの唄に明け暮れしている平和な彼女が、私の部屋になんかめったにはいって来ない行儀のいい彼女が、断りもしないで私の蚊帳へそっともぐり込んで来るのだ。そして大きい息をついて、畳にじっと耳をつけている。
「随分人をなめているわね、旦那さんがかえって来たら皆云ってやるから、私よか十も下なくせに、ませてるわね……」
ガードを省線が、滝のような音をたてて走った。一度も縁づいた事のない彼女が、嫉妬がましい息づかいで、まるで夢遊病者のような変な狂態を演じようとしている。
「兄さんかも知れなくってよ。」
「兄さんだって、一ツ蚊帳には寝ないや。」
私は何だか淋しく、血のようなものが胸に込み上げて来た。
「眼が痛いから電気を消しますよ。」と云うと、彼女はフンゼンとして沈黙って出て行った。やがて梯子(はしご)段をトントン降りて行ったかと思うと、「私達は貴女を主人にたのまれたのですよ。こんな事知れていいのですかッ!」と云う声がきこえている。切れ切れに、言葉が耳にはいってくる。一度も結婚をしないと云う事は、何と云う怖(おそろ)しさだ。あんなにも強く云えるものかしら……。私は蒲団を顔へずり上げて固く瞼(まぶた)をとじた。何もかもいやいやだ。
(七月×日)
――ビョウキスグカエレタノム
母よりの電報。本当かも知れないが、また嘘かも知れないと思った。だけど嘘の云えるような母ではないもの……、出社前なので、急いで旅支度をして旅費を借りに社へ行く。社長に電報をみせて、五円の前借りを申し込むと、前借は絶対に駄目だと云う。だが私の働いた金は取ろうと思えば十五円位はある筈なのだ。不安になって来る。廊下に置いたバスケットが妙に厭になってきた。大事な時間を「借りる!」と云う事で、それも正当な権利を主張しているのに、駄目だと云われて悄気(しょげ)てしまう。これは、こんなところでみきわめをつけた方がいいかも知れない。
「じゃ借りません! その代り止めますから今までの報酬を戴きます。」
「自分で勝手に止されるのですから、社の方では、知りませんよ。満足に勤めて下すっての報酬であって、また十二三日しかならないじゃありませんか!」
黄色にやけたアケビのバスケットをさげて、私は又二階裏へかえって来た。ミシン嬢は、あれから階下の細君と気持ちが凍って、引っ越しをするつもりでいたらしかったが、帰って見ると、どこか部屋がみつかったらしく、荷物を運び出している処(ところ)だった。彼女の唯一の財産である、ミシンだけが、不恰好な姿で、荷車の上に乗っかっていた。全てはああ空(むな)しである――。
(七月×日)
駅には、山や海への旅行者が白い服装で涼し気だった。下の細君に五円借りた。尾道まで七円くらいであろう。やっと財布をはたいて切符を買うと、座席を取ってまず指を折ってみた。何度目の帰郷だろうと思う。
露草の茎
粗壁(かべ)に乱れる
万里の城
いまは何かしらうらぶれた感じが深い。昔つくった自分の詩の一章を思い出した。何もかも厭になってしまうけれど、さりとて、自分の世界は道いまだ遠しなのだ。この生ぐさきニヒリストは腹がなおると、じき腹がへるし、いい風景を見ると呆然としてしまうし、良い人間に出くわすと涙を感じるし、困った奴なり。バスケットから、新青年の古いのを出して読んだ。面白き笑話ひとつあり――。
―囚人曰いわく、「あの壁のはりつけの男は誰ですか?」
―宣教師答えて、「我等の父キリストなり。」
囚人が出獄して病院の小使いにやとわれると、壁に立派な写真が掛けてある。
―囚人、「あれは誰のです?」
―医師、「イエスの父なり。」
囚人、淫売婦を買って彼女の部屋に、立派な女の写真を見て――
―囚人、「あの女は誰だね。」
―淫売婦、「あれはマリヤさ、イエスの母さんよ。」
そこで囚人歎(たん)じて曰く、子供は監獄に父親は病院に、お母さんは淫売帰にああ――。私はクツクツ笑い出してしまった。のろい閑散な夜汽車に乗って退屈していると、こんなにユカイなコントがめっかった。眠る。
(七月×日)
久し振りで見る高松の風景も、暑くなると妙に気持ちが焦々(いらいら)してきて、私は気が小さくなってくる。どことなく老いて憔悴(しょうすい)している母が、第一番に言った言葉は、「待っとったけん! わしも気が小さくなってねえ……」そう云って涙ぐんでいた。今夜は海の祭で、おしょうろ流しの夜だ。夕方東の窓を指さして、母が私を呼んだ。
「可哀そうだのう、むごかのう……」
窓の向うの空に、朝鮮牛がキリキリぶらさがっている。鰯雲(いわしぐも)がむくむくしている波止場の上に、黒く突き揚った船の起重機、その起重機のさきには一匹の朝鮮牛が、四足をつっぱって、哀れに唸(うな)っている。
「あんなのを見ると、食べられんのう……」
雲の上にぶらさがっているあの牛は、二三日の内には屠殺(とさつ)されてしまって、紫の印を押されるはずだ。何を考えているのかしら……。船着場には古綿のような牛の群が唸っていた。
鰯雲がかたくりのように筋を引いてゆくと、牛の群も何時(いつか)去ってゆき、起重機も腕を降ろしてしまった。月の仄(ほのかな)海の上には、もう二ツ三ツおしょうろ船が流れていた。火を燃やしながら美しい紙船が、雁木(がんぎ)を離れて沖の方へ出ていた。港には古風な伝馬(てんま)船が密集している。そのあいだを火の紙船が月のように流れて行った。
「牛を食ったりおしょうろを流したり、人間も矛盾が多いんですねお母さん。」
「そら人間だもん……」
母は呆(ぼん)やりした顔でそんな事を云っている。



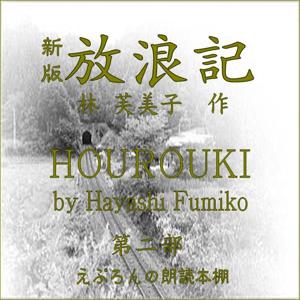

 View all episodes
View all episodes


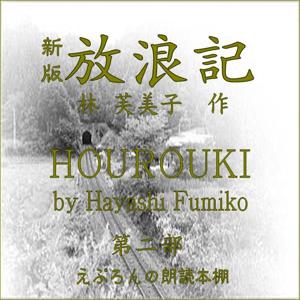 By えぷろん
By えぷろん