WebサービスやWebでのプロダクトを作るのが好きです
株式会社ゼンプロダクツの代表取締役です。
Shodo(shodo.ink)というWebサービスを作っています。AIで文章を校正したり、執筆の状態をワークフローで管理して記事のレビューができます。チームで執筆する人や、ライターさん、編集さん、コンテンツマーケティングをやる人に向けたプロダクトです。
DjangoCongress JPというイベントの代表もしています。
Twitterアカウントはhirokikyです。ぜひフォローしてください!



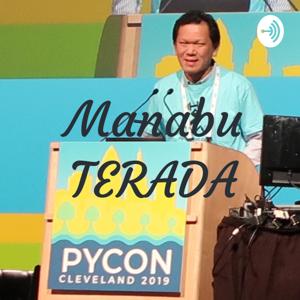

 View all episodes
View all episodes


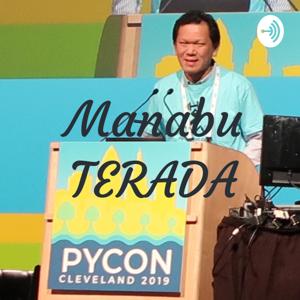 By Manabu TERADA
By Manabu TERADA

