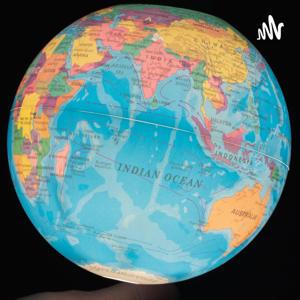前回、エンさんが「承認欲求の強弱によってその人の行動の大枠を説明できるのではないか(意訳です)」というお話をうけ、そのとおりかもなぁと思いました。
エンさんの想像通り、僕にはそんなに承認欲求が大きくないと思っています。その「承認欲求の大小」とはなんなのかなぁと、話をしています。
僕からの結論は、「遺伝子的な影響も恐らくはあるんだと思うんですが、それよりも文化だったり教育だったり、もしくはたまたまレベルの機会であったり、そういったことを含めた複合的な環境の方が、影響として大きい気がしています」です。
科学的に「性格は遺伝する」という話を以前聞いたことがありまして。
ここでいう『性格』ってのが、どのレベルのことをいうだろうかってのはありますよね。
「警戒心が強い」「好奇心が強い」ぐらいだったら、動物界で個体によってあったりするので、あるのかもしれませんね。
「遺伝子を通して遺伝する」ものには、髪質とか近眼リスクとか発がんリスクとか、そういったものについてはありそうですねと思えるのですが。(前者2つは生後や幼少期の時点で差が出やすいですし、発がんリスクもTrue/Falseで定量化して分析しやすいですよね。)
これまで僕が気にしてきた「その子がいつ自分が興味ある分野について意識を向けるか」とか「勉強の本質が分かってないのはなぜか」みたいなレベルについては、ほかの要因のほうが大きいだろうなぁと思っています。
もう少し言ってしまうと、個人を大きく構築するのは『環境』が大きいと、と。
中国に住む友人は、(むこうでは普通だから)列に割り込むことに疑問を持ちませんし、日本に来たらしませんし。
アメリカに移り住んだ子供が主体性が強くなったりするという話があったりとか。
遺伝子の遠い文化圏に移り住んで、人格が変わるというのもよくあると思います。
また別のアプローチから言うと、大多数のヒトは実親が育てていていますし、文化の影響が大きいので、そもそもが遺伝子と相関があるものが多いと思います。
定量化しづらい項目について、遺伝子の影響がないことの証明するには、本来「文化も人種も年齢も性別もバラバラな集団に対して質問をする」必要がありますが、そんなデータはごく少数でしょう。(まぁ、この差をどうこう証明する手法として統計があるのでしょうが。)
「君は歴代の徳川名将軍と遺伝子発現が似てるから、いい政治ができるかもしれない」なんて言われても意味ないじゃないっすか。将軍は世襲制だっつうの。
発がんリスクと遺伝の関係は、がん患者の血液検査がこれまであったから、名確に差をだすことができたんでしょうね。
はたしてはたして、これ以外の定性的なデータについて、どれだけ遺伝を紐付けることができるんでしょうかね。