
Sign up to save your podcasts
Or


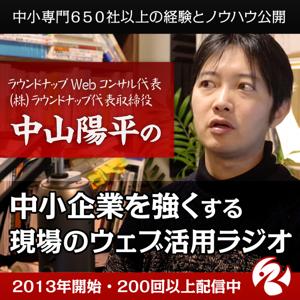

ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。
今回は「社内にいる既存の従業員のデジタルスキル・Webマーケティングスキルをどうやって上げていくか」というテーマでお話しします。特に、
そんな状況で悩んでいる方に向けて、「日常の中で自然にスキルアップしていくための考え方」と「現実的な取り組み方」を、私自身の現場での経験も交えながらお伝えしていきます。
社内のデジタルスキルを上げたいと思ったとき、多くの会社が最初に考えるのは次の二つです。
もちろん、これ自体は悪いことではありません。ただ、よく聞く悩みがあります。
つまり「スキルアップの機会を用意しているつもりなのに、それが身についていないように感じる」という状況です。
ここで一度整理しておきたいのは、単発の研修やセミナーだけで、人が大きく変わることはあまり多くないという前提です。これは講師の腕の問題というより、仕組みの問題に近いと考えています。
外部セミナーの会場を思い浮かべてみてください。きれいな会場に集まって、同じテーマに関心がある人が周りにたくさんいて、成功事例の話も聞ける。非日常の空間として、刺激のある場になりやすいですよね。
その場では「なるほど、自社でもやってみたい」と思うのですが、会社に戻る途中でふと冷静になります。
この段階で、多くの方の行動は次の二つに分かれます。
結果として、セミナーをきっかけに「継続的な行動」が生まれないまま時間が過ぎていくことが多いのです。これは社内研修でも同じで、外部の人が来ることでその場の空気は変わりますが、それだけで日常の行動が変わるかというと、難しい面があります。
私も企業研修を行いますが、必ずセットにしているのが研修後のフォローアップ期間です。たとえば、4日間の研修を行ったら、その後1か月は
など、その会社で使っているグループウェアやチャットツール上で質問を受け付けるようにしています。
実際にやってみると、フォローアップ期間に飛んでくる質問は、研修のスライドに直接は出てこないようなものも多いです。むしろ、そうした具体的な質問へのやりとりのほうが、最終的には役に立ったと言われることが多いくらいです。
この経験からも、「1回の研修で人を変える」という期待をいったん手放すことが重要だと考えています。では、代わりにどこに期待すべきか。それが次のテーマです。
「毎週のように研修をする」「高額な講師を定期的に呼ぶ」というのは、正直なところ、多くの中小企業では現実的ではありません。そこで視点を変えて、
日常の中にある「当たり前の行動」そのものを、学びの場として活用する
という考え方で設計してみてはどうでしょうか。
たとえば、皆さんは普段、自分が何かを買うときやサービスを選ぶとき、どれくらいの頻度でウェブ上の情報を見ているでしょうか。まったく見ないという人は、かなり少ないのではないかと思います。
その「自分がお客様になっている時間」は、自社の顧客の気持ちを理解するうえで、とても大きなヒントの宝庫です。売り手としての時間より、お客様として情報を見ている時間のほうがずっと長い、という方も多いはずです。
であれば、そこから積極的に学んでしまおうという発想です。
おすすめしているのは、何かをウェブで探したり比較したりするときに、次のようなことを意識してメモしてみることです。
特に後者の「選ばなかった理由」が重要です。選んだ理由は、意外と感覚的だったり、うまく言葉にできなかったりすることが多いのですが、
「やめた理由」「避けた理由」は、比較的論理的に説明できることが多いのです。
こういった「マイナスの理由」は、人間の性質として見つけやすい面があります。そこをあえて意識して言葉にしていくと、お客様がどこで離脱するのか、どこに不安を感じるのかが、自分の体験を通じて見えてきます。
最初は少し手間に感じられるかもしれませんが、
といった情報を、簡単なメモや社内の共有ノートにためていくだけでも、かなり視点が変わってきます。
これを続けることで、
といった「読んでいる側の感覚」が、自分の中で整理されていきます。すると、いざ自社のウェブサイトや広告を考えるときに、お客様目線でチェックする力が自然と身についてきます。
とはいえ、頭の中で思うだけだと、どうしてもあいまいなままになりがちです。そこで大切になってくるのが、
といったアウトプットの場です。
知識や気づきを
というプロセスを通さないと、頭の中でうまく整理されません。結果として、
が「なんとなく分かった気がする」状態のまま、ゆっくり記憶から薄れていきます。
よく「研修をしても、すぐ忘れてしまう」と言われますが、正確には
そもそも自分の中で整理できるところまで吸収しきれていない
ことが多いのです。特に、成功事例だけを紹介するような研修は要注意です。
成功事例の話は、限られた時間の中で要点だけが紹介されることが多く、どうしても省略されている部分がたくさんあります。
たとえば、1時間の成功事例セミナーがあるとします。その裏側には、
など、話せば3〜4時間はかかるような「隙間」があります。ただ「そこまで話すと長くなりすぎる」「そこはあまり面白く聞こえない」という理由で、省略されていることが多いのです。
本当に力がつくのは、
を、自社の状況にあてはめて考え直していくプロセスです。その過程で生まれた疑問を言語化し、誰かとやりとりすることで、知識が自分のものになっていきます。
少し違う業界の例ですが、あるアナウンサーの方の話がとても印象に残っています。その方が「どうやって実況がうまくなったのか」と聞かれたとき、こう答えていました。
日常のあらゆる場面で、頭の中で自然と実況するようにしていた。
この話は、ウェブマーケティングのスキルアップにもそのまま応用できます。
頭の中で
といった実況を自然にしてしまう状態を目指します。
こうした目線が身についてくると、
ようになっていきます。「専門家になる」というと大がかりに聞こえますが、日常の中で当たり前にやることを、少し意識して言語化する習慣があるだけで、スキルアップのスピードはかなり変わります。
ここまで、「日常の中で学ぶ」「自分たちの購買行動から学ぶ」という話をしてきました。ただ、もう一つ大事なポイントがあります。
それは、社内だけで考えていると、ときどき変な方向にまとまってしまうことがあるという点です。
全員が真面目に考えていても、視点がどうしても似通ってしまい、「なんとなく皆がそう言っているから」という空気で決まってしまうことがあります。そんなときに役に立つのが、外部のセカンドオピニオンです。
私のところにも、定期的に
といった相談が届きます。
こちらからは、
といった形でコメントを返しますが、それをそのまま鵜呑みにしてほしいとは思っていません。むしろ、
を材料にしながら、自社なりの折衷案をつくっていく会社ほど、結果として強くなると感じています。
外部の専門家とやりとりをしていると、次のような流れになることが多いです。
例えば、
といった点は、専門的なサポートがあったほうがスムーズです。一方で、
といった部分は、どうしても社内でしか決められません。その役割分担をはっきりさせながら進めていくと、実行フェーズも動かしやすくなります。
こうした「日常的な壁打ち」の場を持つために、必ずしも高額な定期研修を契約する必要はありません。私のところでも、いちばん負担の少ないライトなプランであれば、10万円未満の費用感で相談いただけるようにしています。
その範囲でも、
といったことは十分に可能です。そして、そのやりとりを社内の簡単な勉強会や研修に発展させていくと、お金を大きくかけずに、日常の延長線上でスキルアップの仕組みが作れます。
ここまでの話を、実際のステップとして整理してみます。
に、簡単でかまわないので次のような項目をメモします。
ここで大事なのは、正解を出そうとするのではなく、視点を増やすことです。
このサイクルを回していくことで、「研修を受けるとき」だけでなく、普段の仕事そのものが学びの場になっていきます。
こうすることで、
といった効果が期待できます。
「デジタルスキルやWebマーケティングのスキルを上げる機会がなかなか作れない」と感じているとき、
ばかりが「機会」だと思いがちです。
しかし実際には、
もすべて、スキルアップの機会になります。
単発の研修は、そのきっかけを作る上では意味があります。ただ、大事なのはその後、どれだけ日常の中で考え続けられる場を作れるかです。
もし、今回の話の中で「うちの場合はこういう状況だけど、どう考えれば良いのか知りたい」といった具体的な疑問があれば、ぜひ遠慮なく相談してください。現場での経験も踏まえながら、一緒に次の一歩を考えていければと思います。
こちらのフォームへどうぞ。 https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/
投稿 第535回:継続的な成長を促す、中小企業のためのWebマーケティング人材育成、次の一手 は 中小企業専門WEBマーケティング支援会社・ラウンドナップWebコンサルティング(Roundup Inc.) に最初に表示されました。
 View all episodes
View all episodes


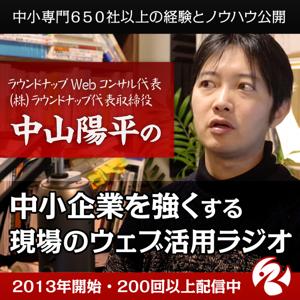 By ラウンドナップ・Webコンサルティング 代表 中山陽平
By ラウンドナップ・Webコンサルティング 代表 中山陽平
ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。
今回は「社内にいる既存の従業員のデジタルスキル・Webマーケティングスキルをどうやって上げていくか」というテーマでお話しします。特に、
そんな状況で悩んでいる方に向けて、「日常の中で自然にスキルアップしていくための考え方」と「現実的な取り組み方」を、私自身の現場での経験も交えながらお伝えしていきます。
社内のデジタルスキルを上げたいと思ったとき、多くの会社が最初に考えるのは次の二つです。
もちろん、これ自体は悪いことではありません。ただ、よく聞く悩みがあります。
つまり「スキルアップの機会を用意しているつもりなのに、それが身についていないように感じる」という状況です。
ここで一度整理しておきたいのは、単発の研修やセミナーだけで、人が大きく変わることはあまり多くないという前提です。これは講師の腕の問題というより、仕組みの問題に近いと考えています。
外部セミナーの会場を思い浮かべてみてください。きれいな会場に集まって、同じテーマに関心がある人が周りにたくさんいて、成功事例の話も聞ける。非日常の空間として、刺激のある場になりやすいですよね。
その場では「なるほど、自社でもやってみたい」と思うのですが、会社に戻る途中でふと冷静になります。
この段階で、多くの方の行動は次の二つに分かれます。
結果として、セミナーをきっかけに「継続的な行動」が生まれないまま時間が過ぎていくことが多いのです。これは社内研修でも同じで、外部の人が来ることでその場の空気は変わりますが、それだけで日常の行動が変わるかというと、難しい面があります。
私も企業研修を行いますが、必ずセットにしているのが研修後のフォローアップ期間です。たとえば、4日間の研修を行ったら、その後1か月は
など、その会社で使っているグループウェアやチャットツール上で質問を受け付けるようにしています。
実際にやってみると、フォローアップ期間に飛んでくる質問は、研修のスライドに直接は出てこないようなものも多いです。むしろ、そうした具体的な質問へのやりとりのほうが、最終的には役に立ったと言われることが多いくらいです。
この経験からも、「1回の研修で人を変える」という期待をいったん手放すことが重要だと考えています。では、代わりにどこに期待すべきか。それが次のテーマです。
「毎週のように研修をする」「高額な講師を定期的に呼ぶ」というのは、正直なところ、多くの中小企業では現実的ではありません。そこで視点を変えて、
日常の中にある「当たり前の行動」そのものを、学びの場として活用する
という考え方で設計してみてはどうでしょうか。
たとえば、皆さんは普段、自分が何かを買うときやサービスを選ぶとき、どれくらいの頻度でウェブ上の情報を見ているでしょうか。まったく見ないという人は、かなり少ないのではないかと思います。
その「自分がお客様になっている時間」は、自社の顧客の気持ちを理解するうえで、とても大きなヒントの宝庫です。売り手としての時間より、お客様として情報を見ている時間のほうがずっと長い、という方も多いはずです。
であれば、そこから積極的に学んでしまおうという発想です。
おすすめしているのは、何かをウェブで探したり比較したりするときに、次のようなことを意識してメモしてみることです。
特に後者の「選ばなかった理由」が重要です。選んだ理由は、意外と感覚的だったり、うまく言葉にできなかったりすることが多いのですが、
「やめた理由」「避けた理由」は、比較的論理的に説明できることが多いのです。
こういった「マイナスの理由」は、人間の性質として見つけやすい面があります。そこをあえて意識して言葉にしていくと、お客様がどこで離脱するのか、どこに不安を感じるのかが、自分の体験を通じて見えてきます。
最初は少し手間に感じられるかもしれませんが、
といった情報を、簡単なメモや社内の共有ノートにためていくだけでも、かなり視点が変わってきます。
これを続けることで、
といった「読んでいる側の感覚」が、自分の中で整理されていきます。すると、いざ自社のウェブサイトや広告を考えるときに、お客様目線でチェックする力が自然と身についてきます。
とはいえ、頭の中で思うだけだと、どうしてもあいまいなままになりがちです。そこで大切になってくるのが、
といったアウトプットの場です。
知識や気づきを
というプロセスを通さないと、頭の中でうまく整理されません。結果として、
が「なんとなく分かった気がする」状態のまま、ゆっくり記憶から薄れていきます。
よく「研修をしても、すぐ忘れてしまう」と言われますが、正確には
そもそも自分の中で整理できるところまで吸収しきれていない
ことが多いのです。特に、成功事例だけを紹介するような研修は要注意です。
成功事例の話は、限られた時間の中で要点だけが紹介されることが多く、どうしても省略されている部分がたくさんあります。
たとえば、1時間の成功事例セミナーがあるとします。その裏側には、
など、話せば3〜4時間はかかるような「隙間」があります。ただ「そこまで話すと長くなりすぎる」「そこはあまり面白く聞こえない」という理由で、省略されていることが多いのです。
本当に力がつくのは、
を、自社の状況にあてはめて考え直していくプロセスです。その過程で生まれた疑問を言語化し、誰かとやりとりすることで、知識が自分のものになっていきます。
少し違う業界の例ですが、あるアナウンサーの方の話がとても印象に残っています。その方が「どうやって実況がうまくなったのか」と聞かれたとき、こう答えていました。
日常のあらゆる場面で、頭の中で自然と実況するようにしていた。
この話は、ウェブマーケティングのスキルアップにもそのまま応用できます。
頭の中で
といった実況を自然にしてしまう状態を目指します。
こうした目線が身についてくると、
ようになっていきます。「専門家になる」というと大がかりに聞こえますが、日常の中で当たり前にやることを、少し意識して言語化する習慣があるだけで、スキルアップのスピードはかなり変わります。
ここまで、「日常の中で学ぶ」「自分たちの購買行動から学ぶ」という話をしてきました。ただ、もう一つ大事なポイントがあります。
それは、社内だけで考えていると、ときどき変な方向にまとまってしまうことがあるという点です。
全員が真面目に考えていても、視点がどうしても似通ってしまい、「なんとなく皆がそう言っているから」という空気で決まってしまうことがあります。そんなときに役に立つのが、外部のセカンドオピニオンです。
私のところにも、定期的に
といった相談が届きます。
こちらからは、
といった形でコメントを返しますが、それをそのまま鵜呑みにしてほしいとは思っていません。むしろ、
を材料にしながら、自社なりの折衷案をつくっていく会社ほど、結果として強くなると感じています。
外部の専門家とやりとりをしていると、次のような流れになることが多いです。
例えば、
といった点は、専門的なサポートがあったほうがスムーズです。一方で、
といった部分は、どうしても社内でしか決められません。その役割分担をはっきりさせながら進めていくと、実行フェーズも動かしやすくなります。
こうした「日常的な壁打ち」の場を持つために、必ずしも高額な定期研修を契約する必要はありません。私のところでも、いちばん負担の少ないライトなプランであれば、10万円未満の費用感で相談いただけるようにしています。
その範囲でも、
といったことは十分に可能です。そして、そのやりとりを社内の簡単な勉強会や研修に発展させていくと、お金を大きくかけずに、日常の延長線上でスキルアップの仕組みが作れます。
ここまでの話を、実際のステップとして整理してみます。
に、簡単でかまわないので次のような項目をメモします。
ここで大事なのは、正解を出そうとするのではなく、視点を増やすことです。
このサイクルを回していくことで、「研修を受けるとき」だけでなく、普段の仕事そのものが学びの場になっていきます。
こうすることで、
といった効果が期待できます。
「デジタルスキルやWebマーケティングのスキルを上げる機会がなかなか作れない」と感じているとき、
ばかりが「機会」だと思いがちです。
しかし実際には、
もすべて、スキルアップの機会になります。
単発の研修は、そのきっかけを作る上では意味があります。ただ、大事なのはその後、どれだけ日常の中で考え続けられる場を作れるかです。
もし、今回の話の中で「うちの場合はこういう状況だけど、どう考えれば良いのか知りたい」といった具体的な疑問があれば、ぜひ遠慮なく相談してください。現場での経験も踏まえながら、一緒に次の一歩を考えていければと思います。
こちらのフォームへどうぞ。 https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/
投稿 第535回:継続的な成長を促す、中小企業のためのWebマーケティング人材育成、次の一手 は 中小企業専門WEBマーケティング支援会社・ラウンドナップWebコンサルティング(Roundup Inc.) に最初に表示されました。
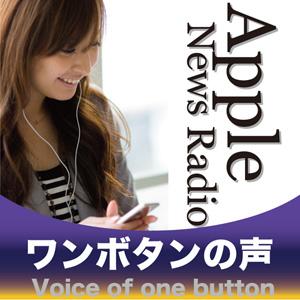
9 Listeners

15 Listeners
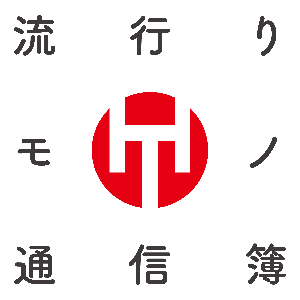
3 Listeners

231 Listeners

3 Listeners

13 Listeners

21 Listeners

42 Listeners

0 Listeners

21 Listeners

5 Listeners

3 Listeners

2 Listeners

2 Listeners

0 Listeners