
Sign up to save your podcasts
Or


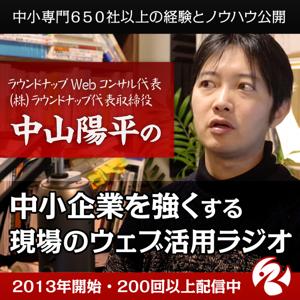

ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。
今回は、Webサイトのコンテンツ運用に関するお悩みの中でも、特に「定期更新」のプレッシャーについてお話しします。「継続的にコンテンツを作らなければ」と考えるあまり、その品質が犠牲になっていませんか?
多くの方が、Webサイトにはブログのような定期更新コンテンツが必要だと考えていらっしゃいますが、その「定期更新」が目的になってしまい、中身のない「こたつ記事」を生み出す結果になってはいないでしょうか。
今の時代において、その継続更新が本当に必要なのか。もし必要だとしたら、何に気をつけるべきか。あるいは、今まさに取り組んでいる方は、何を確認すべきか。そうした「そもそも論」について掘り下げていきたいと思います。
いつからか、「Webサイトは定期的に更新しなければならない」という考えが定着しました。いわゆる「社長ブログ」が流行りだした頃、ホームページの更新が昔に比べて簡単になった時期と重なります。HTMLやCSSといった専門知識がなくても、ブログシステムを使って自分たちでページを追加できる時代が来たのです。
それがいつ頃かというと、Web 2.0という言葉が使われだした頃、今から十数年以上前のことだと思います。
そこからさらに、SEO(検索エンジン最適化)の観点で「様々なトピックスを網羅した方が良い」という時代が来ました。その結果、自分たちが狙うキーワードに関連する情報を網羅するために、ブログやコラム、基礎知識といった名前でコンテンツを定期的に入れなければならない、という流れができてしまったように感じます。
これはお客様側の懸念でもありますが、同時に制作する側がそのように提案するケースも多いため、今もなお、この「定期更新のプレッシャー」が続いているのではないでしょうか。
では結論として、こうした継続的なコンテンツの追加が本当に今も必要なのかというと、必ずしもそうではないというのが私の実感です。
ここで、考え方を変えていただきたいのです。「定期的にコンテンツを出さなければならない」という言葉自体が、少し方向性を間違わせている可能性があります。
皆さんが本当に目指すべきは、お客様が知りたいことや、時代に合わせて新しく現れたトピックスに対して、必要十分な情報提供をできるようにすることです。
多くの競合他社がいる中で、お客様がどこを選ぶか。その時、お客様がまず考えるのは「プラス要素」よりも「マイナス要素がないか」、つまり不安やリスクがないかです。
その際に、自分が知りたい情報がWebサイトに載っていない、というのがお客様にとって一番嫌な状況です。そして、「今、何を知りたいか」は時代によって変わりますし、業界によってはタイムリーなネタもあるでしょう。
そうした情報を迅速に出せる体制にしておくことが大事なのであって、「定期的に出すこと」自体が目的なのではない、ということをまず押さえてください。
今でも「サジェストキーワードローラー作戦」のように、メインキーワードに関連する(検索ボリュームの少ない)キーワードで、安価な記事を外部に大量発注しているケースがあるかもしれません。
しかし、私たちがアクセス解析などを見ていても、これはほとんど意味がないケースが本当に多いのです。
外部に記事作成を委託している場合、失礼ながら、その成果をしっかり見ていないことが多いのではないでしょうか。
そのコンテンツがどれだけアクセスを生んでいるか。たとえアクセスがあったとして、その先にある皆さんのサービスページなど、ビジネスに近いコンテンツにお客様を誘導できているかを見ていますか。
もしコンテンツが本当に意味を持ち、適切に設計されていれば、訪問者は次にその会社自体や他のサービスに興味を持つはずです。そこから、より成果に近いコンテンツへ誘導される流れができているはずです。
そうなれば、直帰率は低く、エンゲージメント率は高く、結果的に滞在時間も長くなるでしょう。さらに、アクセス数を見ても、コラム記事だけが伸びているのではなく、サービスページなどビジネスに近いページのアクセスも相関して上がっているはずです。
まずは、今やっている定期更新コンテンツがどれくらいアクセスを生んでいるか。そして、その伸び(コンテンツは蓄積されていくので基本的には伸びるはずです)に伴って、他の重要なページのアクセスも伸びているか、ページ遷移は起きているか。例えば、Google Analytics 4 (GA4) の「経路データ探索」機能や、Microsoft Clarity (マイクロソフト クラリティ) のようなヒートマップツールでクリックの動向を分析し、成果に近いページへ移動しているかを確認してみてください。
なぜ成果が出ないのか。安価な「サジェストローラー」のような形で発注される記事は、単価が安い分、その辺にある情報を検索してまとめた、いわゆる「こたつ記事」になりがちです。
しかし、今はどの企業も同じようなことをやっていますし、中にはもっと手間とコストをかけてしっかりやっている企業もたくさんあります。そうしたコンテンツに勝てるわけがありません。
ページ数だけが増え、サイトが成長しているかのように見えても、実はビジネスには全く貢献していない。そういうケースが本当に多いのです。
もし現状がそれに近いのであれば、思い切ってその予算の使い道を変えるべきです。
例えば、その予算を使って、もっと専門性のあるライターに既存記事の改善を依頼する方がよほど有益です。
お客様目線で見たときに、「こういうトピックスも加えた方が良い」という内容の追加かもしれませんし、「文字ばかりだから図版や箇条書きを入れて見せ方を変えた方が良い」というアドバイスかもしれません。
新しく10記事を書く予算があるなら、その3倍のコストをかけてでも、3記事のメンテナンスにお金をかけた方が絶対に良いと私は思います。
もちろん、新規記事が有効な場合もあります。特に今は、Googleの評価基準であるE-E-A-T(従来のE-A-TにExperience=経験が加わったもの)が重視されています。
AIが過去の情報を再利用してコンテンツを生成していく中で、Googleは新しい情報、つまり「経験」を重要視していると公言しています。
そして、皆さんの頭の中にあって、まだ世の中のWeb上にはない情報は、たくさんあるはずです。
世の中の情報は語り尽くされたように思われがちですが、そんなことはありません。私自身、仕事柄、非常に多くのWebサイトや情報源に触れています。これまで600社、700社といったお客様とお付き合いし、並行して20〜30社の案件を見ているため、インプット量はかなり多い方だと自負しています。
それでも、お客様のところへ伺って話を聞くと、知らなかったことばかりです。
それはどうでもいい話ではなく、商売の根幹に関わる内容で、「ああ、ここはこういう違いがあるんだ」と驚くことばかりです。だからこそ、ビデオ会議は移動時間がなく効率的ですが、やはりお客様の元へ「行く」ということ自体には、ものすごい価値があるなと感じます。
話が少し逸れましたが、私が驚くくらいですから、皆さんの中には「まだ出していない価値ある情報」が確実に眠っているのです。
例えば、営業現場でお客様と話していて、「こういう話は食いつきが良いな」と感じるネタがあると思います。一方で、それを検索キーワードとして調べると、検索ボリューム(検索される回数)は全然ない、ということも多いでしょう。
ですが、昔からそうですが、結局そういうコンテンツがお客様に響くのです。
確かに、集客の初期段階(フロント)、つまり検索エンジンからの流入数(セッション数)を上げるという観点で作るコンテンツは、お客様が知っている言葉、つまり顕在的なキーワードで検索されるため、ある程度の検索ボリュームを意識して作る必要があります。
しかし、その先、サイト内を回遊してもらい、見込み客を育成する(ナーチャリング)段階では、お客様がすでに知っているキーワードにこだわる必要は全くありません。
むしろ、「そういうこともあるんだ」という、先ほど私が申し上げたような「驚き」や「発見」こそが、数ある選択肢の中から皆さんを選んでもらうための強い理由付けになっていきます。
ですから、検索エンジンからの流入数を上げるためのコンテンツは、ある程度キーワードを意識して作る必要がありますが、それ以外の多くのコンテンツは、SEOを過度に気にせず、皆さんが「お客様に響く」と考える内容を中心に作っていくのが良いと思います。
それは決して「週に1回」や「毎日」出さなければいけないものではありません。圧倒的に質が大事です。
質を犠牲にして量を出すことに、今の時代、意味はほぼありません。それが意味を持ったのは、Googleのアルゴリズムが未熟で、かつ世の中にコンテンツが少なかった、本当に昔の時代だけです。その頃の名残を引きずったまま商売をしていると、現状を見誤ってしまいます。
無駄なことにお金を使うくらいなら、やることを3分の1に減らして、その3倍のコストで良いものを作り上げていくべきです。
理想を言えば、その「質」を担保できるのは、皆さん自身です。自分たちの商売に関する情報発信やお客様への説明を、自分たちがやらない、というのは本来おかしな話です。
Webサイトのコンテンツは、それがブログであれ固定ページであれ、皆さん自身がお客様に対して話しかけているのと同じです。そうであるならば、その中身を外部に丸投げしなければならない、という状態はやはり健全ではありません。
今回のテーマである「定期的なコンテンツ更新が難しい」という悩みへの回答をまとめます。
まず、定期的に出す必要はありません。
ただし、本来の目的を間違えないでください。目的は、時代に合わせて出てくる新しい疑問や、Webサイト上でまだ答えられていないお客様の不安を、できるだけ早く解消できるようにコンテンツを整備することです。そのタスクが膨大にあるから、結果的に「定期更新」のように見えるだけです。
その上で、「量より質」で取り組んでください。
そして「質」に関して言えば、ちゃんと商売をしてきた方ほど、皆さんの中に「お客様が知らない、知ったら驚くようなこと」がたくさんあります。私がお客様の話を聞いて驚くのですから、一般の方はもっと驚くはずです。
Webを気にせずコツコツとお客様に向き合ってきた会社こそ、強いコンテンツを持っています。ご自身を信じて、それをどうコンテンツ化するか(記事か、動画か、スライドか)を考えてみてください。
今、外部パートナーにコンテンツ作成を依頼している方は、アクセス数や直帰率、エンゲージメント率をチェックし、「これに意味があるのか」と疑問を持ってみてください。
信頼できるパートナーであれば、「こういう状況だから意味があります」と、必ず数値をもとに説明できるはずです。
それは「このキーワードで何位になりました」という話ではありません。ニッチなキーワードであれば1位を取ることは難しくないからです。そうではなく、「そこからビジネスにこれだけ繋がっています」という説明ができるかどうかです。
もしその説明が曖昧なら、依頼をやめるか、弊社でも他の会社でも構いませんので、セカンドオピニオンを取ってみることをお勧めします。
お客様は、皆さんが思っているほど「毎日更新しているか」なんて気にしていません。もちろん、ブログが1年も更新されていなければ少し不安になるかもしれませんが、基本的には見ていません。
皆さんも、他の業種で何かを探すとき、「この会社は豆知識を定期的に更新してるな」なんてことを気にして選びますか。おそらく、していないのではないでしょうか。だとすれば、皆さんのお客様も同じです。先入観は捨てた方が良いでしょう。
やるからには、濃いコンテンツを作っていくべきです。ちゃんとした濃いコンテンツを作ると、本当にお客様の動きが変わってきます。
そして、それを会社のコンセプトとセットで設計することで、会社に対しての見え方、例えば「ただの下請け会社」なのか、「このトピックスに関して強い専門家集団」なのか、「雑な仕事をするところ」なのか、「きっちり仕事をするところ」なのか、そういった印象もコンテンツによって大きく変わってきます。
ぜひ、もう少し上の視点からコンテンツ戦略を考えていただけると良いのではないかと思います。
(ここからは中山の余談となりますが)
ただ、それは「時代が変わって新しいトピックスが出てきた時に、書ける場所(受け皿)があった方が良い」という観点や、「制作事例」のようにフォーマットを揃えて現場で更新しやすくするためにシステムを導入する、といった理由が主です。必ずビジネス全体を前提においてご提案していますし、中の皆さんが更新し続けられるようにレクチャーも行っています。
コンテンツは本当に難しいですね。量を出したところで読まれませんし、かといって動画を作っても、しっかり考えて作らなければ見られません。これだけ情報が溢れていれば仕方ない流れですが、「何でも作れば良い」というわけではないことを痛感します。
私自身、自社のコンテンツは放置気味で、お客様のことで手一杯になっており、反省点ではあります(ですので、あまり弊社のサイトは参考にしないでください)。
今回の内容は以上になります。
もし何かお困りのことやお悩みのことがあれば、ラウンドナップWebコンサルティングでは、中小企業、小規模事業者、個人事業主の方からのご相談も承っております。すべて代表取締役である私、中山が対応いたしますので、お気軽に問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。
よろしければ、高評価やレビューなどをいただけますと嬉しいです。ご質問もいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。
こちらのフォームへどうぞ。
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/
投稿 第540回:そのブログ記事、無駄になっていませんか?SEO目的コンテンツの有用性とは は 中小企業専門WEBマーケティング支援会社・ラウンドナップWebコンサルティング(Roundup Inc.) に最初に表示されました。
 View all episodes
View all episodes


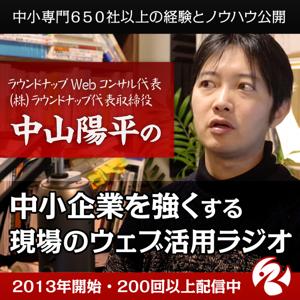 By ラウンドナップ・Webコンサルティング 代表 中山陽平
By ラウンドナップ・Webコンサルティング 代表 中山陽平
ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。
今回は、Webサイトのコンテンツ運用に関するお悩みの中でも、特に「定期更新」のプレッシャーについてお話しします。「継続的にコンテンツを作らなければ」と考えるあまり、その品質が犠牲になっていませんか?
多くの方が、Webサイトにはブログのような定期更新コンテンツが必要だと考えていらっしゃいますが、その「定期更新」が目的になってしまい、中身のない「こたつ記事」を生み出す結果になってはいないでしょうか。
今の時代において、その継続更新が本当に必要なのか。もし必要だとしたら、何に気をつけるべきか。あるいは、今まさに取り組んでいる方は、何を確認すべきか。そうした「そもそも論」について掘り下げていきたいと思います。
いつからか、「Webサイトは定期的に更新しなければならない」という考えが定着しました。いわゆる「社長ブログ」が流行りだした頃、ホームページの更新が昔に比べて簡単になった時期と重なります。HTMLやCSSといった専門知識がなくても、ブログシステムを使って自分たちでページを追加できる時代が来たのです。
それがいつ頃かというと、Web 2.0という言葉が使われだした頃、今から十数年以上前のことだと思います。
そこからさらに、SEO(検索エンジン最適化)の観点で「様々なトピックスを網羅した方が良い」という時代が来ました。その結果、自分たちが狙うキーワードに関連する情報を網羅するために、ブログやコラム、基礎知識といった名前でコンテンツを定期的に入れなければならない、という流れができてしまったように感じます。
これはお客様側の懸念でもありますが、同時に制作する側がそのように提案するケースも多いため、今もなお、この「定期更新のプレッシャー」が続いているのではないでしょうか。
では結論として、こうした継続的なコンテンツの追加が本当に今も必要なのかというと、必ずしもそうではないというのが私の実感です。
ここで、考え方を変えていただきたいのです。「定期的にコンテンツを出さなければならない」という言葉自体が、少し方向性を間違わせている可能性があります。
皆さんが本当に目指すべきは、お客様が知りたいことや、時代に合わせて新しく現れたトピックスに対して、必要十分な情報提供をできるようにすることです。
多くの競合他社がいる中で、お客様がどこを選ぶか。その時、お客様がまず考えるのは「プラス要素」よりも「マイナス要素がないか」、つまり不安やリスクがないかです。
その際に、自分が知りたい情報がWebサイトに載っていない、というのがお客様にとって一番嫌な状況です。そして、「今、何を知りたいか」は時代によって変わりますし、業界によってはタイムリーなネタもあるでしょう。
そうした情報を迅速に出せる体制にしておくことが大事なのであって、「定期的に出すこと」自体が目的なのではない、ということをまず押さえてください。
今でも「サジェストキーワードローラー作戦」のように、メインキーワードに関連する(検索ボリュームの少ない)キーワードで、安価な記事を外部に大量発注しているケースがあるかもしれません。
しかし、私たちがアクセス解析などを見ていても、これはほとんど意味がないケースが本当に多いのです。
外部に記事作成を委託している場合、失礼ながら、その成果をしっかり見ていないことが多いのではないでしょうか。
そのコンテンツがどれだけアクセスを生んでいるか。たとえアクセスがあったとして、その先にある皆さんのサービスページなど、ビジネスに近いコンテンツにお客様を誘導できているかを見ていますか。
もしコンテンツが本当に意味を持ち、適切に設計されていれば、訪問者は次にその会社自体や他のサービスに興味を持つはずです。そこから、より成果に近いコンテンツへ誘導される流れができているはずです。
そうなれば、直帰率は低く、エンゲージメント率は高く、結果的に滞在時間も長くなるでしょう。さらに、アクセス数を見ても、コラム記事だけが伸びているのではなく、サービスページなどビジネスに近いページのアクセスも相関して上がっているはずです。
まずは、今やっている定期更新コンテンツがどれくらいアクセスを生んでいるか。そして、その伸び(コンテンツは蓄積されていくので基本的には伸びるはずです)に伴って、他の重要なページのアクセスも伸びているか、ページ遷移は起きているか。例えば、Google Analytics 4 (GA4) の「経路データ探索」機能や、Microsoft Clarity (マイクロソフト クラリティ) のようなヒートマップツールでクリックの動向を分析し、成果に近いページへ移動しているかを確認してみてください。
なぜ成果が出ないのか。安価な「サジェストローラー」のような形で発注される記事は、単価が安い分、その辺にある情報を検索してまとめた、いわゆる「こたつ記事」になりがちです。
しかし、今はどの企業も同じようなことをやっていますし、中にはもっと手間とコストをかけてしっかりやっている企業もたくさんあります。そうしたコンテンツに勝てるわけがありません。
ページ数だけが増え、サイトが成長しているかのように見えても、実はビジネスには全く貢献していない。そういうケースが本当に多いのです。
もし現状がそれに近いのであれば、思い切ってその予算の使い道を変えるべきです。
例えば、その予算を使って、もっと専門性のあるライターに既存記事の改善を依頼する方がよほど有益です。
お客様目線で見たときに、「こういうトピックスも加えた方が良い」という内容の追加かもしれませんし、「文字ばかりだから図版や箇条書きを入れて見せ方を変えた方が良い」というアドバイスかもしれません。
新しく10記事を書く予算があるなら、その3倍のコストをかけてでも、3記事のメンテナンスにお金をかけた方が絶対に良いと私は思います。
もちろん、新規記事が有効な場合もあります。特に今は、Googleの評価基準であるE-E-A-T(従来のE-A-TにExperience=経験が加わったもの)が重視されています。
AIが過去の情報を再利用してコンテンツを生成していく中で、Googleは新しい情報、つまり「経験」を重要視していると公言しています。
そして、皆さんの頭の中にあって、まだ世の中のWeb上にはない情報は、たくさんあるはずです。
世の中の情報は語り尽くされたように思われがちですが、そんなことはありません。私自身、仕事柄、非常に多くのWebサイトや情報源に触れています。これまで600社、700社といったお客様とお付き合いし、並行して20〜30社の案件を見ているため、インプット量はかなり多い方だと自負しています。
それでも、お客様のところへ伺って話を聞くと、知らなかったことばかりです。
それはどうでもいい話ではなく、商売の根幹に関わる内容で、「ああ、ここはこういう違いがあるんだ」と驚くことばかりです。だからこそ、ビデオ会議は移動時間がなく効率的ですが、やはりお客様の元へ「行く」ということ自体には、ものすごい価値があるなと感じます。
話が少し逸れましたが、私が驚くくらいですから、皆さんの中には「まだ出していない価値ある情報」が確実に眠っているのです。
例えば、営業現場でお客様と話していて、「こういう話は食いつきが良いな」と感じるネタがあると思います。一方で、それを検索キーワードとして調べると、検索ボリューム(検索される回数)は全然ない、ということも多いでしょう。
ですが、昔からそうですが、結局そういうコンテンツがお客様に響くのです。
確かに、集客の初期段階(フロント)、つまり検索エンジンからの流入数(セッション数)を上げるという観点で作るコンテンツは、お客様が知っている言葉、つまり顕在的なキーワードで検索されるため、ある程度の検索ボリュームを意識して作る必要があります。
しかし、その先、サイト内を回遊してもらい、見込み客を育成する(ナーチャリング)段階では、お客様がすでに知っているキーワードにこだわる必要は全くありません。
むしろ、「そういうこともあるんだ」という、先ほど私が申し上げたような「驚き」や「発見」こそが、数ある選択肢の中から皆さんを選んでもらうための強い理由付けになっていきます。
ですから、検索エンジンからの流入数を上げるためのコンテンツは、ある程度キーワードを意識して作る必要がありますが、それ以外の多くのコンテンツは、SEOを過度に気にせず、皆さんが「お客様に響く」と考える内容を中心に作っていくのが良いと思います。
それは決して「週に1回」や「毎日」出さなければいけないものではありません。圧倒的に質が大事です。
質を犠牲にして量を出すことに、今の時代、意味はほぼありません。それが意味を持ったのは、Googleのアルゴリズムが未熟で、かつ世の中にコンテンツが少なかった、本当に昔の時代だけです。その頃の名残を引きずったまま商売をしていると、現状を見誤ってしまいます。
無駄なことにお金を使うくらいなら、やることを3分の1に減らして、その3倍のコストで良いものを作り上げていくべきです。
理想を言えば、その「質」を担保できるのは、皆さん自身です。自分たちの商売に関する情報発信やお客様への説明を、自分たちがやらない、というのは本来おかしな話です。
Webサイトのコンテンツは、それがブログであれ固定ページであれ、皆さん自身がお客様に対して話しかけているのと同じです。そうであるならば、その中身を外部に丸投げしなければならない、という状態はやはり健全ではありません。
今回のテーマである「定期的なコンテンツ更新が難しい」という悩みへの回答をまとめます。
まず、定期的に出す必要はありません。
ただし、本来の目的を間違えないでください。目的は、時代に合わせて出てくる新しい疑問や、Webサイト上でまだ答えられていないお客様の不安を、できるだけ早く解消できるようにコンテンツを整備することです。そのタスクが膨大にあるから、結果的に「定期更新」のように見えるだけです。
その上で、「量より質」で取り組んでください。
そして「質」に関して言えば、ちゃんと商売をしてきた方ほど、皆さんの中に「お客様が知らない、知ったら驚くようなこと」がたくさんあります。私がお客様の話を聞いて驚くのですから、一般の方はもっと驚くはずです。
Webを気にせずコツコツとお客様に向き合ってきた会社こそ、強いコンテンツを持っています。ご自身を信じて、それをどうコンテンツ化するか(記事か、動画か、スライドか)を考えてみてください。
今、外部パートナーにコンテンツ作成を依頼している方は、アクセス数や直帰率、エンゲージメント率をチェックし、「これに意味があるのか」と疑問を持ってみてください。
信頼できるパートナーであれば、「こういう状況だから意味があります」と、必ず数値をもとに説明できるはずです。
それは「このキーワードで何位になりました」という話ではありません。ニッチなキーワードであれば1位を取ることは難しくないからです。そうではなく、「そこからビジネスにこれだけ繋がっています」という説明ができるかどうかです。
もしその説明が曖昧なら、依頼をやめるか、弊社でも他の会社でも構いませんので、セカンドオピニオンを取ってみることをお勧めします。
お客様は、皆さんが思っているほど「毎日更新しているか」なんて気にしていません。もちろん、ブログが1年も更新されていなければ少し不安になるかもしれませんが、基本的には見ていません。
皆さんも、他の業種で何かを探すとき、「この会社は豆知識を定期的に更新してるな」なんてことを気にして選びますか。おそらく、していないのではないでしょうか。だとすれば、皆さんのお客様も同じです。先入観は捨てた方が良いでしょう。
やるからには、濃いコンテンツを作っていくべきです。ちゃんとした濃いコンテンツを作ると、本当にお客様の動きが変わってきます。
そして、それを会社のコンセプトとセットで設計することで、会社に対しての見え方、例えば「ただの下請け会社」なのか、「このトピックスに関して強い専門家集団」なのか、「雑な仕事をするところ」なのか、「きっちり仕事をするところ」なのか、そういった印象もコンテンツによって大きく変わってきます。
ぜひ、もう少し上の視点からコンテンツ戦略を考えていただけると良いのではないかと思います。
(ここからは中山の余談となりますが)
ただ、それは「時代が変わって新しいトピックスが出てきた時に、書ける場所(受け皿)があった方が良い」という観点や、「制作事例」のようにフォーマットを揃えて現場で更新しやすくするためにシステムを導入する、といった理由が主です。必ずビジネス全体を前提においてご提案していますし、中の皆さんが更新し続けられるようにレクチャーも行っています。
コンテンツは本当に難しいですね。量を出したところで読まれませんし、かといって動画を作っても、しっかり考えて作らなければ見られません。これだけ情報が溢れていれば仕方ない流れですが、「何でも作れば良い」というわけではないことを痛感します。
私自身、自社のコンテンツは放置気味で、お客様のことで手一杯になっており、反省点ではあります(ですので、あまり弊社のサイトは参考にしないでください)。
今回の内容は以上になります。
もし何かお困りのことやお悩みのことがあれば、ラウンドナップWebコンサルティングでは、中小企業、小規模事業者、個人事業主の方からのご相談も承っております。すべて代表取締役である私、中山が対応いたしますので、お気軽に問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。
よろしければ、高評価やレビューなどをいただけますと嬉しいです。ご質問もいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。
こちらのフォームへどうぞ。
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/
投稿 第540回:そのブログ記事、無駄になっていませんか?SEO目的コンテンツの有用性とは は 中小企業専門WEBマーケティング支援会社・ラウンドナップWebコンサルティング(Roundup Inc.) に最初に表示されました。
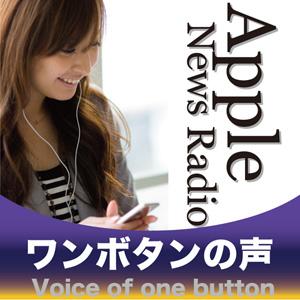
9 Listeners

15 Listeners
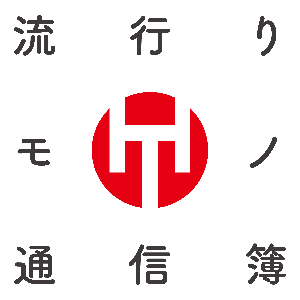
3 Listeners

231 Listeners

3 Listeners

13 Listeners

21 Listeners

42 Listeners

0 Listeners

21 Listeners

5 Listeners

3 Listeners

2 Listeners

2 Listeners

0 Listeners