
Sign up to save your podcasts
Or


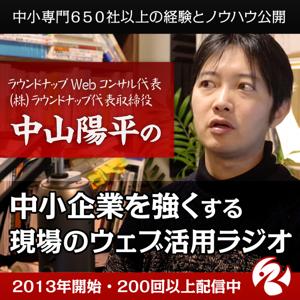

ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。
多くの企業が業務の効率化を目指して様々なツールを導入しています。しかし、その導入が期待通りの成果に繋がらず、高価なライセンス料だけを払い続けている、というケースも少なくありません。今回は、特に中小企業が業務効率化ツールを導入する際に、失敗を避けて成功へと導くためのステップについて、コンサルティングの現場での経験を交えながらお話しします。
CRM(Customer Relationship Management)やSFA(Sales Force Automation)、MA(Marketing Automation)といったツールは、業務を効率化し、新たなマーケティングの可能性を広げるものとして期待されます。特に、経営層や管理職の方々にとっては魅力的に映ることでしょう。
しかし、現実には「数年前に導入したものの、全く使われていない」という状況に陥っている企業に数多く出会います。世の中には成功事例も溢れていますが、その裏で多くの企業がツールの活用に苦戦しているのです。では、成功する企業と失敗する企業とでは、一体何が違うのでしょうか。
様々な企業の事例を見ていくと、成功しているケースには共通点があります。それは、ツールを導入する以前に、社内に明確な業務フローが確立され、共有されているという点です。彼らの成功事例は、「もともとこのような業務フローがあったが、この部分に時間がかかっていた。そこでツールを導入し、このように改善された」という形で語られます。つまり、改善すべき「型」がすでにあるのです。
一方で、うまくいかないケースの多くは、ツールを導入することによって、業務の「仕組み」も一緒に作ろうとしてしまうパターンです。例えば、見込み客を獲得し、アプローチし、営業部門でフォローアップしていく、という一連の流れが定まっていない状態で、「このツールを使えばうまくいくはずだ」と、仕組みそのものを買うような感覚で導入してしまうのです。
このアプローチは、よほど手厚いコンサルティングがセットになっており、かつ社内に変革を受け入れる体制が整っていない限り、ほとんどの場合失敗に終わります。特に、すでに様々な「暗黙のルール」で業務が回っている企業に、全く新しいデジタルツールと新しい業務フローという、2つの大きな変化を同時に持ち込むと、現場は間違いなく混乱します。
結果として、以前のやり方と新しいツールの二重管理で業務が増えるだけになるか、あるいは「面倒だから」と誰も使わなくなり、高価なツールが放置されることになるのです。
では、どうすればツールの導入を成功させられるのでしょうか。答えはシンプルで、「仕組みづくり」と「ツール導入」を切り分けて、順番に進めることです。
最初に手掛けるべきは、ツールの選定ではありません。まずは、デジタルに頼らず、今社内にある方法で業務の仕組みを確立し、それを動かしてみることです。
それは、将来的に見れば「なぜ紙で管理しているんだ」「付箋で伝言するのか」と感じるような、非効率な方法で構いません。重要なのは、まず業務のフローを「見える化」し、その流れを関係者全員が理解し、実行できる状態を作ることです。
多くの会社には、明文化されていなくても「この案件は〇〇さんに渡せば進む」「この書類はここに置いておけば大丈夫」といった、暗黙知で成り立っている業務フローが存在します。最初のステップは、こうした流れをきちんと文書や図に落とし込み、誰もがわかる形にすることから始まります。
社内で業務フローが確立され、「業務を改善することの重要性」が浸透したら、いよいよツールの出番です。その段階で、「この業務フローの、この部分を効率化するために最適なツールは何か」という視点でツールを選定し、導入します。
この順番であれば、現場のスタッフも「今まで紙でやっていた作業が、このツール入力に置き換わるんだな」「ここの手間は減るけれど、あちらの作業は変わらないな」というように、変化点を具体的に理解できます。業務全体の流れを把握していない段階でツールを導入しようとするから、何がどう変わるのか分からず、大混乱に陥ってしまうのです。
仕組み化を先行させるアプローチを取る上で、さらに心に留めておいていただきたい点が2つあります。
仕組みの構築からツールの導入・定着までにかかる時間は、自分たちが想定している期間の、少なくとも倍はかかると考えておくことをお勧めします。また、ツールの費用だけでなく、人件費や移行期間中の機会損失といった見えないコストも考慮すると、予算も余裕を持たせた方が賢明です。
多くのツールには、「このように使ってもらうのが最も効率的だ」という、作り手側が想定した標準的な業務フローが存在します。自分たちに合うやり方が全く分からない場合に、荒療治としてそのツールの標準フローに自社の業務を無理やり合わせていく、という選択肢も無いわけではありません。
しかし、基本的にはお勧めしません。どの会社にも、これまでの歴史の中で最適化されてきた独自の業務の流れがあります。まずはその流れをツール上で再現することから始めましょう。ツールによって業務が数値化され、ボトルネックが見えてくれば、そのデータをもとに周囲を説得しながら、段階的に業務を改善していく方が、はるかに現実的で成功率も高まります。
業務の無駄をなくし、効率化を進めたいという気持ちは非常によく分かります。しかし、ツールが仕組みを作ってくれるわけではありません。ツールは、すでにある仕組みをより効率的に動かすための道具です。
この順番を間違えると、効率化どころか、かえって無駄な業務を増やしてしまう結果になりかねません。人手不足が深刻化する中で、業務効率化は喫緊の課題です。一見遠回りに見えても、まずは社内の仕組み化・見える化から着手することが、成功への最も確実な道筋です。
これはマーケティング活動においても同様で、仕組み化を進めることで、何が問題なのかが明確になり、数字に基づいた改善がしやすくなります。ぜひ、貴社の業務プロセスを見直すきっかけにしていただければと思います。
続きはPodcastをご覧下さい。
こちらのフォームへどうぞ。
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/
投稿 第547回:業務効率化ツールの導入前に、中小企業が押さえるべき成功へのステップ は 中小企業専門WEBマーケティング支援会社・ラウンドナップWebコンサルティング(Roundup Inc.) に最初に表示されました。
 View all episodes
View all episodes


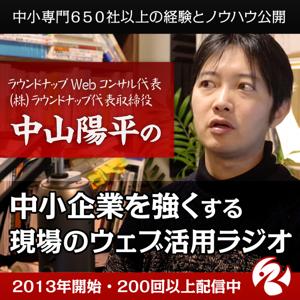 By ラウンドナップ・Webコンサルティング 代表 中山陽平
By ラウンドナップ・Webコンサルティング 代表 中山陽平
ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。
多くの企業が業務の効率化を目指して様々なツールを導入しています。しかし、その導入が期待通りの成果に繋がらず、高価なライセンス料だけを払い続けている、というケースも少なくありません。今回は、特に中小企業が業務効率化ツールを導入する際に、失敗を避けて成功へと導くためのステップについて、コンサルティングの現場での経験を交えながらお話しします。
CRM(Customer Relationship Management)やSFA(Sales Force Automation)、MA(Marketing Automation)といったツールは、業務を効率化し、新たなマーケティングの可能性を広げるものとして期待されます。特に、経営層や管理職の方々にとっては魅力的に映ることでしょう。
しかし、現実には「数年前に導入したものの、全く使われていない」という状況に陥っている企業に数多く出会います。世の中には成功事例も溢れていますが、その裏で多くの企業がツールの活用に苦戦しているのです。では、成功する企業と失敗する企業とでは、一体何が違うのでしょうか。
様々な企業の事例を見ていくと、成功しているケースには共通点があります。それは、ツールを導入する以前に、社内に明確な業務フローが確立され、共有されているという点です。彼らの成功事例は、「もともとこのような業務フローがあったが、この部分に時間がかかっていた。そこでツールを導入し、このように改善された」という形で語られます。つまり、改善すべき「型」がすでにあるのです。
一方で、うまくいかないケースの多くは、ツールを導入することによって、業務の「仕組み」も一緒に作ろうとしてしまうパターンです。例えば、見込み客を獲得し、アプローチし、営業部門でフォローアップしていく、という一連の流れが定まっていない状態で、「このツールを使えばうまくいくはずだ」と、仕組みそのものを買うような感覚で導入してしまうのです。
このアプローチは、よほど手厚いコンサルティングがセットになっており、かつ社内に変革を受け入れる体制が整っていない限り、ほとんどの場合失敗に終わります。特に、すでに様々な「暗黙のルール」で業務が回っている企業に、全く新しいデジタルツールと新しい業務フローという、2つの大きな変化を同時に持ち込むと、現場は間違いなく混乱します。
結果として、以前のやり方と新しいツールの二重管理で業務が増えるだけになるか、あるいは「面倒だから」と誰も使わなくなり、高価なツールが放置されることになるのです。
では、どうすればツールの導入を成功させられるのでしょうか。答えはシンプルで、「仕組みづくり」と「ツール導入」を切り分けて、順番に進めることです。
最初に手掛けるべきは、ツールの選定ではありません。まずは、デジタルに頼らず、今社内にある方法で業務の仕組みを確立し、それを動かしてみることです。
それは、将来的に見れば「なぜ紙で管理しているんだ」「付箋で伝言するのか」と感じるような、非効率な方法で構いません。重要なのは、まず業務のフローを「見える化」し、その流れを関係者全員が理解し、実行できる状態を作ることです。
多くの会社には、明文化されていなくても「この案件は〇〇さんに渡せば進む」「この書類はここに置いておけば大丈夫」といった、暗黙知で成り立っている業務フローが存在します。最初のステップは、こうした流れをきちんと文書や図に落とし込み、誰もがわかる形にすることから始まります。
社内で業務フローが確立され、「業務を改善することの重要性」が浸透したら、いよいよツールの出番です。その段階で、「この業務フローの、この部分を効率化するために最適なツールは何か」という視点でツールを選定し、導入します。
この順番であれば、現場のスタッフも「今まで紙でやっていた作業が、このツール入力に置き換わるんだな」「ここの手間は減るけれど、あちらの作業は変わらないな」というように、変化点を具体的に理解できます。業務全体の流れを把握していない段階でツールを導入しようとするから、何がどう変わるのか分からず、大混乱に陥ってしまうのです。
仕組み化を先行させるアプローチを取る上で、さらに心に留めておいていただきたい点が2つあります。
仕組みの構築からツールの導入・定着までにかかる時間は、自分たちが想定している期間の、少なくとも倍はかかると考えておくことをお勧めします。また、ツールの費用だけでなく、人件費や移行期間中の機会損失といった見えないコストも考慮すると、予算も余裕を持たせた方が賢明です。
多くのツールには、「このように使ってもらうのが最も効率的だ」という、作り手側が想定した標準的な業務フローが存在します。自分たちに合うやり方が全く分からない場合に、荒療治としてそのツールの標準フローに自社の業務を無理やり合わせていく、という選択肢も無いわけではありません。
しかし、基本的にはお勧めしません。どの会社にも、これまでの歴史の中で最適化されてきた独自の業務の流れがあります。まずはその流れをツール上で再現することから始めましょう。ツールによって業務が数値化され、ボトルネックが見えてくれば、そのデータをもとに周囲を説得しながら、段階的に業務を改善していく方が、はるかに現実的で成功率も高まります。
業務の無駄をなくし、効率化を進めたいという気持ちは非常によく分かります。しかし、ツールが仕組みを作ってくれるわけではありません。ツールは、すでにある仕組みをより効率的に動かすための道具です。
この順番を間違えると、効率化どころか、かえって無駄な業務を増やしてしまう結果になりかねません。人手不足が深刻化する中で、業務効率化は喫緊の課題です。一見遠回りに見えても、まずは社内の仕組み化・見える化から着手することが、成功への最も確実な道筋です。
これはマーケティング活動においても同様で、仕組み化を進めることで、何が問題なのかが明確になり、数字に基づいた改善がしやすくなります。ぜひ、貴社の業務プロセスを見直すきっかけにしていただければと思います。
続きはPodcastをご覧下さい。
こちらのフォームへどうぞ。
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/
投稿 第547回:業務効率化ツールの導入前に、中小企業が押さえるべき成功へのステップ は 中小企業専門WEBマーケティング支援会社・ラウンドナップWebコンサルティング(Roundup Inc.) に最初に表示されました。
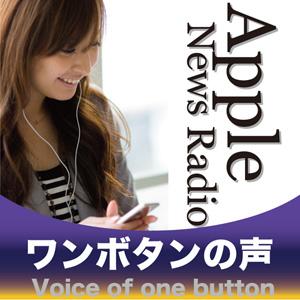
9 Listeners

15 Listeners
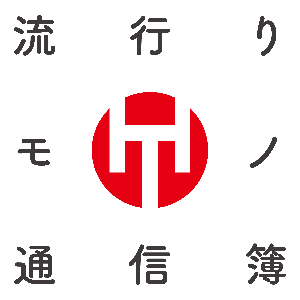
3 Listeners

231 Listeners

3 Listeners

13 Listeners

21 Listeners

42 Listeners

0 Listeners

21 Listeners

5 Listeners

3 Listeners

2 Listeners

2 Listeners

0 Listeners