
Sign up to save your podcasts
Or


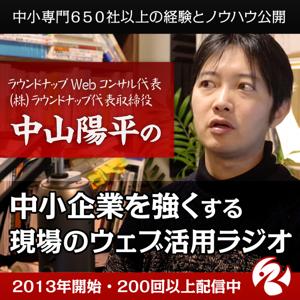

ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。今回は、AIの進化がもたらす、決して目を背けることのできない未来についてお話しします。それは、情報発信できる企業とできない企業が明確に「勝ち組」と「負け組」に分かれてしまう「二極化」、そして情報発信できない企業が淘汰されかねない時代の到来です。以前は、AIがビジネスの中心になるのはまだ先だと考えていました。しかし、ここ最近の動向を見て、その考えを改めました。中小企業は、思っていたよりもずっと早くAIに対応しなければ、生き残れない可能性があるという強い危機感をお伝えします。
AI検索、例えば「Perplexity(パープレキシティ)」のようなツールを実際に使ってみると、従来のGoogle検索との決定的な違いがわかります。従来の検索では、「何を」「どういう基準で」調べるかは、ユーザー自身が考える必要がありました。例えば、賃貸物件を探すなら、「おすすめの選び方」をまず調べて、その基準を元に物件を探す、というように2つのステップが必要だったのです。
しかし、AI検索は違います。「こういう状況で、こういうものを探しているんだけど、どういう基準で探したらいい?それに合うものは何?」と尋ねると、AIは「駅から何分以内、防音性、耐震性能といった基準で選ぶと良いでしょう」という「判断基準」と、それに合致する「具体的なリスト」を同時に提示してくれます。もっと言えば、「この辺でおいしいラーメン屋」と聞くだけで、AIが「こういう選び方がありますよ」と先回りして考え方を示し、おすすめのお店まで提案してくれるのです。
これはつまり、ユーザーが何も考えずに希望を伝えるだけで、AIが裏側で判断基準を決め、それに沿った選択肢を提示するという仕組みが確立されつつあることを意味します。
これまでのWebマーケティングは、「まず自社のサイトに来てもらい、そこで独自の魅力を伝えよう」というモデルが主流でした。しかし、AIが判断基準を提示するようになると、その基準に合致しない魅力、つまり「サイトに来てくれればわかる」「使ってもらえればわかる」といった価値は、そもそもユーザーの目に触れる機会すら失ってしまいます。
AIは、多くの人に当てはまる「最大公約数」的な判断基準を提示しがちです。その結果、企業はその限られた基準の中で戦うしかなくなり、競争は激化します。この戦いで有利なのは、すでに豊富な情報(資産)を持っているか、あるいは質の高い情報を継続的に発信できる(資産を作る能力が高い)企業です。これは、採用市場で起きている「採れる会社と採れない会社の二極化」と全く同じ構造です。魅力的なストーリーを提示できる企業に人が集まり、そうでない企業には人が来ない。この現象が、購買行動の世界でも起こる可能性が非常に高いのです。
私がこの変化のスピードが速いと感じる理由は、AIの浸透の仕方にあります。AIは「新しい検索エンジン」として一気に広がるのではなく、GoogleマップのQ&A機能のように、既存の様々なツールに細かく組み込まれる形で私たちの日常に入り込んでいます。
人間は、大きな変化には抵抗しますが、小さな変化が積み重なり、気づいたら使っていた、という状況には弱いものです。そして、「今まで便利に使っていたこの機能が、実はAIだった」と後から気づかされると、「AIはよくないと思っていたけど、便利だったしな」と態度が変わりやすくなります。このように、細かく、静かに浸透していくことで、AIの普及は一気に加速していくでしょう。
では、この大きな変化の波に乗り遅れないために、何をすべきか。結論から言えば、「自分たちの情報を、自分たちで掘り起こし、外部にきちんと見える形で発信できるようになる」ことです。言うのは簡単ですが、これは非常に難しい課題です。日々の業務に追われる中で、情報発信の必要性を感じていなかったり、社内に担当者がいなかったりするのが実情でしょう。
しかし、このまま情報発信能力がないままAI時代に突入するのは、致命的な状況を招きかねません。
これからの情報発信は、単に「何屋さんで、何を作っているか」を伝えるだけでは不十分です。就職活動を思い出してください。企業は理念やストーリーを掲げ、共感を呼び起こそうとします。それと同じで、「自分たちは何を解決する企業なのか」というミッションを、ストーリーとして語れる会社になっていかなければなりません。
そのためには、企業理念や事業の方向性といった、会社全体の根本的な部分から見直し、合意形成を図る必要があります。これは特定部署だけで完結する話ではなく、会社全体の文化を変えていく壮大なプロジェクトです。特に、歴史が長く、なかなか変化しづらい体質の企業ほど、今、大きな危機に瀕していると言えるかもしれません。逆に、経営層と現場が一体となって迅速に意思決定できる、少人数の企業には大きな可能性があります。
Webの世界での競争が厳しくなるからこそ、視点を変えることも重要です。特に地域に根ざしたビジネスを展開している企業は、Webで顧客と接点を持った後、いかにオフライン(リアル)の関係性で顧客を掴み続けるか、という戦略が有効になります。Webへの依存度を見直し、リアルでの活動と連携させることで、独自のポジションを築くことができるはずです。
コンテンツの考え方もアップデートが必要です。単にSEOを意識して記事を量産するだけでは、もはや意味がありません。そうした記事は誰にも読まれず、自己満足に終わってしまいます。これからは、顧客の心の中に自社の存在を刻むための、洗練されたコンテンツが必要です。それはブログ記事だけでなく、地域イベントへの協賛やボランティア、未来の顧客を育てるための学校での活動など、あらゆる企業活動が「コンテンツ」になり得るのです。
今回、最も伝えたかったことは、「AIによって判断基準と結果が自動的に提示される時代が、すぐそこまで来ている」という事実と、そのために必要な行動の「スピード感」です。
「来年に向けて準備しよう」ではありません。「今年やれることは、すべて今年のうちにやる」というくらいのスピード感で、自社を変化させていかなければ、厳しい状況に追い込まれるでしょう。実際、多くのお客様からご相談をいただく中で、この危機感を共有している企業は増えていると感じます。もし、何から手をつければいいかわからない、という状況であれば、私たちのような外部のパートナーと共に、二人三脚で未来を考えていくことも一つの選択肢です。
今回の話が、皆さんの会社が未来へ向けて一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。役に立った、面白いと感じていただけたら、各種プラットフォームでの高評価やシェアをしていただけると嬉しいです。また、ウェブサイトでは、ブログ記事やメールマガジンのバックナンバーなど、他の情報も無料で公開しておりますので、ぜひご覧ください。
最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。ラウンドナップ・ウェブコンサルティング株式会社、代表取締役の中山がお送りいたしました。
AI検索が「判断基準」と「おすすめ」を同時に提示するようになり、顧客の購買行動が大きく変わるためです。この変化に乗り遅れると、顧客から選ばれる機会そのものを失い、ビジネスの二極化で不利な立場に置かれる可能性が高いからです。
「Webサイトに来てもらえれば良さが伝わる」という考え方が通用しなくなることです。AIが標準化された基準で企業を評価するため、情報発信ができていない企業は比較の土俵にすら上がれないリスクがあります。
自社の理念やミッションに基づいたストーリーを発信することです。「何をしている会社か」だけでなく「何を解決する企業か」を明確に伝え、AIと顧客の両方に自社の価値を認識させることが重要になります。
キーワードを詰め込むような小手先のSEOは効果が薄れます。しかし、ユーザーの疑問に応え、専門性や信頼性を示す質の高いコンテンツを作るという本質的なSEOは、AI時代においてさらに重要性を増します。
まず社内で「自社は何を解決する企業なのか」という根本を議論し、言語化することから始めましょう。その上で、自分たちの言葉でストーリーとして発信する体制を、外部の支援も視野に入れながら構築していくことが第一歩です。
こちらのフォームへどうぞ。
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/
投稿 第550回:AI検索が引き起こす二極化時代…情報発信できない企業が淘汰される前に、今すぐ取り組むべきこと は 中小企業専門WEBマーケティング支援会社・ラウンドナップWebコンサルティング(Roundup Inc.) に最初に表示されました。
 View all episodes
View all episodes


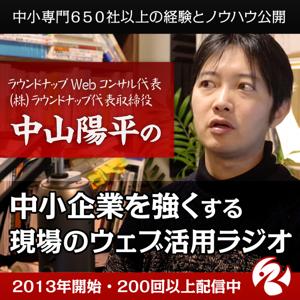 By ラウンドナップ・Webコンサルティング 代表 中山陽平
By ラウンドナップ・Webコンサルティング 代表 中山陽平
ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。今回は、AIの進化がもたらす、決して目を背けることのできない未来についてお話しします。それは、情報発信できる企業とできない企業が明確に「勝ち組」と「負け組」に分かれてしまう「二極化」、そして情報発信できない企業が淘汰されかねない時代の到来です。以前は、AIがビジネスの中心になるのはまだ先だと考えていました。しかし、ここ最近の動向を見て、その考えを改めました。中小企業は、思っていたよりもずっと早くAIに対応しなければ、生き残れない可能性があるという強い危機感をお伝えします。
AI検索、例えば「Perplexity(パープレキシティ)」のようなツールを実際に使ってみると、従来のGoogle検索との決定的な違いがわかります。従来の検索では、「何を」「どういう基準で」調べるかは、ユーザー自身が考える必要がありました。例えば、賃貸物件を探すなら、「おすすめの選び方」をまず調べて、その基準を元に物件を探す、というように2つのステップが必要だったのです。
しかし、AI検索は違います。「こういう状況で、こういうものを探しているんだけど、どういう基準で探したらいい?それに合うものは何?」と尋ねると、AIは「駅から何分以内、防音性、耐震性能といった基準で選ぶと良いでしょう」という「判断基準」と、それに合致する「具体的なリスト」を同時に提示してくれます。もっと言えば、「この辺でおいしいラーメン屋」と聞くだけで、AIが「こういう選び方がありますよ」と先回りして考え方を示し、おすすめのお店まで提案してくれるのです。
これはつまり、ユーザーが何も考えずに希望を伝えるだけで、AIが裏側で判断基準を決め、それに沿った選択肢を提示するという仕組みが確立されつつあることを意味します。
これまでのWebマーケティングは、「まず自社のサイトに来てもらい、そこで独自の魅力を伝えよう」というモデルが主流でした。しかし、AIが判断基準を提示するようになると、その基準に合致しない魅力、つまり「サイトに来てくれればわかる」「使ってもらえればわかる」といった価値は、そもそもユーザーの目に触れる機会すら失ってしまいます。
AIは、多くの人に当てはまる「最大公約数」的な判断基準を提示しがちです。その結果、企業はその限られた基準の中で戦うしかなくなり、競争は激化します。この戦いで有利なのは、すでに豊富な情報(資産)を持っているか、あるいは質の高い情報を継続的に発信できる(資産を作る能力が高い)企業です。これは、採用市場で起きている「採れる会社と採れない会社の二極化」と全く同じ構造です。魅力的なストーリーを提示できる企業に人が集まり、そうでない企業には人が来ない。この現象が、購買行動の世界でも起こる可能性が非常に高いのです。
私がこの変化のスピードが速いと感じる理由は、AIの浸透の仕方にあります。AIは「新しい検索エンジン」として一気に広がるのではなく、GoogleマップのQ&A機能のように、既存の様々なツールに細かく組み込まれる形で私たちの日常に入り込んでいます。
人間は、大きな変化には抵抗しますが、小さな変化が積み重なり、気づいたら使っていた、という状況には弱いものです。そして、「今まで便利に使っていたこの機能が、実はAIだった」と後から気づかされると、「AIはよくないと思っていたけど、便利だったしな」と態度が変わりやすくなります。このように、細かく、静かに浸透していくことで、AIの普及は一気に加速していくでしょう。
では、この大きな変化の波に乗り遅れないために、何をすべきか。結論から言えば、「自分たちの情報を、自分たちで掘り起こし、外部にきちんと見える形で発信できるようになる」ことです。言うのは簡単ですが、これは非常に難しい課題です。日々の業務に追われる中で、情報発信の必要性を感じていなかったり、社内に担当者がいなかったりするのが実情でしょう。
しかし、このまま情報発信能力がないままAI時代に突入するのは、致命的な状況を招きかねません。
これからの情報発信は、単に「何屋さんで、何を作っているか」を伝えるだけでは不十分です。就職活動を思い出してください。企業は理念やストーリーを掲げ、共感を呼び起こそうとします。それと同じで、「自分たちは何を解決する企業なのか」というミッションを、ストーリーとして語れる会社になっていかなければなりません。
そのためには、企業理念や事業の方向性といった、会社全体の根本的な部分から見直し、合意形成を図る必要があります。これは特定部署だけで完結する話ではなく、会社全体の文化を変えていく壮大なプロジェクトです。特に、歴史が長く、なかなか変化しづらい体質の企業ほど、今、大きな危機に瀕していると言えるかもしれません。逆に、経営層と現場が一体となって迅速に意思決定できる、少人数の企業には大きな可能性があります。
Webの世界での競争が厳しくなるからこそ、視点を変えることも重要です。特に地域に根ざしたビジネスを展開している企業は、Webで顧客と接点を持った後、いかにオフライン(リアル)の関係性で顧客を掴み続けるか、という戦略が有効になります。Webへの依存度を見直し、リアルでの活動と連携させることで、独自のポジションを築くことができるはずです。
コンテンツの考え方もアップデートが必要です。単にSEOを意識して記事を量産するだけでは、もはや意味がありません。そうした記事は誰にも読まれず、自己満足に終わってしまいます。これからは、顧客の心の中に自社の存在を刻むための、洗練されたコンテンツが必要です。それはブログ記事だけでなく、地域イベントへの協賛やボランティア、未来の顧客を育てるための学校での活動など、あらゆる企業活動が「コンテンツ」になり得るのです。
今回、最も伝えたかったことは、「AIによって判断基準と結果が自動的に提示される時代が、すぐそこまで来ている」という事実と、そのために必要な行動の「スピード感」です。
「来年に向けて準備しよう」ではありません。「今年やれることは、すべて今年のうちにやる」というくらいのスピード感で、自社を変化させていかなければ、厳しい状況に追い込まれるでしょう。実際、多くのお客様からご相談をいただく中で、この危機感を共有している企業は増えていると感じます。もし、何から手をつければいいかわからない、という状況であれば、私たちのような外部のパートナーと共に、二人三脚で未来を考えていくことも一つの選択肢です。
今回の話が、皆さんの会社が未来へ向けて一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。役に立った、面白いと感じていただけたら、各種プラットフォームでの高評価やシェアをしていただけると嬉しいです。また、ウェブサイトでは、ブログ記事やメールマガジンのバックナンバーなど、他の情報も無料で公開しておりますので、ぜひご覧ください。
最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。ラウンドナップ・ウェブコンサルティング株式会社、代表取締役の中山がお送りいたしました。
AI検索が「判断基準」と「おすすめ」を同時に提示するようになり、顧客の購買行動が大きく変わるためです。この変化に乗り遅れると、顧客から選ばれる機会そのものを失い、ビジネスの二極化で不利な立場に置かれる可能性が高いからです。
「Webサイトに来てもらえれば良さが伝わる」という考え方が通用しなくなることです。AIが標準化された基準で企業を評価するため、情報発信ができていない企業は比較の土俵にすら上がれないリスクがあります。
自社の理念やミッションに基づいたストーリーを発信することです。「何をしている会社か」だけでなく「何を解決する企業か」を明確に伝え、AIと顧客の両方に自社の価値を認識させることが重要になります。
キーワードを詰め込むような小手先のSEOは効果が薄れます。しかし、ユーザーの疑問に応え、専門性や信頼性を示す質の高いコンテンツを作るという本質的なSEOは、AI時代においてさらに重要性を増します。
まず社内で「自社は何を解決する企業なのか」という根本を議論し、言語化することから始めましょう。その上で、自分たちの言葉でストーリーとして発信する体制を、外部の支援も視野に入れながら構築していくことが第一歩です。
こちらのフォームへどうぞ。
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/
投稿 第550回:AI検索が引き起こす二極化時代…情報発信できない企業が淘汰される前に、今すぐ取り組むべきこと は 中小企業専門WEBマーケティング支援会社・ラウンドナップWebコンサルティング(Roundup Inc.) に最初に表示されました。
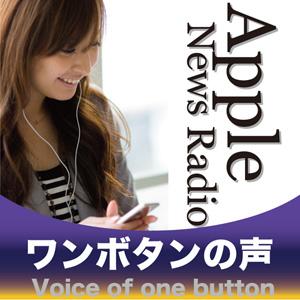
9 Listeners

15 Listeners
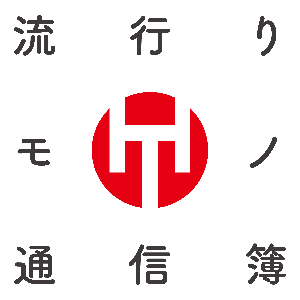
3 Listeners

231 Listeners

3 Listeners

13 Listeners

21 Listeners

42 Listeners

0 Listeners

21 Listeners

5 Listeners

3 Listeners

2 Listeners

2 Listeners

0 Listeners