
Sign up to save your podcasts
Or


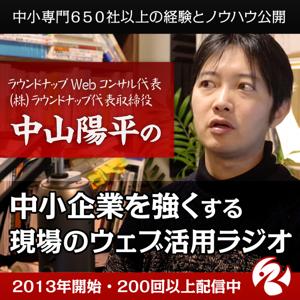

今回は、前回のポッドキャストでお話しした「SEO業界の収益構造がどのように変わってきているか」というテーマを深掘りしていきたいと思います。
これは、特定の企業の内部情報ではなく、あくまで私のネットワークや、クライアント様に提案される資料などから感じ取る「現場の肌感覚」として捉えていただければ幸いです。
皆さんは、SEO業界が何で収益を上げていると思われますか。多くの方は「Webサイトの検索順位を上げるための様々な施策」を想像するのではないでしょうか。それは、かつては正解でした。
昔は、専門的な技術(テクニカルSEO)を駆使することで、明確に成果を出すことができました。そして2014年頃、日本で「コンテンツマーケティング」という言葉が広まり始めます。これは、企業から顧客へ情報を押し出す「プッシュ型」ではなく、顧客に有益な情報を提供して惹きつけ、関係性を育んでいく「インバウンドマーケティング」という考え方が注目された時期と重なります。
この流れの中で、「コンテンツSEO」という言葉が生まれました。本来、コンテンツはSEOのためだけにあるのではなく、顧客とのコミュニケーション手段です。しかし、テクニカルな手法が通用しにくくなる中で、良質なコンテンツを作ることがSEOの主要な施策として定着し、現在まで続いているという認識が一般的かもしれません。売上の構成比で言えば、テクニカルな施策が3割、コンテンツ制作が7割、といったイメージでしょうか。
しかし、現在ではその構造が大きく変わってきていると感じています。正直なところ、従来のテクニカルな施策とコンテンツ制作だけでは、ビジネスとして成り立たせるのが難しくなっているのです。
例えば、Webサイト全体の診断(オーディット)のような大規模なメンテナンス業務は、四半期や年に一度といったスパンで需要があります。これらはある程度の単価になりますが、AIの活用で効率化が進んでいるため、以前ほどの価値は提供しにくくなっています。
毎月継続的に行うような細かなチューニング業務は、すぐに行うべき施策が尽きてしまうため、継続的な仕事として成立しにくいのが実情です。提案はできても、クライアント様の社内体制が追い付かず「実施できない」というボトルネックに突き当たることも少なくありません。
コンテンツ制作についても同様です。検索キーワードの候補(サジェスト)を網羅するだけ、といったいわゆる「こたつ記事」は、本当に効果が出なくなりました。実際にクライアント様のサイトを分析しても、そうした記事からの流入がほとんどないケースが大半です。サイト全体の評価を高める効果も、限定的だと感じます。
多くのクライアント様も「月々10万円、20万円を払ってコンテンツを作り続けても、意味があるのだろうか」と気づき始めており、コンテンツ制作の単価は下落傾向にあります。高い価格では売れなくなってきているのです。
では、SEO会社はどこに収益の軸足を移しているのでしょうか。現場で感じる大きな流れは、主に以下の3つです。
一つは、ローカル領域へのシフトです。MEO(Map Engine Optimization)やローカルSEOと呼ばれる分野で、実店舗を持つビジネスにとって重要なGoogleマップでの表示を最適化する施策です。この分野は、残念ながら悪質な業者も多いのが現状ですが、Webサイト本体のSEOだけではカバーしきれないニーズに応える形で、提案を行う会社が増えている印象です。
もう一つは「AI対応」です。まだ日本には本格導入されていませんが、Googleが海外で進めている検索結果へのAI導入を見据え、「AIに最適化されたコンテンツ作り」や「既存サイトの改修」を提案するケースが増えています。将来への投資として、これに応じる企業も多いようです。
次に、人材関連のビジネスです。企業のWeb担当者として専門人材を送り込んだり、フリーランスと企業をマッチングさせたりして、仲介手数料を得るモデルです。これはウェブマーケティング業界全体で数年前から見られる動きですが、SEO会社がこれまで培ってきたブランド力を活かして、この事業を収益の柱に加えるケースが増えています。
うまく軌道に乗れば大きな収益が見込めるため、多くの会社が参入しています。ただし、提供される人材の質は担当者やサービスによって大きく異なるため、注意が必要です。
もう一つの大きな柱が、エデュケーション(教育)関連事業です。これは、同業者である制作会社や広告代理店、あるいは地域の企業を取りまとめる組織などに対して、SEOやコンテンツ制作のツール、あるいはノウハウそのものを販売する、いわば「ツルハシを売る」ビジネスです。
特に海外のツール提供企業は、ツールの使い方だけでなく、そのツールを使いこなすための前提となる考え方や学習コンテンツの提供に非常に力を入れています。対面での個別サポートが苦手な会社でも、ツールや仕組みの販売は比較的行いやすいため、今後AIと絡めてこの分野に注力する会社はさらに増えていくでしょう。
こうした業界の変化を踏まえ、外部のパートナーに依頼する際には、いくつか知っておいていただきたいことがあります。
まず、SEO会社の収益構造がこのように多角化しているという事実を知っておくことが重要です。その上で、自社が本当に依頼したい分野において、その会社がどれほどの専門性や実績を持っているのかを必ず確認しましょう。
例えば、人材紹介を大きな収益源としている会社であれば、テクニカルなSEO施策に関するスキルを持ったスタッフが少ない可能性も考えられます。それは良い悪いではなく、会社としての成り立ちの問題です。自社のニーズと、相手の強みが合致しているかを見極めることが大切です。
ちなみに、私はしばしばSEOの専門会社と見られがちですが、そうではありません。私は、Webの活用に悩む中小企業や小規模事業者の「右腕」となり、戦略立案から実行までを伴走支援することです。
Webサイトをどう改善すればよいか分からない、一度失敗してしまったが次は成功させたい、そういった企業様に寄り添い、社内にノウハウを蓄積しながら、どうしても手が回らない部分の作業を代行しています。その過程で、まずは検索エンジンからのアクセスを確保することが多いため、結果的にSEOに関するお話が多くなる、というのが実情です。
クライアント様側の変化も感じています。「どうすれば順位が上がりますか?」という質問よりも、「どうすればもっと問い合わせが増えますか?」「どうすれば売上が上がりますか?」といった、事業の成果に直結する問いが増えてきました。これは、多くの企業が事業目線でWeb活用を捉えられるようになってきた、非常に良い傾向だと感じています。
一方で、業界全体がGoogleのAI導入(AI Overview)に大きく揺れています。海外ではすでに導入が始まっており、Webサイト運営者やSEO関係者の間では、その影響を巡って賛否両論、まさに議論が絶えない状況です。これが当たり前の未来だと受け入れる人々と、これまでのやり方が通用しなくなることに反発する人々との間で、意見がぶつかり合っています。
本来であれば、メディアが中立的な立場で情報を整理すべきですが、残念ながら現状は、PV(ページビュー)を稼ぎやすい、対立を煽るような話題に偏りがちです。これは、ある意味でコンテンツマーケティングの行き詰まりを示しているのかもしれません。
これからの時代、SEOを単体で考えてはいけません。SEOはあくまで、自社のターゲット顧客に存在を知ってもらうための一つの「手段」でしかありません。
本当に取り組むべきは、自社が何者で、どのような価値を提供できるのかを伝え、顧客との信頼関係を築いていく「ブランド構築」です。それはWebサイトの中だけで完結するものではなく、オフラインの活動も含めた会社全体の取り組みです。その上で、Webという領域でブランド構築を加速させるための一つのパーツとして、SEOが存在します。この主従関係を見誤ると、大きな失敗につながる可能性がありますので、ぜひ気をつけていただきたいです。
こちらのフォームへどうぞ。 https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/
投稿 第564回:SEO業界の「提供価値」と「収益の柱」はどんどん変わっている…? は 中小企業専門WEBマーケティング支援会社・ラウンドナップWebコンサルティング(Roundup Inc.) に最初に表示されました。
 View all episodes
View all episodes


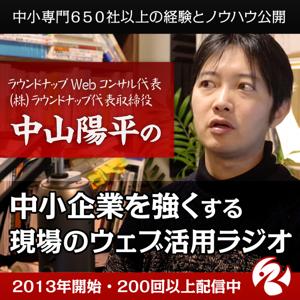 By ラウンドナップ・Webコンサルティング 代表 中山陽平
By ラウンドナップ・Webコンサルティング 代表 中山陽平
今回は、前回のポッドキャストでお話しした「SEO業界の収益構造がどのように変わってきているか」というテーマを深掘りしていきたいと思います。
これは、特定の企業の内部情報ではなく、あくまで私のネットワークや、クライアント様に提案される資料などから感じ取る「現場の肌感覚」として捉えていただければ幸いです。
皆さんは、SEO業界が何で収益を上げていると思われますか。多くの方は「Webサイトの検索順位を上げるための様々な施策」を想像するのではないでしょうか。それは、かつては正解でした。
昔は、専門的な技術(テクニカルSEO)を駆使することで、明確に成果を出すことができました。そして2014年頃、日本で「コンテンツマーケティング」という言葉が広まり始めます。これは、企業から顧客へ情報を押し出す「プッシュ型」ではなく、顧客に有益な情報を提供して惹きつけ、関係性を育んでいく「インバウンドマーケティング」という考え方が注目された時期と重なります。
この流れの中で、「コンテンツSEO」という言葉が生まれました。本来、コンテンツはSEOのためだけにあるのではなく、顧客とのコミュニケーション手段です。しかし、テクニカルな手法が通用しにくくなる中で、良質なコンテンツを作ることがSEOの主要な施策として定着し、現在まで続いているという認識が一般的かもしれません。売上の構成比で言えば、テクニカルな施策が3割、コンテンツ制作が7割、といったイメージでしょうか。
しかし、現在ではその構造が大きく変わってきていると感じています。正直なところ、従来のテクニカルな施策とコンテンツ制作だけでは、ビジネスとして成り立たせるのが難しくなっているのです。
例えば、Webサイト全体の診断(オーディット)のような大規模なメンテナンス業務は、四半期や年に一度といったスパンで需要があります。これらはある程度の単価になりますが、AIの活用で効率化が進んでいるため、以前ほどの価値は提供しにくくなっています。
毎月継続的に行うような細かなチューニング業務は、すぐに行うべき施策が尽きてしまうため、継続的な仕事として成立しにくいのが実情です。提案はできても、クライアント様の社内体制が追い付かず「実施できない」というボトルネックに突き当たることも少なくありません。
コンテンツ制作についても同様です。検索キーワードの候補(サジェスト)を網羅するだけ、といったいわゆる「こたつ記事」は、本当に効果が出なくなりました。実際にクライアント様のサイトを分析しても、そうした記事からの流入がほとんどないケースが大半です。サイト全体の評価を高める効果も、限定的だと感じます。
多くのクライアント様も「月々10万円、20万円を払ってコンテンツを作り続けても、意味があるのだろうか」と気づき始めており、コンテンツ制作の単価は下落傾向にあります。高い価格では売れなくなってきているのです。
では、SEO会社はどこに収益の軸足を移しているのでしょうか。現場で感じる大きな流れは、主に以下の3つです。
一つは、ローカル領域へのシフトです。MEO(Map Engine Optimization)やローカルSEOと呼ばれる分野で、実店舗を持つビジネスにとって重要なGoogleマップでの表示を最適化する施策です。この分野は、残念ながら悪質な業者も多いのが現状ですが、Webサイト本体のSEOだけではカバーしきれないニーズに応える形で、提案を行う会社が増えている印象です。
もう一つは「AI対応」です。まだ日本には本格導入されていませんが、Googleが海外で進めている検索結果へのAI導入を見据え、「AIに最適化されたコンテンツ作り」や「既存サイトの改修」を提案するケースが増えています。将来への投資として、これに応じる企業も多いようです。
次に、人材関連のビジネスです。企業のWeb担当者として専門人材を送り込んだり、フリーランスと企業をマッチングさせたりして、仲介手数料を得るモデルです。これはウェブマーケティング業界全体で数年前から見られる動きですが、SEO会社がこれまで培ってきたブランド力を活かして、この事業を収益の柱に加えるケースが増えています。
うまく軌道に乗れば大きな収益が見込めるため、多くの会社が参入しています。ただし、提供される人材の質は担当者やサービスによって大きく異なるため、注意が必要です。
もう一つの大きな柱が、エデュケーション(教育)関連事業です。これは、同業者である制作会社や広告代理店、あるいは地域の企業を取りまとめる組織などに対して、SEOやコンテンツ制作のツール、あるいはノウハウそのものを販売する、いわば「ツルハシを売る」ビジネスです。
特に海外のツール提供企業は、ツールの使い方だけでなく、そのツールを使いこなすための前提となる考え方や学習コンテンツの提供に非常に力を入れています。対面での個別サポートが苦手な会社でも、ツールや仕組みの販売は比較的行いやすいため、今後AIと絡めてこの分野に注力する会社はさらに増えていくでしょう。
こうした業界の変化を踏まえ、外部のパートナーに依頼する際には、いくつか知っておいていただきたいことがあります。
まず、SEO会社の収益構造がこのように多角化しているという事実を知っておくことが重要です。その上で、自社が本当に依頼したい分野において、その会社がどれほどの専門性や実績を持っているのかを必ず確認しましょう。
例えば、人材紹介を大きな収益源としている会社であれば、テクニカルなSEO施策に関するスキルを持ったスタッフが少ない可能性も考えられます。それは良い悪いではなく、会社としての成り立ちの問題です。自社のニーズと、相手の強みが合致しているかを見極めることが大切です。
ちなみに、私はしばしばSEOの専門会社と見られがちですが、そうではありません。私は、Webの活用に悩む中小企業や小規模事業者の「右腕」となり、戦略立案から実行までを伴走支援することです。
Webサイトをどう改善すればよいか分からない、一度失敗してしまったが次は成功させたい、そういった企業様に寄り添い、社内にノウハウを蓄積しながら、どうしても手が回らない部分の作業を代行しています。その過程で、まずは検索エンジンからのアクセスを確保することが多いため、結果的にSEOに関するお話が多くなる、というのが実情です。
クライアント様側の変化も感じています。「どうすれば順位が上がりますか?」という質問よりも、「どうすればもっと問い合わせが増えますか?」「どうすれば売上が上がりますか?」といった、事業の成果に直結する問いが増えてきました。これは、多くの企業が事業目線でWeb活用を捉えられるようになってきた、非常に良い傾向だと感じています。
一方で、業界全体がGoogleのAI導入(AI Overview)に大きく揺れています。海外ではすでに導入が始まっており、Webサイト運営者やSEO関係者の間では、その影響を巡って賛否両論、まさに議論が絶えない状況です。これが当たり前の未来だと受け入れる人々と、これまでのやり方が通用しなくなることに反発する人々との間で、意見がぶつかり合っています。
本来であれば、メディアが中立的な立場で情報を整理すべきですが、残念ながら現状は、PV(ページビュー)を稼ぎやすい、対立を煽るような話題に偏りがちです。これは、ある意味でコンテンツマーケティングの行き詰まりを示しているのかもしれません。
これからの時代、SEOを単体で考えてはいけません。SEOはあくまで、自社のターゲット顧客に存在を知ってもらうための一つの「手段」でしかありません。
本当に取り組むべきは、自社が何者で、どのような価値を提供できるのかを伝え、顧客との信頼関係を築いていく「ブランド構築」です。それはWebサイトの中だけで完結するものではなく、オフラインの活動も含めた会社全体の取り組みです。その上で、Webという領域でブランド構築を加速させるための一つのパーツとして、SEOが存在します。この主従関係を見誤ると、大きな失敗につながる可能性がありますので、ぜひ気をつけていただきたいです。
こちらのフォームへどうぞ。 https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7
株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)
代表取締役・コンサルタント 中山陽平
Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/
投稿 第564回:SEO業界の「提供価値」と「収益の柱」はどんどん変わっている…? は 中小企業専門WEBマーケティング支援会社・ラウンドナップWebコンサルティング(Roundup Inc.) に最初に表示されました。
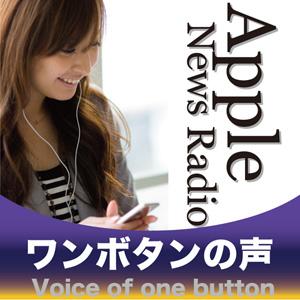
9 Listeners

15 Listeners
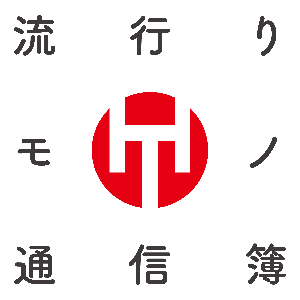
3 Listeners

231 Listeners

3 Listeners

13 Listeners

21 Listeners

42 Listeners

0 Listeners

21 Listeners

5 Listeners

3 Listeners

2 Listeners

2 Listeners

0 Listeners