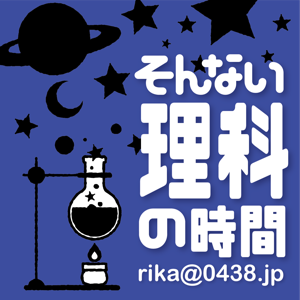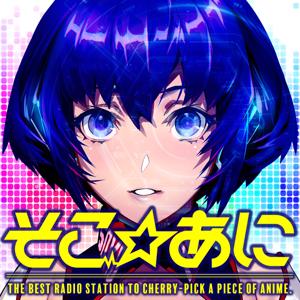「日本でも1980年代から研究が続く太陽光発電衛星、その実現の可能性は?」 太陽光発電といえば、風力発電と並ぶ再生可能エネルギーの双璧です。東日本大震災以降、日本でも太陽光発電の導入が進んできました。2023年4月に国際エネルギー機関が発行した「太陽光発電システム研究協力プログラム報告書」によれば、電力需要に占める太陽光発電の割合が高い国として、日本は10.2%で9位につけています(1位はスペインで19.1%)。また、2022年の国内における太陽光発電の年間導入量は6.5GWで7位でした(1位は中国で106GW)。累積導入量は2022年の時点で84.9GWで、日本は3位と健闘しているのです。しかし、日本はもともと国土が狭く、太陽光発電施設の設置に適した平野部は限られています。太陽光発電の今度の導入に関しては、現在主流の重いシリコン型太陽光パネルのままでは今後の大幅な伸びを期待しにくいとされています。また、経済産業省・資源エネルギー庁によれば、日本では太陽光パネルの費用が海外と比べておよそ1.5倍、工事費もおよそ1.5~2倍と割高であることを示す調査結果もあるといいます。こうした国土や費用の制約もあり、太陽光発電は各家庭、マンション、オフィスビルなどに設置されるような、主要な発電システムとはなっていません。この傾向は日本だけでなく、世界でも同様です。太陽光パネルの設置に適した場所が不足していることに加えて、発電量が天候に左右されやすく、パネルの表面が汚れても発電量が低下しますし、そもそも夜間は発電できないというデメリットなどがその理由です。





 View all episodes
View all episodes


 By 株式会社sorae
By 株式会社sorae