
Sign up to save your podcasts
Or


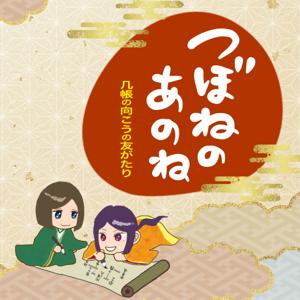

3月といえば異動の季節です。年度末の忙しさに加え、仕事の整理、引き継ぎ、引っ越しの手配とやること満載!それに加えて送別会まで入ってきて…。
そんな忙しさを1100年前のあの人も経験していました。それは、紀貫之。赴任先である土佐(今の高知県)から都へ帰る時の様子を土佐日記に記しているのですが、その最初のほうはもうじれったくってたまらない。行くと言いながら行かない。さあ出発!と言いつつ、まだ行かない。それは延々と送別会を繰り返していたから!!!
紀貫之が経験した送別会とはどんなものだったのでしょうか?あの人、この人、こんな人が紀貫之を送ります。その様子は令和を生きるおぎたまにも耳の痛い話です・・・。
<時のしおり>
(00:00) 三月、それは異動の季節
(03:28) 土佐に異動した平安人・紀貫之
(05:12) なぜ女性のふりで日記を書くの?
(09:37) 土佐日記は“出自がはっきりしてる”作品
(13:13) 進まぬ旅路、その原因は…
(15:40) 元・都人主催!お土産満載送別会
(20:34) 送別の和歌と酒
(23:15) あやなし!格式張った送別会
(27:46) 貫之は部下に慕われていた説
(33:24) 送別会は人物評価の総決算!
(37:58) 紀貫之はどんな人だったのか
<おぎ注>
土佐日記:紀貫之が書いた紀行文。当時、男性の書く日記といえば外国語である漢文で書くのが主流だった時に、母国語である日本語で書いた。赴任先の土佐から都へ帰る紀貫之に同行している女房の立場で記している。「男もすなる日記といふものを女もしてみむとてするなり」という冒頭部部分は、「する」の活用と「なり」の用法について説明するのに最も適した教材です。
紀貫之(きのつらゆき):藤原道長の90年ほど前に生まれた。古今和歌集の編者の一人で、土佐日記の筆者でもある。
小右記(しょうゆうき):藤原実資が63年間にわたって記した業務日誌。宮中の行事や儀式などを正確に伝えており、1000年経った今でも超一級の資料。
倉本一宏先生:国際日本文化研究センター教授。小右記全巻を現代語に翻訳するという偉業を成し遂げた方。「光る君へ」で時代考証を担当なさっており、ここ最近たくさん著書を出版なさっている。
藤原為家(ふじわらのためいえ):藤原定家の息子。紀貫之が土佐日記を書いたおよそ300年後にその自筆本を正確に写した。多くの写本が残り、どれが原本なのかわからないという古典文学作品の中で、最も出自のはっきりした写本を残すという奇跡を成し遂げた人物。勝手に書き換える父・定家とは大違い。
※おぎがわかりやすく説明しているだけなので、テストに書いてもマルはもらえませんのでご注意ください!
<今回ご紹介した和歌>
元都人の女性より:
浅茅生(あさじふ)の野辺にしあれば水もなき池に摘みつる若菜なりけり
(おぎ訳:お正月に食べる若菜をどうぞ。ここ、土佐の池で採りましたよ)
紀貫之より:
行く先に立つ白波の声よりも遅れて泣かむ我や勝らむ
(おぎ訳:これでお別れですね。涙が出ます)
<参考文献>
土佐日記 新日本古典文学大系 岩波書店
※自由気ままな古典愛トークですので、学術的・歴史的に正しいものとは限りません。
※内容は諸説あります。
X(旧Twitter) → https://x.com/TUBONEnoANONE
ご質問などはこちらへ → https://marshmallow-qa.com/tubonenoanone
HP、更新中 →おぎたまの局 https://www.tibonenoanone.com
https://line.me/S/sticker/25960481
 View all episodes
View all episodes


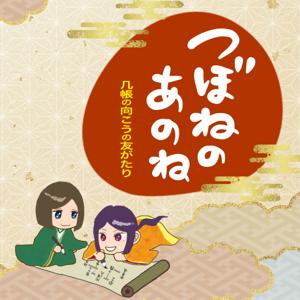 By おぎたま
By おぎたま
3月といえば異動の季節です。年度末の忙しさに加え、仕事の整理、引き継ぎ、引っ越しの手配とやること満載!それに加えて送別会まで入ってきて…。
そんな忙しさを1100年前のあの人も経験していました。それは、紀貫之。赴任先である土佐(今の高知県)から都へ帰る時の様子を土佐日記に記しているのですが、その最初のほうはもうじれったくってたまらない。行くと言いながら行かない。さあ出発!と言いつつ、まだ行かない。それは延々と送別会を繰り返していたから!!!
紀貫之が経験した送別会とはどんなものだったのでしょうか?あの人、この人、こんな人が紀貫之を送ります。その様子は令和を生きるおぎたまにも耳の痛い話です・・・。
<時のしおり>
(00:00) 三月、それは異動の季節
(03:28) 土佐に異動した平安人・紀貫之
(05:12) なぜ女性のふりで日記を書くの?
(09:37) 土佐日記は“出自がはっきりしてる”作品
(13:13) 進まぬ旅路、その原因は…
(15:40) 元・都人主催!お土産満載送別会
(20:34) 送別の和歌と酒
(23:15) あやなし!格式張った送別会
(27:46) 貫之は部下に慕われていた説
(33:24) 送別会は人物評価の総決算!
(37:58) 紀貫之はどんな人だったのか
<おぎ注>
土佐日記:紀貫之が書いた紀行文。当時、男性の書く日記といえば外国語である漢文で書くのが主流だった時に、母国語である日本語で書いた。赴任先の土佐から都へ帰る紀貫之に同行している女房の立場で記している。「男もすなる日記といふものを女もしてみむとてするなり」という冒頭部部分は、「する」の活用と「なり」の用法について説明するのに最も適した教材です。
紀貫之(きのつらゆき):藤原道長の90年ほど前に生まれた。古今和歌集の編者の一人で、土佐日記の筆者でもある。
小右記(しょうゆうき):藤原実資が63年間にわたって記した業務日誌。宮中の行事や儀式などを正確に伝えており、1000年経った今でも超一級の資料。
倉本一宏先生:国際日本文化研究センター教授。小右記全巻を現代語に翻訳するという偉業を成し遂げた方。「光る君へ」で時代考証を担当なさっており、ここ最近たくさん著書を出版なさっている。
藤原為家(ふじわらのためいえ):藤原定家の息子。紀貫之が土佐日記を書いたおよそ300年後にその自筆本を正確に写した。多くの写本が残り、どれが原本なのかわからないという古典文学作品の中で、最も出自のはっきりした写本を残すという奇跡を成し遂げた人物。勝手に書き換える父・定家とは大違い。
※おぎがわかりやすく説明しているだけなので、テストに書いてもマルはもらえませんのでご注意ください!
<今回ご紹介した和歌>
元都人の女性より:
浅茅生(あさじふ)の野辺にしあれば水もなき池に摘みつる若菜なりけり
(おぎ訳:お正月に食べる若菜をどうぞ。ここ、土佐の池で採りましたよ)
紀貫之より:
行く先に立つ白波の声よりも遅れて泣かむ我や勝らむ
(おぎ訳:これでお別れですね。涙が出ます)
<参考文献>
土佐日記 新日本古典文学大系 岩波書店
※自由気ままな古典愛トークですので、学術的・歴史的に正しいものとは限りません。
※内容は諸説あります。
X(旧Twitter) → https://x.com/TUBONEnoANONE
ご質問などはこちらへ → https://marshmallow-qa.com/tubonenoanone
HP、更新中 →おぎたまの局 https://www.tibonenoanone.com
https://line.me/S/sticker/25960481

15 Listeners

10 Listeners

8 Listeners
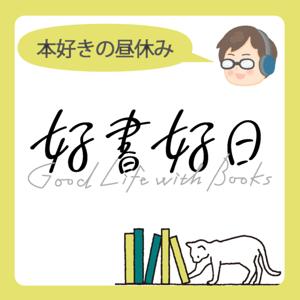
2 Listeners

7 Listeners

2 Listeners

37 Listeners

20 Listeners

4 Listeners

2 Listeners

35 Listeners
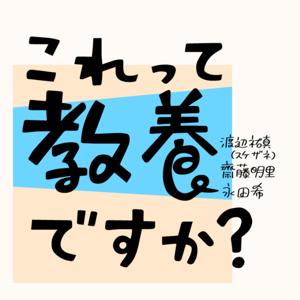
1 Listeners

0 Listeners

4 Listeners

17 Listeners