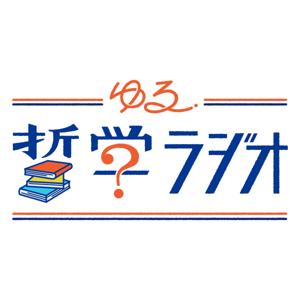夏と言えば「お化け」。日本の風土は、夏に蒸し暑く、寝苦しいこともあり、昔から、お化けは夏によく出る。
お化けにもいろいろあるが、日本では大きく妖怪と幽霊に分けられる。妖怪とは、様々な場所で起こる不可思議な現象に与えられた名前のことであり、幽霊とは、恨みを抱いた死者の怨念のことだろう。どちらも科学的・物理的には実在しない。にもかかわらず、お化けは実在してしまう。
ゲゲゲの鬼太郎と握手はできないが、不可思議現象は前近代に限らず今でも起こる。死んだ人間が物理的に活動するはずはないが、「恨みを抱いて死んだ人間」はいる。「人を呪わば穴二つ」と言い、切腹、特攻、自死による他者攻撃といった呪術にすがる衝動が、日本人の精神にはしばしば宿る。怪異や怨念は、人間にとっての現実である意識の世界で、どうしようもなく実在してしまう。
東洋大学の創設者、井上円了は、明治を代表する哲学者であり教育者だった。しかし、彼の名前は哲学よりも、妖怪研究のパイオニアとして知られている。
哲学による日本の近代化を目指した円了は、無知蒙昧な迷信から人々を解放するため、古今の妖怪に関する文献を渉猟し、全国各地の怪異譚を取材して、様々な不可思議現象について、物理学・医学・心理学上の知見から合理的に真相を究明していった。妖怪についての膨大な知識と、探偵さながら怪異を暴くその様より、「不思議博士」「妖怪博士」と呼ばれた。
『妖怪学』は、彼が妖怪と呼ぶ様々な怪異現象の紹介と、それに対する科学的解釈、迷信批判を展開した論文である。例えば、「こっくりさん」という現象が起こる物理的・生理的・心理的原因を解明し、その起源が古いものではなく、明治期にアメリカ人が伝えたテーブル・ターニングという占いであることも暴いてしまう。
妖怪を、科学的に未解明な現象である「真怪」、自然現象によって実際に発生する「仮怪」、誤認や恐怖感などの心理的要因が生む「誤怪」、人が人為的に引き起こす「偽怪」に分類し、俗信の打破を目指した円了だが、妖怪を否認したわけではない。妖怪とは「心これなり」とし、宗教信仰を奨励して霊魂の不滅を説いてもいる。
自分が害した死者の悪夢にうなされる者へ、「幽霊なんて非科学的だから気にするな」と言ってあげたところで意味はない。そんなことは元より分かっているのだ。科学的に実在しないものは、科学の力では消せようがない。だから、怖い。だから人は、鎮魂の儀式を必要とする。死者の魂を鎮めることで、生者の心を鎮めるために。
妖怪はその後、柳田國男ら民俗学者によって、体系的な研究の対象となる。