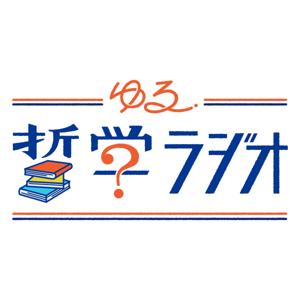駅を通過中の列車の中でAさんが、プラットホームでBさんが、同時にボールを下に落とす。床までの距離はどちらも1m。AさんもBさんも、自分のボールは真下へ向かっているように見える。しかし、列車の速度で進むAさんのボールを静止しているホームのBさんが見ると、電車の進行方向斜め下向きに進んでいる。三平方の定理により、≪電車の進行距離≫²+≪Aさんの手から床までの距離≫²=≪Aさんのボールが移動する斜め下向きの距離≫²。Aさんのボールの移動距離は明らかにBさんのボールの移動距離より長い。でも、落ちるのは同時。なぜなら、時間=距離÷速さ。Aさんのボールは、落下速度に列車の速度を加えた速さで進むので、進行距離も長くなるが速度も大きい。ボールが床に到達するのに1秒かかるとして、電車の速さが秒速10mならAさんのボールが床につくまでの横向きの移動距離は10m。ならば、斜め下向きの移動距離は10²+1²の平方根だから√101m。この時、横向きの速さと下向きの速さの合計も、秒速10m²+秒速1m²の平方根だから、秒速√101m。床に到達するまでの時間は、距離√101m÷速さ√101m=1秒となり、Bさんのボールが落ちる時間と等しくなる。
次に、宇宙ステーションを光速に近い速さで通過する宇宙船内でAさんが、宇宙ステーションでBさんが、同時に天井から真下の床へ同じ距離だけライトで光線を落とす。すると今度は、Bさんの光線が床に到達した時、Aさんの光線はまだ床に届いていない。なぜか。光速は秒速30万km弱。これを秒速Ckmとして、Aさんの宇宙船が秒速Vkmで進むとしたら、Aさんの光線が、Aさんの時計で、T秒後に床へ落ちた時、横向きにはVkm × T秒、移動していることになる。すると、三平方の定理から、斜め下向きには≪宇宙船の移動距離VT≫²+≪Aさんの光線が真下の床へ着いた距離CT≫²の平方根だけ移動していることになるはず。でも、その速さはどんなに速くても秒速30万kmより速くなることが宇宙では不可能だ。つまり、距離は伸びても速さは伸びないので秒速Ckmに宇宙船の速さ秒速Vkmを加えられない。よって、≪Aさんの光線が移動した距離≫÷≪光線だけの速さ≫ が、Aさんの光線が床へ到達するまでにかかる時間となり、これではBさんの光線が床へ到達する時間より長くなってしまう。
ここで、宇宙船で移動するAさんの時間をTa、停止しているBさんの時間をTbと、分けて三平方の法則で式にしてみる。すると、≪Bさんから見た宇宙船の移動した距離≫²+≪Aさんから見た光線が真下の床へ着いた距離≫²=≪Bさんから見たAさんの光線が移動した斜め下向きの距離≫²は、(VTb)²+(CTa)²= (CTb)² となる。この式を変形すると、Ta=√(1-V²/C²)×Tb と表せるが、これは、宇宙船の速度Vが大きくなればなるほど、Aさんの時間Taが、Bさんの時間Tbより小さくなる、即ち遅くなることを示している。
1905年、スイスの特許局に勤めていたドイツ生まれのユダヤ人アインシュタインは、博士号取得のために提出した「特殊相対性理論」についての論文により、人類の世界観に変革をもたらすことになった。
ニュートン力学は、宇宙に絶対的な時間と空間があることを前提に構築されていたが、電磁気学におけるマクスウェル方程式の発明と、光の不思議な性質の発見で、この前提は覆る。赤道上、地球の自転速度は時速1700km。太陽からの光は、太陽へ向かう位置の方が、太陽から遠ざかる位置より、速くなるはず。しかし、その差は測定されない。この事実から導かれる「光速度不変の原理」を基に、アインシュタインは科学的事実として、つまり、数式による事象の言明として、絶対的な時空間を否定した。代わりに、光の速さが絶対的な尺度の王座へ就くことになる。
慣性系の速度の違いにより、時間は伸びて空間は縮む。更に、光速に近づく物質の質量は、急速に増大して加速を抑え、秒速30万kmに達することがないよう、ブレーキがかかる。質量の増大はエネルギーの増大となる。E=mc²。これも、アインシュタインが導いた結論の一つ。
1916年、重力が質量による時空間の歪みであることを示すアインシュタイン方程式の完成とともに、「一般相対性理論」が発表される。不動の時空間は存在しない。時空間は、歪み、捩れ、消え去りもするものだった。
これが、数式の描く宇宙の実在。