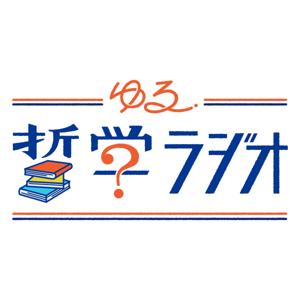1915年、漢民族系台湾人による最後の武装抵抗だった「西来庵事件」が鎮圧された頃、世界では、辛亥革命、ロシア革命、アメリカのウィルソン大統領による民族自決の提唱、朝鮮の三・一運動など、民主化と反植民地主義の風が吹いていた。
日本でも大正デモクラシーと呼ばれる民主主義・自由主義の運動が国民的に広がり、1918年には立憲政友会の原敬が初の本格政党内閣を成立させた。原は台湾の人事においても、武官総督を文官総督に代え、田健次郎を任命する。この原首相と田総督が台湾統治に対して採った方針は内地延長主義だった。台湾では「六三法」という時限立法により、日本本土の法律と異なる台湾総督の律令によって統治されていたが、新たな法律「法三号」により総督の律令制定権は制限され、台湾にも本土の法律が施行されることになった。だがそれは、台湾を日本へ完全に同化させようとすることでもあった。
これに先んじて台湾では1914年に明治の元勲板垣退助を引き込んで、林献堂たちが台湾同化会を結成し、台湾人の日本への同化を訴えた。だが、日本人と同等の権利獲得を目指す主張が、反統治主義的だと総督府に危険視され、結成から1ヶ月で解散に追い込まれた。
その後、林献堂は日本に渡り、東京で留学中の蔡培火らと「六三法」の撤廃を目指す啓発会を設立し、更にこの会を発展的に解消して、林呈禄らと新民会を設立した。この間、献堂たちは「六三法」撤廃と日本人への同化を求める立場から、内地延長主義を植民地主義だと批判する立場に変化、台湾の独自性を訴えて自治権獲得を目指す台湾議会設置請願運動を開始し、機関誌である「台湾青年」で主張を展開していった。この運動は日本の学者や政治家からも多くの支援を得たが、台湾では政治活動が許されなかったため、蔣渭水らが台湾文化協会を設立し、文化振興を建前とした活動を広めていった。
台湾内で結社を禁じられた台湾議会期成同盟会だが、東京では内務大臣の認可を得、議会設置の請願を行うことができた。その会員が台湾に戻った時、事件が起こる。東京で活動した会の会員が、先に台湾で禁止した会の会員と同一であったため、治安警察法違反容疑で18名が拘留、起訴された。裁判では貴族院議員の渡辺暢や衆議院議員の清瀬一郎が弁護人となり、一審では全員無罪となったが、二審と三審で有罪判決を受け13名が入獄した。
やがて世界的な社会主義の伸長が台湾にも影響し、運動は左右に分裂、日中戦争の開始と共に終息した。だが、一連の政治運動は、台湾人の心に政治的近代化と台湾人アイデンティティをもたらした。その歴史的意義は、この後この島に訪れる悲劇によって顕現することになる。