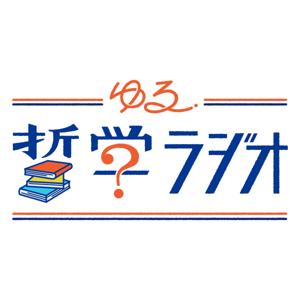霊長類である人間は、生きるために群れをなします。そして外部からの攻撃や危険からその集団を守ろうとして団結し、その結束に傷がつくことを恐れます。傷をつける言動をする者がいれば、「空気を読め」と同調を求めます。それは、群れの中で群れに結びつけられた個々の神経のごく自然な反応であり、学校も会社も隣近所も、そうした神経の同調作用で平穏が保たれています。
しかし、このような集団が合議を行う時は、「複数の人が集まっているから問題は解決しやすくなる」というよりも、「同意したい、対立を避けたいという欲求のために、話はなかなか進まない」可能性が強くなります。場合によっては、決定的に不合理で危険な意思決定が容認されてしまうこともあります。こうした現象を集団思考、あるいは集団浅慮といいます。
1959年、革命によってカストロ政権が誕生したキューバは、旧政権を支援していたアメリカと対立します。その後、キューバと国交を断絶したアメリカでは1961年にケネディが大統領に就任し、前任のアイゼンハワー大統領時代からCIAが進めていたキューバ侵攻計画を承認します。
こうしてキューバからの亡命者で編成された1400人の部隊がCIAによる軍事訓練を受けて、カストロ打倒を目指してキューバ南部のピッグズ湾に侵攻します。しかし、アメリカの政権交代を跨いで進められたこの計画は、CIAの強い自信に反して形式に堕した杜撰で滑稽なもので、これにアメリカ軍の直接介入を禁じたケネディの命令なども加わって作戦は失敗、待ち構えていた20万のキューバ軍を前に兵士たちは無残に虐殺されました。更にこの事件を機にキューバはソ連に急速接近し、その核ミサイルを持ち込もうとするキューバ危機が発生して、人類は危うく核戦争に巻き込まれかけたのでした。
大統領とその顧問、CIAと軍、みな優秀な人々で多くの情報も持っていながら、発足直後の政権内での対立を避けて作戦の検証を怠り、非常に愚かな結果を招いたこの事件を、心理学者アーヴィング・ジャニスは集団思考の典型的な例として提示しました。他にも、真珠湾攻撃、朝鮮戦争、ベトナム戦争、ウォーターゲート事件など、いくつかのアメリカ政権の誤断が集団思考の例として挙げられています。
集団思考は、①集団の成員同士の仲がよく、②その集団が孤立していて、③重要な決断を下す期限が決まっている時、起こりやすいようです。集団の合意を合理化し、会議の場では誰も反対していなかったのに、後で個別に話してみるとみんな「うまくいかないと思っていたよ」と言ったりする。しばしばあることです。