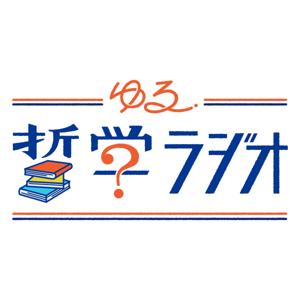農業革命は、サピエンスに繁栄と進歩をもたらした大きな一歩だという考えがある一方で、地獄のような苦痛との戦いをもたらしたという考えもあります。
確かに、スマートフォン一つで様々なサービスを享受できる今の私達にとっては、現代文明を築くために不可欠な革命だったと言えます。しかし、近代以前の人類の歴史において人口の9割以上を占めていた農民の長く過酷な日々を思う時、広大なエリアを住み処としていた狩猟採集生活より、地球上極端に限定された猫の額のような農耕地に寄り集まって、人口の1割に満たない上層階級に身をすり減らして生産物を貢納し続ける日々が幸福だったとは、簡単には言えないでしょう。
それでも、ひとたび農耕生活に入った人類は決して後戻りすることなく、地上のわずか2%の土地に家を作り、村を作り、町を作り、国を作り、広大な未開地に囲まれたそんな人工の島から抜け出せない生き物になっていくのでした。
ところで、人工の島で生きるようになったサピエンスの社会には、偉大な発明とも言える二つの虚構が発達していきます。その一つは時間です。もちろん、狩猟採集生活においても物語を共有する人類には、過去・現在・未来の意識はありました。でも、必要な食物だけを日々入手していた狩猟採集と異なり、農耕生活は季節に応じて作業を進めていく必要がありますし、旱魃や洪水などの脅威に備えて食料を貯蔵しておく必要もあります。何日も先、何年も先の、未来に対する不安を語り合い、対処していくことで、概念世界に時間が拡大していき、暦や時間に追われる人類の性質が生まれてきたのでした。
人工の島で発達したもう一つの虚構は秩序、または、正義・倫理・道徳と呼ばれるものです。狩猟採集民も数十人から数百人の人々が、語り合いを通して秩序を共有していましたが、農耕とともに生まれてきたエジプト、アッカド、アッシリア、バビロニア、ペルシア、秦朝、ローマなど諸帝国では、何十万~何百万もの臣民を支配し、何万もの兵士や役人を抱えていたため、より強力な秩序が必要でした。アリやハチの群れのように遺伝子レベルで秩序立った行動ができるわけではない人類は、容易に悲劇的な対立に陥ります。それを防ぐ働きを果たすのが、神話の共有です。
古代のハンムラビ法典が説く身分制と「目には目を」の原理も、近代のアメリカ独立宣言が説く自由・平等の人権も、人々が共有する神話に基づいた共同主観的想像上の秩序であることに変わりはありません。ハンムラビ法典は、ハンムラビ王ではなくエンリル神やマルドゥク神が定めたもの、自由と平等の人権は、トマス・ジェファソンではなく創造主に約束されたもの、あるいは市場原理は、アダム・スミスではなく自然法則なる神の見えざる手が決めたもの、そう人々が信じることでそれぞれの社会の秩序は守られます。更にこの秩序が、王宮や聖剣や宝冠、国会議事堂やバリアフリーの公共バスやナイキのスニーカーなど、建物・道具・装飾具といった人工物の形を定め、それらを求める私達の欲望を作るため、人々からの一層の支持と信仰を得ることができるのです。