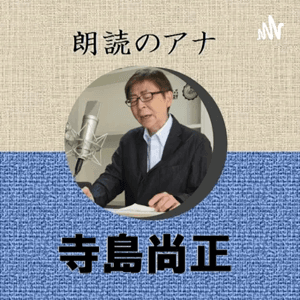十日の月が西の煉瓦塀れんぐわべいにかくれるまで、もう一時間しかありませんでした。
その青じろい月の明りを浴びて、獅子ししは檻をりのなかをのそのそあるいて居をりましたが、ほかのけだものどもは、頭をまげて前あしにのせたり、横にごろっとねころんだりしづかに睡ねむってゐました。夜中まで檻の中をうろうろうろうろしてゐた狐きつねさへ、をかしな顔をしてねむってゐるやうでした。
わたくしは獅子の檻のところに戻って来て前のベンチにこしかけました。
するとそこらがぼうっとけむりのやうになってわたくしもそのけむりだか月のあかりだかわからなくなってしまひました。
いつのまにか獅子が立派な黒いフロックコートを着て、肩を張って立って
「もうよからうな。」と云いひました。
すると奥さんの獅子が太い金頭のステッキを恭しく渡しました。獅子はだまって受けとって脇わきにはさんでのそりのそりとこんどは自分が見まはりに出ました。そこらは水のころころ流れる夜の野原です。
ひのき林のへりで獅子は立ちどまりました。向ふから白いものが大へん急いでこっちへ走って来るのです。
獅子はめがねを直してきっとそれを見なほしました。それは白熊しろくまでした。非常にあわててやって来ます。獅子が頭を一つ振って道にステッキをつき出して云ひました。
「どうしたのだ。ひどく急いでゐるではないか。」
白熊がびっくりして立ちどまりました。その月に向いた方のからだはぼうっと燐りんのやうに黄いろにまた青じろくひかりました。
「はい。大王さまでございますか。結構なお晩でございます。」
「どこへ行くのだ。」
「少し尋ねる者がございまして。」
「誰たれだ。」
「向ふの名前をつい忘れまして、」
「どんなやつだ。」
「灰色のざらざらした者ではございますが、眼めは小さくていつも笑ってゐるやう。頭には聖人のやうな立派な瘤こぶが三つございます。」
「ははあ、その代り少しからだが大き過ぎるのだらう。」
「はい。しかしごくおとなしうございます。」
「所がそいつの鼻ときたらひどいもんだ。全体何の罰であんなに延びたんだらう。おまけにさきをくるっと曲げると、まるでおれのステッキの柄のやうになる。」
「はい。それは全く仰おほせの通りでございます。耳や足さきなんかはがさがさして少し汚なうございます。」
「さうだ。汚いとも。耳はボロボロの麻のはんけち或あるいは焼いたするめのやうだ。足さきなどはことに見られたものでない。まるで乾いた牛の糞くそだ。」
「いや、さう仰おっしゃってはあんまりでございます。それでお名前を何と云はれましたでございませうか。」
「象だ。」
「いまはどちらにおいででございませうか。」
「俺おれは象の弟子でもなければ貴様の小使ひでもないぞ。」
「はい、失礼をいたしました。それではこれでご免を蒙かうむります。」
「行け行け。」白熊しろくまは頭を掻かきながら一生懸命向ふへ走って行きました。象はいまごろどこかで赤い蛇じゃの目の傘かさをひろげてゐる筈はずだがとわたくしは思ひました。
ところが獅子ししは白熊のあとをじっと見送って呟つぶやきました。
「白熊め、象の弟子にならうといふんだな。頭の上の方がひらたくていゝ弟子になるだらうよ。」そして又のそのそと歩き出しました。
月の青いけむりのなかに樹きのかげがたくさん棒のやうになって落ちました。
そのまっくろな林のなかから狐きつねが赤縞あかじまの運動ズボンをはいて飛び出して来ていきなり獅子の前をかけぬけようとしました。獅子は叫びました。
「待て。」
狐は電気をかけられたやうにブルルッとふるへてからだ中から赤や青の火花をそこら中へぱちぱち散らしてはげしく五六遍まはってとまりました。なぜか口が横の方に引きつってゐて意地悪さうに見えます。
獅子が落ちついてうで組みをして云ひました。
「きさまはまだ悪いことをやめないな。この前首すぢの毛をみんな抜かれたのをもう忘れたのか。」
狐がガタガタ顫ふるへながら云ひました。
「だ、大王様。わ、わたくしは、い今はもうしゃう正直でございます。」歯がカチカチ云ふたびに青い火花はそこらへちらばりました。
「火花を出すな。銅臭くていかん。こら。偽うそをつくなよ。今どこへ行くつもりだったのだ。」
狐は少し落ちつきました。
「マラソンの練習でございます。」
「ほんたうだらうな。鶏を盗みに行く所ではなからうな。」
「いえ。たしかにマラソンの方でございます。」
獅子は叫びました。
「それは偽うそだ。それに第一おまへらにマラソンなどは要らん。そんなことをしてゐるからいつまでも立派にならんのだ。いま何を仕事にしてゐる。」
「百姓でございます。それからマラソンの方と両方でございます。」
「偽だ。百姓なら何を作ってゐる。」
「粟あはと稗ひゑ、粟と稗でございます。それから大豆まめでございます。それからキャべヂでございます。」
「お前は粟を食べるのか。」
「それはたべません」
「何にするのだ。」
「鶏にやります。」
「鶏が粟をほしいと云ふのか。」
「それはよくさう申します。」
「偽だ。お前は偽ばっかり云ってゐる。おれの方にはあちこちからたくさん訴が来てゐる。今日はお前のせなかの毛をみんなむしらせるからさう思へ。」
狐きつねはすっかりしょげて首を垂れてしまひました。
「これで改心しなければこの次は一ぺんに引き裂いてしまふぞ。ガアッ。」
獅子ししは大きく口を開いて一つどなりました。
狐はすっかりきもがつぶれてしまってたゞ呆あきれたやうに獅子の咽喉のどの鈴の桃いろに光るのを見てゐます。
その時林のへりの藪やぶがカサカサ云ひました。獅子がむっと口を閉ぢてまた云ひました。
「誰たれだ。そこに居るのは。こゝへ出て来い。」
藪の中はしんとしてしまひました。
獅子はしばらく鼻をひくひくさせて又云ひました。
「狸たぬき、狸。こら。かくれてもだめだぞ。出ろ。陰険なやつだ。」
狸が藪からこそこそ這はひ出して黙って獅子の前に立ちました。
「こら狸。お前は立ち聴きをしてゐたな。」
狸は目をこすって答へました。
「さうかな。」
そこで獅子は怒ってしまひました。
「さうかなだって。ずるめ、貴様はいつでもさうだ。はりつけにするぞ。はりつけにしてしまふぞ。」
狸はやはり目をこすりながら
「さうかな。」と云ってゐます。狐はきょろきょろその顔を盗み見ました。獅子も少し呆れて云ひました。
「殺されてもいゝのか。呑気のんきなやつだ。お前は今立ち聴きしてゐたらう。」
「いゝや、おらは寝てゐた。」
「寝てゐたって。最初から寝てゐたのか。」
「寝てゐた。そして俄にはかに耳もとでガアッと云ふ声がするからびっくりして眼を醒さましたのだ。」
「あゝさうか。よく判わかった。お前は無罪だ。あとでご馳走ちそうに呼んでやらう。」
狐きつねが口を出しました。
「大王。こいつは偽うそつきです。立ち聴きをしてゐたのです。寝てゐたなんてうそです。ご馳走なんてとんでもありません。」
狸たぬきがやっきとなって腹鼓を叩たたいて狐を責めました。
「何だい。人を中傷するのか。お前はいつでもさうだ。」
すると狐もいよいよ本気です。
「中傷といふのはな。ありもしないことで人を悪く云ふことだ。お前が立ち聴きをしてゐたのだからそのとほり正直にいふのは中傷ではない。裁判といふもんだ。」
獅子ししが一寸ちょっとステッキをつき出して云ひました。
「こら、裁判といふのはいかん。裁判といふのはもっとえらい人がするのだ。」
狐が云ひました。
「間違ひました。裁判ではありません。評判です。」
獅子がまるであからんだ栗くりのいがの様な顔をして笑ひころげました。
「アッハッハ。評判では何にもならない。アッハッハ。お前たちにも呆あきれてしまふ。アッハッハ。」
それからやっと笑ふのをやめて云ひました。
「よしよし。狸は許してやらう。行け。」
「さうかな。ではさよなら。」と狸は又藪やぶの中に這はひ込みました。カサカサカサカサ音がだんだん遠くなります。何でも余程遠くの方まで行くらしいのです。
獅子はそれをきっと見送って云ひました。
「狐。どうだ。これからは改心するか、どうだ。改心するなら今度だけ許してやらう。」
「へいへい。それはもう改心でも何でもきっといたします。」
「改心でも何でもだと。どんなことだ。」
「へいへい。その改心やなんか、いろいろいゝことをみんなしますので。」
「あゝやっぱりお前はまだだめだ。困ったやつだ。仕方ない、今度は罰しなければならない。」
「大王様。改心だけをやります。」
「いやいや。朝までこゝに居ろ。夜あけ迄までに毛をむしる係りをよこすから。もし逃げたら承知せんぞ。」
「今月の毛をむしる係りはどなたでございますか。」
「猿さるだ。」
「猿。へい。どうかご免をねがひます。あいつは私とはこの間から仲が悪いのでどんなひどいことをするか知れません。」
「なぜ仲が悪いのだ。おまへは何か欺だましたらう。」
「いゝえ。さうではありません。」
「そんならどうしたのだ。」
「猿が私の仕掛けた草わなをこはしましたので。」
「さうか。そのわなは何をとる為ためだ。」
「鶏です。」