
Sign up to save your podcasts
Or




 View all episodes
View all episodes


 By TOKYO FM
By TOKYO FM




5
55 ratings


43 Listeners

170 Listeners
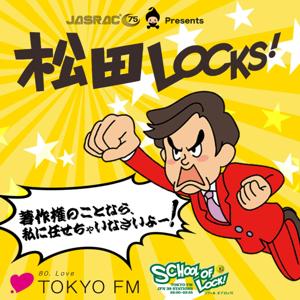
0 Listeners

175 Listeners

237 Listeners

8 Listeners

102 Listeners

21 Listeners
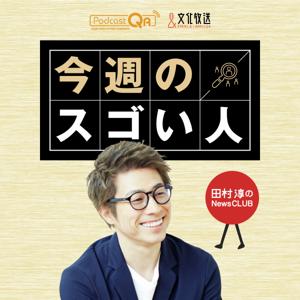
9 Listeners

41 Listeners

40 Listeners

14 Listeners
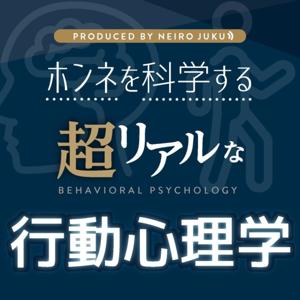
20 Listeners

164 Listeners

6 Listeners

1 Listeners

0 Listeners
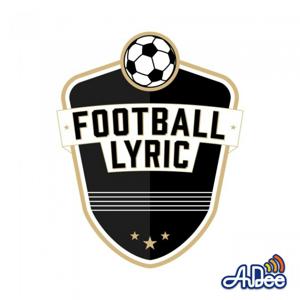
0 Listeners

0 Listeners

0 Listeners
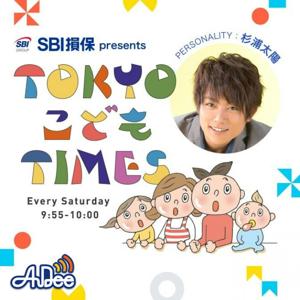
0 Listeners

0 Listeners
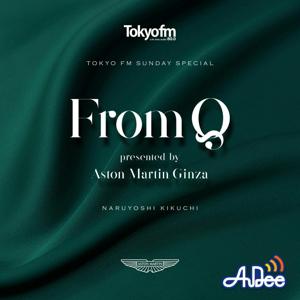
0 Listeners
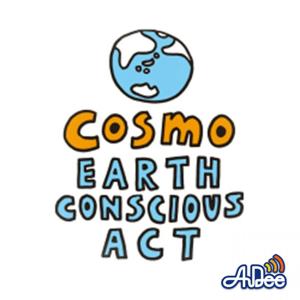
0 Listeners

0 Listeners
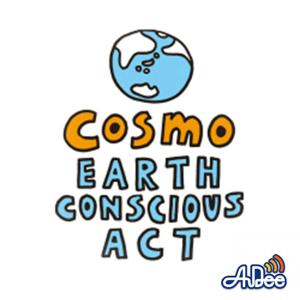
0 Listeners
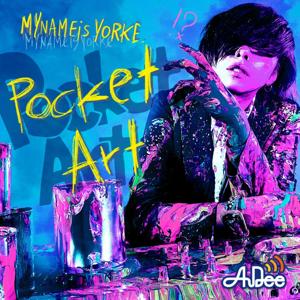
0 Listeners

0 Listeners

0 Listeners

17 Listeners

0 Listeners