
Sign up to save your podcasts
Or


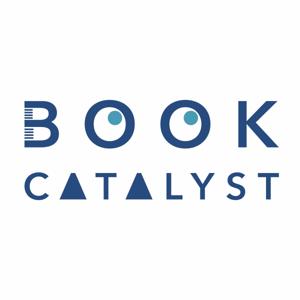

今回は、倉下が『哲学史入門Ⅳ』を紹介しました。
一般向けの哲学紹介本の中でも、本書は一味違った楽しさがあります。
書誌情報
* 出版社
* NHK出版(NHK出版新書)
* 発売日
* 2025/9/10
* 編者
* 斎藤哲也
* 人文ライター。1971年生。東京大学文学部哲学科卒業。著書『試験に出る哲学』シリーズ、『哲学史入門』シリーズ(NHK出版新書)、監修に『哲学用語図鑑』(プレジデント社)など。
* 目次
* 序章 倫理学に入門するとは何をすることなのか(古田徹也)
* 第1章 現代に生きる功利主義―誰もが幸福な社会を目指して(児玉聡)
* 第2章 義務論から正義論へ―カントからロールズ、ヌスバウムまで(神島裕子)
* 第3章 徳倫理学の復興―善い生き方をいかに実現するか(立花幸司)
* 第4章 なぜケアの倫理が必要なのか―「土台」を問い直すダイナミックな思想(岡野八代)
* 特別章 「地べた」から倫理を考える(ブレイディみかこ)
構成は、編者による解説+研究者へのインタビューで、両方読むとよくわかるようになっていますが、インタビューだけを読んでも楽しめると思います。ざっくばらんな雰囲気と、論文などではあまり見えてこないそれぞれの研究者の「人間くささ」が伝わってきます。そして、本シリーズを通して読むと、哲学というのは「人間の営みなのだ」ということがよくわかります。
でもって、このⅣはまさにその「人間」に焦点を当てています。
倫理学の必要性
現代ほど倫理学の視点が大切な時代はないでしょう、と書くといささか大げさめいていますが、それでも科学の発達で「人間の拡張」の可能性が開かれたり、LLMの登場で「人間知性の拡張」が現実味を帯びてきた中で、「そもそも人間とは何か、人間として生きるとはどういうことか」を問うことは欠かせないように思います。
また、インターネットとスマートフォンの普及によって、これまでになかった規模や範囲で人と人の交流が生まれるようになっています。人間(じんかん)を捉える視点が、これまで長く続いてきた社会とは大きく異なりはじめているわけです。目の前に顔が現れ、文脈を共有し、共感が働きやすい共同体とは違った関係において、その関係を維持したり、よいものにしたりする能力を磨くことも必要でしょう(少なくとも生得的な能力としては持っていなさそうです)。
加えて言えば、現代では市場原理があまりにも強くなり過ぎています。あたかも「原理」がそれしかないかのように扱われています。しかし、アダム・スミスが道徳を論じたように、市場に参加する人の感情的能力があってこそ成り立つものがあるはずです。それを無視して、システム=メカニズムを整備すればうまくいくという考え方は、あまりにも見過ごしてしているものが多いと感じられます。
そのような単一の原理の一強体制は、市場だけに限りません。本編でも触れたように「正義」の原理だけが重視され、ケアの倫理が無視されてきた歴史も同様でしょう。もちろん、それぞれの時代においての最善はなされてきたのだと思います。だからといって、それをこだまのように繰り返せばいいとは言えません。「解釈と批判」を続け、その時代に必要な新しい視点を確立していく必要があります。
というよりも、そのような営みをずっと続けてきたのが「人間」なのかもしれません。だとすれば、「人間」の終焉がありえるとしたら、そのような営みが閉じられるタイミングなのでしょう。
 View all episodes
View all episodes


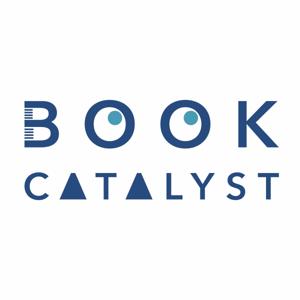 By goryugo
By goryugo
今回は、倉下が『哲学史入門Ⅳ』を紹介しました。
一般向けの哲学紹介本の中でも、本書は一味違った楽しさがあります。
書誌情報
* 出版社
* NHK出版(NHK出版新書)
* 発売日
* 2025/9/10
* 編者
* 斎藤哲也
* 人文ライター。1971年生。東京大学文学部哲学科卒業。著書『試験に出る哲学』シリーズ、『哲学史入門』シリーズ(NHK出版新書)、監修に『哲学用語図鑑』(プレジデント社)など。
* 目次
* 序章 倫理学に入門するとは何をすることなのか(古田徹也)
* 第1章 現代に生きる功利主義―誰もが幸福な社会を目指して(児玉聡)
* 第2章 義務論から正義論へ―カントからロールズ、ヌスバウムまで(神島裕子)
* 第3章 徳倫理学の復興―善い生き方をいかに実現するか(立花幸司)
* 第4章 なぜケアの倫理が必要なのか―「土台」を問い直すダイナミックな思想(岡野八代)
* 特別章 「地べた」から倫理を考える(ブレイディみかこ)
構成は、編者による解説+研究者へのインタビューで、両方読むとよくわかるようになっていますが、インタビューだけを読んでも楽しめると思います。ざっくばらんな雰囲気と、論文などではあまり見えてこないそれぞれの研究者の「人間くささ」が伝わってきます。そして、本シリーズを通して読むと、哲学というのは「人間の営みなのだ」ということがよくわかります。
でもって、このⅣはまさにその「人間」に焦点を当てています。
倫理学の必要性
現代ほど倫理学の視点が大切な時代はないでしょう、と書くといささか大げさめいていますが、それでも科学の発達で「人間の拡張」の可能性が開かれたり、LLMの登場で「人間知性の拡張」が現実味を帯びてきた中で、「そもそも人間とは何か、人間として生きるとはどういうことか」を問うことは欠かせないように思います。
また、インターネットとスマートフォンの普及によって、これまでになかった規模や範囲で人と人の交流が生まれるようになっています。人間(じんかん)を捉える視点が、これまで長く続いてきた社会とは大きく異なりはじめているわけです。目の前に顔が現れ、文脈を共有し、共感が働きやすい共同体とは違った関係において、その関係を維持したり、よいものにしたりする能力を磨くことも必要でしょう(少なくとも生得的な能力としては持っていなさそうです)。
加えて言えば、現代では市場原理があまりにも強くなり過ぎています。あたかも「原理」がそれしかないかのように扱われています。しかし、アダム・スミスが道徳を論じたように、市場に参加する人の感情的能力があってこそ成り立つものがあるはずです。それを無視して、システム=メカニズムを整備すればうまくいくという考え方は、あまりにも見過ごしてしているものが多いと感じられます。
そのような単一の原理の一強体制は、市場だけに限りません。本編でも触れたように「正義」の原理だけが重視され、ケアの倫理が無視されてきた歴史も同様でしょう。もちろん、それぞれの時代においての最善はなされてきたのだと思います。だからといって、それをこだまのように繰り返せばいいとは言えません。「解釈と批判」を続け、その時代に必要な新しい視点を確立していく必要があります。
というよりも、そのような営みをずっと続けてきたのが「人間」なのかもしれません。だとすれば、「人間」の終焉がありえるとしたら、そのような営みが閉じられるタイミングなのでしょう。

48 Listeners

5 Listeners

0 Listeners

17 Listeners

244 Listeners

67 Listeners

17 Listeners
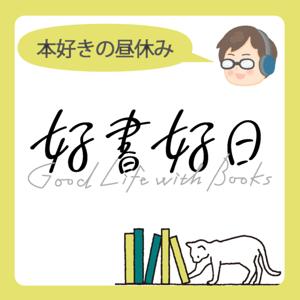
1 Listeners

18 Listeners

1 Listeners

6 Listeners

2 Listeners
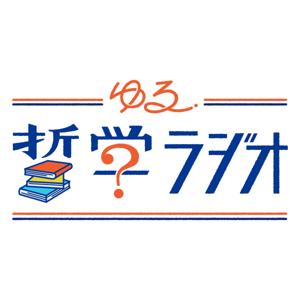
3 Listeners

9 Listeners
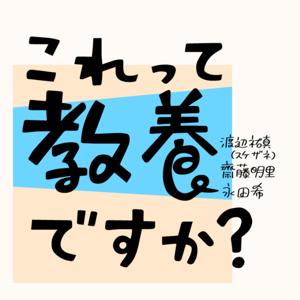
0 Listeners