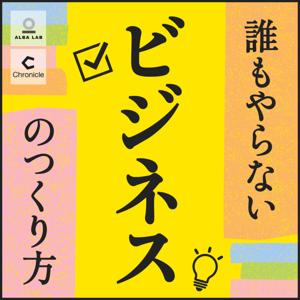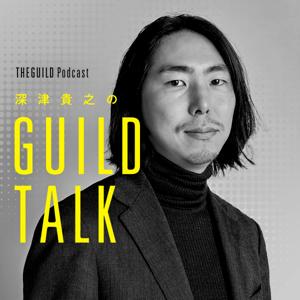組織には多様性があるものだが、ただいろいろな価値観を同居させるだけだと、コミュニケーションやコラボレーションが生まれにくいばかりではなく、むしろ喧嘩が起きたりする。多様性を価値にアップデートしていくためにはどうすればいいのだろう?ということを考えたい。特にスタートアップなどの小さいコミュニティにおいては、長い歴史があるわけではないのに慣習がいつの間にか文化になっており、新しくジョインした人からするとその文化が「ノるべき文化なのか、問い直すべき文化なのか」ということの判別がつきにくい。近年、ダイバーシティとともに語られる言葉として「協調性」があるが、それは本当なのだろうか?多様さを受け入れるためには、対話が必要になる。明確に違う足場や文化を持った人同士が、お互いへの理解の解像度を上げて、AとBという別々の案で終わるのではなく、新たな案Cを生み出していくことが大事になる。このとき、AとBという異なるものを「異なる」と認識できる第三者的な存在がいて、その人が新たなアイデアCを良いものとして認めてあげるファシリテーター的存在が必要になる。小さい組織だとそれが経営者の仕事になるのではないか。違いから摩擦が生まれたとき、「重なる部分はここだから〜」と摩擦をおさめる方向にファシリテートしてしまうのではなく、そこから一歩踏み込んで背後のWHYを深ぼる信念が必要になる。そうして初めて、多様性が対話を通して価値になっていく構造が生まれていく。




 View all episodes
View all episodes


 By CULTIBASE(安斎勇樹、ミナベトモミ)
By CULTIBASE(安斎勇樹、ミナベトモミ)