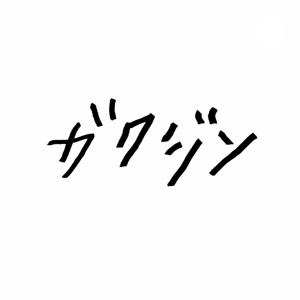インディペンデント・キュレーターの池田佳穂さんは、GAKUのアートのクラス「歓待としてのキュレーション」において、「社会と接続したキュレーション」と、それを実現していくために「領域横断的なキュレーター」であるということに力点を置かれていました。そのようなキュレーション観の基盤にあるのは、インドネシアを中心とした、東南アジアのキュレーションカルチャーに触れた経験であるそうです。「日本のキュレーションは西洋の博物館学、つまり『ものをセレクトする』ことがベースにありますが、東南アジアでは、DIYではなく『DIWO(Do it with others)』と言われるほど、人の繋がりや関係性が重視されています。その根底にあるのは『交流することが可能性を広げる』という考え方です」とする池田さんの考え方は、アートのみならず、都市や文化に拡張していくと、どのような展望や探求が広がるでしょうか。
今回は、池田さんと、まさに池田さんが多くのインスピレーションを受け、そして「歓待としてのキュレーション」のゲスト講師としてお招きしたレオナルド・バルトロメウスさんが、活動を振り返りながら、アートやキュレーションや文化について語り合う機会となりました。
出演:Leonhard Bartolomeus(キュレーター)、池田佳穂(インディペンデント・キュレーター)、熊井晃史(GAKU事務局長)
ジングル:newtone by Mecanika [MARU-169]
ホテルはまさに歓待の舞台/インドネシアで出会い、9年来の付き合いとなる池田さんとバルトさん/ルアンルパで学んだこと/コモンプレイスをつくる、というキュレーションのあり方/オープンスペースとオープンソース/教える・教わるではなく、それぞれが持っているものを分け合うという学びの空間/ドクメンタ15でのルアンルパの実践/展示会場にキッチン?宿泊施設?!/「展覧会は社会的な遊び場」であるべきという姿勢/「カルチュラル・ワーカー」という言葉に救われた/分類し得ない存在と営み/文化実践としての「池田バー」/「カルチュラル・アクティビスト」と名乗っていたルアンルパ/独裁政権下のインドネシアでは、5人以上で集まることができなかった/集うことの切実さ/生きることとアート、学びが遠ざかっていかないように/バルトさんによるYCAMの「遊べる図書館」/誰しもが、一緒に遊んで学ぶことが作品になる/アートかアートじゃないかではなく、まずはやってみる/バルトさんの座右の銘「アートより友達」/バルトさんと池田さんからのお知らせ
このPodcastは、GAKUが東急株式会社と共催で実施しているクラス「歓待としてのキュレーション」の活動の一環として収録、配信しています。このクラスは、10代が渋谷を舞台にアートキュレーションに挑戦していく機会となりますが、同時にテーマに関する探求を深め、それを10代の活動とともに広く発信していきたいと考えています。前回の配信は「革命としてのピクニック」。「東京ピクニッククラブ」を主宰する建築家の太田浩史さんのお話は、ピクニックという営みが宿していた革命性を浮かび上がらせるものでした。そして、池田さんがインドネシアのアートシーンでの実践から学び大切にされているキュレーションのキーワードである「ノンクロン(無目的にダラダラ過ごす)」「マジェリス(時間を厭わずに話し合う)」とも重なっていくものでした。是非、合わせてお聴きください。