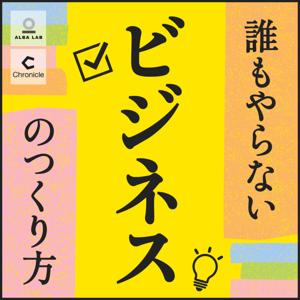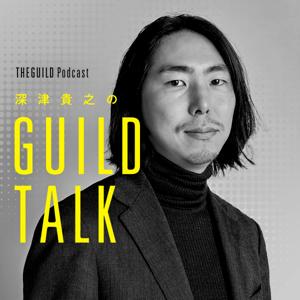「遊びのデザイン」はCULTIBASEでも3回の連載記事を掲載しているだけではなく、いずれ本として出版したいと考えているテーマ。1回目は理論をメインに紹介した内容だったが、2、3回目では「ワークショップで既存のものをぶち壊したくなる衝動をいかにくすぐるか」、「中学生の観察力がついつい磨かれてしまう遊びをデザインするには」など、具体的な事例を紹介している。「もともと人間が持っている内発的動機付けをくすぐる」というのが遊びのデザインの一端であるが、これをもっと日常レベルでできないだろうか?というのが今回のテーマ。例えば、Slackのスタンプやbotには、会社の文化が滲み出る。それぞれに「押したくなるスタンプ」や「押されるとなんか嬉しいスタンプ」があったりする。遊び心とは、そういう些細な一面に仕込まれているものなのかもしれない。ミナベの芸風は「雑味」を残したデザイン。堅い空気が漂う会議であえてアジェンダを壊しにいってみたり、マーケティング施策として「お堅い社長にYouTuberとしてデビューしてもらいましょう」という提案を盛り込んでみたり。特に組織論ではシステム化や効率化を重視するが、そうすると「納得はするが感情的に乗らない」ということが起きがち。だからこそ「目的とKPIに合致してはいるが、HOWがとてもくだらない」というような余白(=遊び)を入れることが大切である。




 View all episodes
View all episodes


 By CULTIBASE(安斎勇樹、ミナベトモミ)
By CULTIBASE(安斎勇樹、ミナベトモミ)