
Sign up to save your podcasts
Or




 View all episodes
View all episodes


 By CULTIBASE(安斎勇樹、ミナベトモミ)
By CULTIBASE(安斎勇樹、ミナベトモミ)




5
11 ratings


16 Listeners

229 Listeners

18 Listeners

0 Listeners

6 Listeners

4 Listeners

2 Listeners

1 Listeners

1 Listeners

10 Listeners

1 Listeners
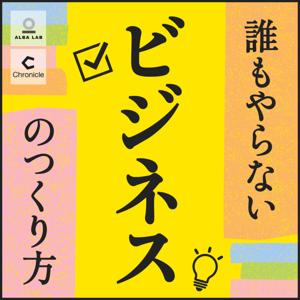
0 Listeners

0 Listeners
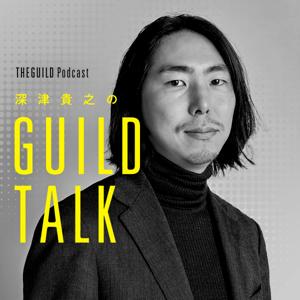
0 Listeners

18 Listeners